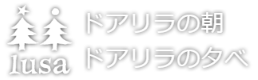時ならぬあたたかな日和が続いて、4月4日にはキタコブシ(北辛夷/モクレン科モクレン属。キタコブシはコブシの亜種。多雪地帯に多いという)が咲きはじめていました。
キタコブシは春の使者です。
野山に自生する似たようなモクレン属(=マグノリア)にタムシバ(田虫葉)というものがありますが、コブシの花の下には小さな葉が1枚つくのに対してタムシバにはありません。
さらにタムシバの花は全体が白であるのに対して、キタコブシの場合は花の基部はほんのりあかむらさきの色が差しています。
そんな日に、ここから約1キロほど離れた施設近くにサルの群れが来ていました。
雪が消えるとサルは例年真っ先に現れるのですが、何をしに来るのかというと、キクイモ(菊芋/キク科ヒマワリ属)の芋(塊茎)がめあて、塊茎を掘って食べているのです。
ここは耕作をまったくしていないのに土がやわらかくところどころ凹凸を作っていますが、これはイノシシの仕業。アナグマも加勢しているかもしれない。
イノシシが土中のオケラとかミミズを求めて土を掘り返し引っ掻き回してはまるで耕したように程よい空気を入れ(時に落とし物もするだろう)、そこに根を張ったキクイモが塊茎を作って増え、それを冬の間満足な食事にありつけなかったサルが掘って食べて腹を満たし(時に落とし物もするだろう)ているのです。

堅い土→イノシシは土中生物を漁(あさ)って、結果として耕し→キクイモはよい環境を得て塊茎を作って繁殖し→サルは塊茎を掘り出して腹を満たし→キクイモはさらによい環境を得て塊茎を増やし、美しい花を咲かせ→固まった土をイノシシが耕し……、何という見事なサイクルだろう。
ヒト属の食糧も消費電力エネルギーも、こんな無理のないサイクルだったらどんなにいいだろう。
ちなみに下は9月末の同じ場所の、キクイモの花畑。
*
で、計測地点に自然積雪がまだ60センチあった3月27日、日当たりよく雪が解けて土が見えはじめた薪小屋の南に、真っ先に顔を出したのがフキノトウでした。見つけたのは堅い蕾のふたつ。
ふたつばかりではなあ、食べるのもなんだなあと思い、石見(いわみ)焼きの器に水を張って浮かべてしつらえてみました。
少ししたら、花が開きました。リビングに一足早い春がまたひとつ。
3月下旬から4月上旬にかけては一気に気温があがって雪が急激に解け、そうしてフキノトウはここにもあそこにも、そこかしこに。
我が家で山菜として採るフキノトウの第一は、まだ花があまり開かない堅い蕾のものです。
これをてんぷらにしていただきます。また、刻んで散らして、味噌汁の実にします。時にはふきのとう味噌なども試して。
ほろ苦い野生の香りがあたりに漂って春を感じさせてくれます。
コナラ(小楢)とハリギリ(針桐)の葉を毛布にして出てきた、まだ堅い蕾のフキノトウ。
フキノトウは春告げの花。
フキノトウは、長い間雪に閉ざされた雪国にようやく春がきたことを知らせてくれるうれしいシグナルです。
筆者は子ども時分からそれがうれしくて、あたたかくなって雪が解けた南斜面の葦原(あしはら)にいち早く出てきたフキノトウをスケッチしていた記憶があるほどです。10歳に満たない少年も、描いては春がきたことを身体にしみこませたかったのだろう。
春がくるという喜びとフキノトウの姿は不可分に結びついているのです。
雪国の人間と南のあたたかな気候のひとたちとではフキノトウを見つけたときの感情の発露はきっとちがうのでは。よって、それを食材とする料理への愛着もちがうかもしれない。
そんな折、Aさんからフキノトウを描いた絵手紙が届きました。
上手いなあ。地上部すぐの赤味の差し具合が何ともいい。葉っぱと茎の質感、肉感のよさ!
Aさんは季節折々にその時々の植物を描いて送ってくれますが、彼女もまた春を身体にしみこませたかったらしく。
フキノトウは蕗の薹。
蕗の薹はフキ(蕗/キク科フキ属)という植物の蕾またはそれが育ったもの(しかしこの“薹”、むずかしすぎてゼッタイ覚えられない、書けない、覚える気にもならない)(笑い)。
蕗の薹の“薹”は茎(くき)のことを指すので、かな(カナ)で正確に表そうとすれば、「フキのトウ」または「ふきノとう」なはず。それが「フキノトウ」や「ふきのとう」のようにひとつにくっついてしまっています。
フキは雌雄異株。雄株と雌株があります(こんなことを知ったのは近年です)。
下は、雌株。
これは雄株、
これも雄株にして、
こっちは雌株。
黄色みを帯び大粒の花(頭花)をつけるのが雄株で、比べて小粒の白い花をつけるのが雌株です。
雄株は花粉をつけて昆虫に提供し、花が咲き切ると株自体が枯れて消滅します。
雌株は花をつけたあとに大きく育って、やがてたんぽぽの綿毛のような種をたくさん作って風に飛ばされます。
大きく高く育つのは、よい風を受けるためですね。

そういえば、フキノトウには発がん性物質が含まれているということが話題になり(1980年代初頭だったと思う)、筆者の若い日のあこがれだった国分一太郎(こくぶんいちたろう/1911-85。山形県東根出身で戦中戦後を通じて“綴り方教育運動”を主導した。筆者は国分晩年の82年の秋に東京中野のご自宅にお訪ねしたことがある)が、雑誌か著書でそのことを憤慨していたことを思い出しました。
生まれ育った田舎をこよなく愛した彼には思い出多いフキノトウに発がん性物質が含まれているなど、とても認めがたく許せないこと、おのれの出自やアイデンティティーを否定されたような感覚だったのだろうと思います。
マスコミって、物事をセンセーショナルに伝えてひとびとの興味をことさら引こうとするからね。それは今も変わらないけど。
なお、この「発がん性物質」とは“フキノトキシン”のことで、水溶性にして、さわしたり茹でたりすると消えてしまうようなものとのこと。
それよりも、フキノトウにはたくさんの効用があります。
ビタミンA(抗酸化作用)、ビタミンB群(代謝促進)、カリウム(体内調整)、ポリフェノール群(肝機能向上)、ケンフェール(免疫力強化)、フキノリド(整腸作用)、葉酸(貧血予防)など効能は多大で、身体に害があるどころか健康にすこぶるよいということです。※web日本educe食育総合研究所、などより。
だ、そうですよ、国分さん!ご安心あれ! 草葉の陰からでもフキノトウを誇らしく思われたし!です(笑い)。
*
そして雌株も消えそうになる頃にその地下茎から心形の大きな葉が出てきて、これがフキ(蕗)本体の柄(葉柄)と葉になるというわけです。
フキの茎(葉柄)を採って“キャラブキ”とか“炒め煮”にしたことのあるひとなら分かると思うけど、フキの茎って、樋(とい)のようにくぼみが走っているのですが(切って断面を見ると、極端に言ってU字になる)、その形状は、大きな葉を漏斗(ろうと)遣いにしてわずかな水でも集め、樋を通して水を確実に茎の直下つまりは地下茎(または根)に染みわたらせるためのものというわけです。
スゴイ造形です。フキはそれだけ水を欲し、水への渇望がこの形になったということですね。
自然って、スゴイなあ。
自然は美しくこそあれ、いやしい相貌を決して見せない。
このフキ(自生の山蕗)の炒め煮がとにかくうまいんだよね。
ごま油で炒めて、醤油と酒とみりんで味を調えて、タカノツメを加えて。
時期になると筆者は野に出て採取し、これをよく作ります。
と、ひさしぶりにわが青春の(笑い)よしだたくろう(吉田拓郎)を何気に聴いていたら、いつの間に、「フキの唄」2009なる歌を歌っていたのですね。
拓郎らしいテンポがあって、いい曲でした。拓郎はまだ枯れていないね(笑い)。
その歌詞にこうあります。
…僕が子供だった頃/日本は貧しくひ弱で/お金もなく肩寄せあって生きていた/物が足りないのは/みんな一緒だし普通だし/何より平和が大切でありました//僕はフキが大好きです/毎日でも食べたくなる
そうだったんだね。
つまり拓郎は幼き佳き日のニホンの(そして自身の)暮らし向きにフキを重ねているわけだ。このことに共感するひとも多いのでは。
筆者の場合は幼いころに重ねてというよりも、年を重ねるごとに魅力に気づいて好きになってきたという感じ。近年は特にです。
横道にそれます。
テツオ君のマル秘もマル秘事項にかかわることだけれど(笑い)、筆者はラジオ(文化放送「加藤諦三のセイ!ヤング」)に投稿し曲をリクエストしたことがあるのです。それも中3の秋のただの1度だけ。それは、たくろうの「今日までそして明日から」であります(笑い)。
「……、それでは山形県のホンマテツロウ君からのリクエストです、どうぞ!」…。
いやあ、なつかしい!(笑い)。
*
Aさんがしたためたのは、フキノトウでもトウ(薹)の立ったもの。
画面にAさんは「これぐらいがうまい」と大書しています。
そうなのです。「これぐらいがうまい」のです。
下は、トウの立ったフキノトウの群落。郊外の田んぼのへりにて。これはすべて雄株のようで。
Aさんの絵も雄株のようで。
いつもの散歩コースから採取したトウの立ったフキノトウ。
実はこのトウの立ったフキノトウが料理の材料になると知ったのはここ30年ちょっと前のこと。昔ではなく、いわば近年の範囲です。
最近地区の何人かに聞いたら、「ずっと前から食べていた」というひともいたので知らなかったのは筆者たち一部だけかもしれないのだけれど(Aさんが知ったのはここ10年15年くらい前だった、少なくとも幼いころは食材ではなかったという)、フキノトウの価値というのは、あくまで蕾しかも花が展開しない堅いものであったわけです、筆者的には、それまでは。
ルーザの森に越してくる(1993年秋)以前の市中暮らしの時、家族でワラビを求めて近郊の野山を歩いているおりに、フキノトウの大きな花がたくさん捨ててある光景に出会って不審に思ったのです。
そうしてそれは、持ち帰るに嵩(かさ)ばってしまうので不要なものとしてちぎり取ってしまって捨てたと推測したのです。
それからほどなくです。フキノトウのトウの立ったものも実はおいしいと知ったのは。
堅い蕾の味噌もてんぷらも汁の実もいいけれど、トウの立ったフキノトウを油揚げやこんにゃくと一緒にした煮びたしはとてもおいしい。
キドさ(苦み)をわずかに残しつつ、茎はやわらかく、味がしっかりと染みて…。それはまさに春の味というものなのです。
これはひとつの、カルチャーショック!
なぜそれまでこんなおいしい食べ方を知らなかったのか!
今では我が家は、旬にたくさん採っておいて、茹でて冷凍保存をして冬場にも煮びたしをしているほどです。
ちなみにだけど、米沢にお住まいだった在野の植物学者の清水大典さんが著した『山菜全科―採取と料理』家の光協会1967には「食用部位…つぼみのときの花茎(フキノトウ)、葉柄、葉」としかありません。もしトウの立ったフキノトウの茎なら別の書きようがあったはずです。
また、筆者が山菜についてよく参照する『Outdoor』山と溪谷社1997の付録『山菜フィールド・ブック』にも食用は蕾についてだけしか記していません。。
さらに、筆者の大切な愛読書『柳宗民の雑草ノオト(1.2)』毎日新聞社2002でも蕾のままの料理しか紹介はありません。
つまり、トウの立ったフキノトウの茎を食材にするということは、一般にはいまだあまり知られていないことなのではないでしょうか。
でもどうしてこういう調理法が今まで知られていないのだろう。知られてこなかったのだろう。なぜひとびとはずっと昔からこれに気づいて伝播し、拡散させ、広めなかったのだろう。
それは、より小さな単位で地域が想像以上に閉鎖状態だった? それとも、秘伝として教えたくなかった? そんなケチくさいことではないと思うのだが…。
山菜王国の秋田に最近にしてようやくコシアブラの食し方が伝わった(『秋田春夏秋冬こぼれ話』カッパプラン2008)というのと似て、何とも不思議と言えば不思議なものです。この情報化時代の現代にねえ。
そして、“蕗の薹の薹”、つまりトウの立ったフキノトウの煮びたしの出来上がりです。いただきまーす。
んーん、おいひー!(笑い)。んめー!(笑い)。
と、この9日は一日中雪降り。あたたかさに慣れてきた身は縮こまり…。
でも、そんなルーザの森にも春が来たのです。ケタケタの春です。
それじゃあ、バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。