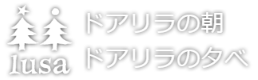ルーザの森クラフトの、工房の増築日誌4。棟上げと骨組み。
(2020年の)5月の連休前ともなれば、世の中、コロナ、コロナで物騒になって、町内のガソリンスタンドに入れば、「大丈夫だか(感染してないか)?」があいさつ代わりでした。
そんなあいさつを受けて筆者は、「大丈夫、大丈夫、うちはもう30年選手!」と答えればスタンドのオヤジは怪訝(けげん)な顔をするので、「ストーブのことよ、コロナストーブ!」(笑い)(大笑い)。
トヨタの名車もコロナだったし、何よりストーブの信頼のブランドのコロナ。このご時世、コロナの社員、その家族はたいへんな精神的苦痛を味わったのだろうな(しかも現在進行形で)と想像していました。
コロナの(対流式石油)ストーブが30年と言ったけど、これは芯を1回取り替えただけで、故障らしい故障がない素晴らしいストーブなのです。
今、心底から叫びたくなります。「ガンバレ、コロナ!」と。「フレー、フレー、コロナ!」、「コロナ禍に負けるな、コロナ!」と。
時は早、山菜の季節、5月に入りました。コシアブラ(漉油)がちょうど摘み頃を迎えました。
基礎に土台が据えられ、いよいよ上棟、そして主体工事のメインである構造躯体(骨組み)の組み立てがはじまります。
ここでちょっと、本当は、日誌1で触れる方がよかったかなと思うことを差しはさみます。工法のことです。
というのは、日誌の1と2を読んだ方からメールが来て、「知人から、一間くらいの小さな家(小屋?)なら自分でも建てられるとざっくりその行程を聞いてその気になっていた」というのです。ここはすっきりはっきりさせていた方がよいなと思われたので。
木造建築の場合、大きく言ってふたつの工法があります。
そのひとつは筆者がずーっと変わらずにこだわってきた“和小屋軸組構法”という、日本の在来の代表的な建築法(在来工法ともいう)です。これは、基礎の上に土台が載り、
もうひとつが2×4(
こう言っては失礼になるかもしれないけれど……、西洋で開発され、したがって西洋の家屋に一般的で、日本にも浸透してきたツーバイフォー工法は工事が安易で簡単だと思います(アパートの建築現場をのぞくと、けっこうこの工法が採用されているよう。一般住宅でも数日で完成するようなものもこの工法を採用していますね)。
ツーバイフォー工法は2×4材に合板を張りつけて壁を作るのが基本ですから、規格の材料をそろえドライバドリルとビスがあれば作業は誰でも容易なのではないでしょうか。壁を必要な枚数だけ作り、あとは金物で連結すれば箱はできあがります。屋根も同様、トラスを(三角構造)を必要数作り、それを箱の上に載せ、連結すればよいわけです。
正直言って筆者には、こういったツーバイフォー工法には建築の妙味が感じられず、技術の習得の初期段階から興味がなかったです。というよりも筆者は、日本の大工と、大工が長年培ってきた技術にほれ込んでリスペクトしているのです。
材料の性質を見抜いて適材適所に配る、木材の癖を生かす、癖を取る、躯体を強固にするために“仕口”と“継手”を工夫する、そうして日本の大工は徹底して木材と向き合って、よりよい建物を建てようとしてきたのです。そこには、当然ながら大工の技術をはじめとして愛情や心意気が余すところなく注ぎ込まれます。
筆者の主屋が完成したのは1993年の晩秋のことだったけど、棟梁が、これがオレが作った家だと言って連れてきた奥さんに見せていた光景は、施主でありながら清々しいものでした。それは、大工が誇らしい仕事をした印でした。それはとてもうれしかった。
(その時まで筆者は、建築の技術はおろか知識もまったくなかった)。
筆者が在来の和小屋軸組構法を採用しているというのは、単に建物を建てるというにとどまらず、その精神的な香りをも体験したいというあこがれからきていると言えば大げさに聞こえるでしょうか。そう、筆者にとって、建物を含めたモノは、対話あるいは会話の対象なのです。モノは語ります。
土台に、1間(けん。約182センチ)置きに柱が立ちました。
下は、工房の増築では屋根を同じ角度で連結させる方法を取ったので(屋根の下に新たな屋根を作る方法もあって、こちらの方が簡単なのだがあえてむずかしい方法を選んだ。すべては出来上がりの見栄えから)、それを計算に入れて梁の出の位置を決め、ホゾの差込口にドリルで穴をあけ、ホゾ穴を手ノミで整えているところ。
この、位置の計算が狂っていずにほっと胸をなでおろしたものです。
1間分の4本の梁を元の工房の壁面(の東側)に継ぎ足しました。
この作業はひとりでできるものではなく、相棒のヨーコさんに助手を務めてもらいました。
落としどころを掛矢(かけや)でたたいて、“軒桁”を据えつけました。
これで、基本の骨組みができました。
春は進行して、イワカガミ(岩鏡、岩鑑)が野山に、敷地にも咲きはじめました。
もう山菜の最盛期で、どうしよう、山菜採りに行こうか、建築を進めようかと本当に迷い、とにかく時間を見つけては山へ(といっても10分ほどのところ)、山から帰れば大工仕事と、身体はいつにも増して休まらず、身体はいくつあっても足らず。
申し訳ないが、世の中新型コロナ、コロナコロナで右往左往する中にあって、こちらの生活への影響はほんのわずかです。買い物で出るときぐらい(つまりコロナ禍というのは……、ウイルスにしてみれば、ひとが多く集まるところがとても好きで、そこには宿主になってくれそうな人がたくさんいて、うれしいということ。ウイルス禍は、賃金が高いとか、交通が便利だとか、華やかであるとか、賑わいがあるとか様々な理由で、地方から田舎から離れて都市へ都市へと流れた人口移動を嗤っているかのようです。当然これは、市場原理を重視する経済思想である“新自由主義”が背景にありますね。でもようやく人々は事の本質に気づきはじめましたかね、都市空間は人間らしい暮らしを営むには不都合であり不似合いだということを)。
下は、見る者にとっては奇妙な写真と思います。“アンカーボルト”(基礎と土台をつなぐ金物)を切断している図、です。
なぜ?
“普通ボルト”(木材同士の締め付けや羽子板ボルトの固定などに使用)がなくて必要なら買わねばならず、アンカーボルトは以前の建築の際に買いすぎて余っていたので、アンカーボルトを普通ボルト代わりに加工しているのです。
これを見た大工は、呆気に取られていました(笑い)。普通、いくらなんでもこんなことはしませんからね(笑い)。
下は、“タップダイス”(ねじを切る道具)のダイスを使って、アンカーボルトのねじ部を切断して、あらたに“雄ねじ”を切っているところ。
タップダイスの作業は本当に久しぶりの感覚です。直筒の丸い金属棒が手の力だけで雄ねじに変化していく様は目の当たりにすれば気持ちがいいものです。
このねじ(螺子)というもの、1543年の種子島の鉄砲伝来によってもたらされた(鉄砲の伝来よりもはるかに大きな意味を持つ)画期的な技術でした。
切って作った短寸のアンカーボルトは普通ボルトの役目を担って、2か所の“火打ち梁”(梁と軒桁の直角を強固にする材)を連結しました。これは胸がすく作業でした。
この増築工事の要諦は次の写真に最も顕著です。
屋根の軒先(“垂木”の先)に当たる箇所に“束”(つか=小屋束。縦の短い柱)が立っているのが分かるでしょうか。さらに右に左の束よりもさらに短い束も立っています。元の建物と同じ角度で屋根を延長するためにどうしても必要な、しっかり計算せねばなしえない難工事がこの小屋束の作りであり、位置だったのです。
左の束が重要なそれで、この上に“母屋”が載っていますが、この母屋こそが元の軒先の垂木を載せ、新たな垂木をさらに継いで載せる役目を担っているのです。
正直に告白しますが、筆者はこの部分ができませんでした。
この日の作業にはお願いしてS大工に入ってもらうことにしていて、さっそくにも出来上がっていた束の寸を修正してもらったものでした。都合8本の束すべてが60ミリずつ狂っていた、ということでした。これはしたりです(笑い)。
さらに、母屋の垂木受けの欠きが甘く、水糸を張って正確に欠きの深さを出してもらい、手ノミで何か所かを刻んで欠いてようやく垂木を載せたのでした。
この作業は、悔しいけれども自分ひとりではできませんでした。大工の経験と技術の確かさに触れたひと時でした。
知恵を絞って奮闘するS大工。余裕の笑顔(笑い)。
庭に、めずらしいウスギタンポポ(薄黄蒲公英)が咲いて。
“野地板”(屋根の下地の板)張りは自分でも十分できることですが、「急ぐべ!」というS大工の意向で(彼には時間が限られていた)、電動釘打ち機を使って短時間でやってのけてくれました。こちらは、言われた通りに必要な寸の野地板を切って差し出しただけです。
これは5月5日のこと。工房前のブナ(山毛欅)の黄緑が初々しいです。
野地板が張られたとあれば、あとはトタン葺きをお願いする手前、作業がふたつ残っています。
さっそくにも、防水のルーフィング紙を敷きました。
このアスファルト・ルーフィングは1巻で重量が25キロもあり(本当はこれよりも軽く安価なものはあったのですが、どうせならと思ってより強力な防水性能を持つものにしたのです)、これを屋根まで担ぎ上げ、横に這わせるのはちょっとしたひと苦労でした。
下は、増築分の“破風板”を継いでいるところ。ここに、小割の“登り淀”(垂木の“鼻隠し”の板の上には小割の“広小舞”が既に設置済み)を取りつければ、あとはトタン葺き職人にバトンタッチです。
以上、建築用語のオンパレードでスミマセン。
トタン葺きには、S大工の紹介で、隣の町内会のS屋根葺きが仕事の合間を縫って駆けつけてくれました。ありがたいことです。
作業をしながらも、屋根葺きの仕事の要点やその技術の一端をていねいに話してくれました。
職人と話しているのはとても勉強になるし、楽しいです。
「(トタンは下から葺いてくるのだが、増築の際のトタン葺きの)最後には“三角”(建築の隠語で左右の寸法が同一でなくなること)になることが多いが、お前のは左右両端が同じ、大したもんだ」とほめてもらったくらいにして(笑い)。この“三角”の意味がよく分かるなあ。
こうして、下の写真で増築の図がはっきりと見えてきました。この部分を広げたかったのです。
よく、ここまで来ました。よい景色です。
屋根がかかればこっちのもの、雨が降ったとて、こちらのペースでいくらでも仕事ができます。
ひとの暮らしの歴史の中で、屋根を得てどれほど生活の幅を広げたことかを時に思ったりします。
家屋の初期段階の洞窟にしても、土手の壁を掘ったものにせよ(ローラ=インガルスが著した『大草原の小さな家』でも、こんな時代がありましたね……「プラム・クリークの土手で」)、縄文の掘立小屋でも、住む場所に天から雨が入ってこないというありがたさをつくづく思うのです。
家屋の躯体を頑丈にする重要な工事である、柱と柱の間に1.5尺(約45.5センチ)のピッチで“間柱”を入れ、“筋交い”の取りつけに入りました。
筋交いは四角形を分割して三角形を作るもので、これは想像以上に家屋の頑丈さを高めるものです。柱のコーナー2か所に“大入れ”の欠きを入れ、間柱に筋交いの厚みである3センチの深さの欠きを入れます。この作業は、丸ノコと手ノミが主に担いました。
現代のハウスメーカーの家屋では、こういう面倒な箇所を効率化・合理化の名のもとに省く傾向があります。刻みと欠きを省いてはやおら金物で補強するわけです。こういうところが大工の見せ場だというのに、ったく!
当然、強度には雲泥の差があると思います。
写真は、刻んで欠いて、筋交いをぴったりに納めたところ。
ヤマブキ(山吹)の花咲く頃となりました。
窓台に窓枠が入りました。
増築分の南北のふたつの窓は新品です。当然にも、高価でした。
東側の窓枠は元のものを取り外したもの。これはガラス窓ともども、中学校の解体現場から解体直前に取り外していただいてきたものの再利用です。
窓があって、そこにガラス窓が入るというのはとても素敵なことです。
先のローラ=インガルスの著作にあったことだけど、「父さん」がようやく手に入れたガラス窓が窓枠に入った場面の家族中の喜びようは今でも印象深くあります。
室内から外が見える、しかも風の影響を受けない、風が欲しい時には開け放つことができる……、現代ではまったく当たり前のことですが、窓の原点に帰ってみればこれほどの喜びはまたとあるでしょうか。
筆者は建築に勤しみつつ、こういう素朴な喜びを時としてかみしめるのです。
内部の上部の構造がよく見て取れる1枚。
と、窓枠から、現場監督がひょっこりと顔を出しました。
しっかり働いているか、監視かなあ(笑い)。
これで、日誌4、「棟上げと骨組み」はおしまいです。
次回はいよいよ最終回、日誌5、「内外装とレイアウト」。どうぞお楽しみに。
これからちょっと夏の休暇をとるので、次回は本当に日を置き、日を改めて、です。
それじゃあ、またね!