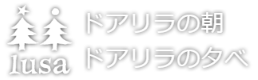シラベやブナの薪のくすぶる烟り、香り。急に焰を吹出すときやはぜるときの音。誰かが戸をあけた拍子に風が吹込み、煙がまわって眼に沁みるあの渋い刺戟。いぶされて黒光りする柱やタル木。その天井の闇に吸込まれていく火の粉。自在鉤には木の子の煮える鍋。大きな囲炉裏のカマチに雪だらけの脚を踏込ませ、ドブロクの茶碗を手にする男たち、そんな風景は、眼を閉じなくともアリアリと私には見える。
そこは久しく私にとって学校であった。
炉辺というのは不思議なものだ。炉を囲んで焰を見ている夜は、たとえ沈黙が一晩中続いたとしても、人々はけっして退屈もしないし気詰りなおもいもしないのだ。反対にまた乾いた喉に渋茶がそそがれ、あるいは盃代りの茶碗が回り、誰かが賑やかにしゃべりはじめても、そう邪魔にならないだろう。相槌を打っても打たなくてもいいのだ。語り手は半ば焰を聴手とし、人々は燃えうつり消える熱と光を濾してあるいは遠くあるいは近く、そこから生れてくる話を聴くのだから。(略)
で私はささやかな薪を拾って、ここに並べ、ちいさな焰を立ててひととき囲炉裏の仲間にしてもらえればとおもうのである。
辻まこと『山の声』東京新聞出版社1971
下は、内田耕作撮影(というクレジットのある)の辻まこと。「辻まことの世界展」目録、西武美術館1979より。
ちょうど10年ぐらい前、2010年の冬あたり、山についてのエセー(随筆)を読んでいたら、このことばの連なりに出会いました。いやあ、衝撃でした。何か心が衝き動かされるようで落ち着かず、作者・辻まことへのさぐりにまかせ、面影を求めて列車に乗って東京に行ったものです。そして、御茶ノ水の(近くに“岩波ホール”があった)小さなビルの3階、(辻ゆかりの)“茗溪堂”という書店を訪ねました。そこには山岳関係の書籍とともに辻の出版物もそろっており、店内の静謐な雰囲気にひたりつつ代表的な書物の何冊かを求めて出ました(それから約半年後に残念ながらこの店は幕を下ろしたということです)。
調べれば辻まこと(1913-75)は、詩人、エセーイストにして画家。
父親はダダイズム(既成の秩序や常識に対する否定や破壊を標榜する主張)のキーパーソンの辻潤(1884-1944。宮澤賢治の詩集『春と修羅』をいち早く評価した人物としても有名ですね)、母が婦人解放運動で知られた伊藤野枝(1895-1923。後に、大杉栄に出奔。関東大震災の混乱の中で軍部によって惨殺)。
この数行を眺めてさえ、辻まことはその出自にしてすでに柔和な魂は揺さぶられ続けていたのではあるまいかと思わされます。それを鎮めるのが山であり、スキーであり、狩猟であり、炉辺の火であった…、そういう人生であったのではとも思うのです。その彼が紡いだ美しいことば。
「語り手は半ば焰を聴手とし、人々は燃えうつり消える熱と光を濾してあるいは遠くあるいは近く、そこから生れてくる話を聴くのだから」……。筆者が募らせていた薪ストーブ(そして焚火)への思いの底というのは、辻が奇しくも文字に定着させたよう、いわばこういう世界のイマージュであるとひとり諒解したのです。
火というのは、熱とひかりとをともなって何かしらこころの奥に語りかけてくる…、その前に居れば時間は静かに満たされながら過ぎてゆく…。
そうそう、辻まことは画家でもあり。見事な油絵をたくさん残していますが、先般亡くなった俳優の八千草薫さんも所有者のおひとりでした。あるじのいなくなったその家に飾られていた「スイスの教会」はどうしたろう。特別に懇願して辻に描いてもらったという壁画はそのままひっそりと息しているか。
*
下は、ストーブについてきたカード。ストーブの前でくつろぐ少年と犬が木版画で描かれてほのぼの。
日が傾いて冷えこんできた夕べ、窓ガラスまでも凍りつく朝…、火が恋しくなります。
下は、リビングのストーブの2代目、アメリカのバーモントキャスティングス社のイントレピッドⅡ。会社によれば、イントレピッド(Intrepid)とは“勇気”とか“勇ましさ”という意味とのこと。
これはメーカー品の主流になっている2次燃焼システムを採用している機種です。炉内で燃えたものが熱い空気となってそのまま煙突に吸い込まれていくのが1次燃焼、そこで煙突への空気の流れを排出口で(ダンパーによって)閉じ込めると、空気の流れが内蔵された触媒(キャタリティックコンバスター)に入り、触媒を通過することによって未燃焼ガスが再燃焼して熱エネルギーを効率よく引き出すというものなのだそうで。薪の量も減るとのこと。
初代の“アンデルセンもどき”は当然ながら1次燃焼のみの輻射式だったのでその比較は容易です(輻射式とは、ファイヤーボックス内で火を焚いて炉全体を暖め、暖まった熱=遠赤外線を四方八方に放出する方式のこと)。2代目は取り出す灰の量がぐっと少なくなり、その灰の比重の重いことにはちょっと驚いた記憶があります。
ただイントレピッドⅡでは、リビングの広さが台所部分も含めると18畳、総吹き抜けの天井の高さが約7メートルという大空間を温めるというのは容易なことではなく、当然ながら厳寒期には補助暖房が必要となります。
ヒュッテ(筆者のデスクワークの部屋。兼、宿泊可能なゲストルーム)の完成にともなって入れたストーブは、新潟のホンマ製作所が企画し中国で生産しているMS-310TXという機種です。ホームセンター扱いの取り寄せ品です。値段は7万円弱くらいだったと思います。
ヒュッテそのもの(および併設の工房も)はほとんどの材料が廃材で、それを墨付けして刻んで自分で建てたもので、設置するストーブもすべて自分で施工すると決めていました。こういう場所にストーブとはいえ金はかけられないとの判断が働きました。当然ながら、燃焼室はひとつの輻射式、でもスタイルは美しかった。
このストーブは正解でした。45センチくらいの長さの薪も、大きなドンコロも入ります。確かに薪の量は食いますが、煙突の吸い込みがよく、燃焼がすこぶる良好です。したがってこの空間は湿度が低く、冬場の洗濯物干し場にもってこいの場所になっています(笑い)。
ストーブの右のディスプレーのスキーは、約100年前の、日本にスキーが導入されたころの輸入物と思われます。ストックなんて、竹ですからね。輪っかはラタン。
この貴重な品は、知り合いの骨董屋からヒュッテの完成記念にとありがたくにいただいたもの。
ヒュッテに併設の工房に備えられた中国製のストーブ。これはネットオークションで4万円ほどだったと思います。一応ST-0406なんていう名前がありますが、名前というよりはむしろ品番のようです。当然、燃焼室はひとつの輻射式です。高さが65センチほどで、上から見たらほぼ正方形ですので奥行きも含めてその容量は想像できると思います。
工房に設置ということは、燃料は作った薪というよりも木工作業で出た端材やカンナ屑・おが屑などが主です。でも、スマート(ストーブとして賢い働きをするという意味)だし、なかなかのスタイル!
12畳の工房にしては容量的に小さなものですが、冬場に工房に入って仕事をする分には(身体は常に動いているし)十分な能力です。ただ、工房はもう少しすると増築予定で、広さが18畳となった場合はどうだろう。ちょっと寒いかも?(笑い)。
下は、2015年から作りはじめた主屋内のアトリエ(兼ギャラリー)に設置したもの。
ネットオークションで、37,000円ほどの落札価格だったと思います。高さがわずか55センチほどのマッチ箱をタテにしたような形状です。炉内容量があまりないので、薪割りで出た小ぶりなものとか小片が燃料となります。でも6畳間のアトリエにしたらこれで十分です。当然、輻射式です。
このストーブは冬期の作業用(ドアリラ製品の塗装および最終組み立て)の暖房はもちろんですが、ギャラリーとして展示してある製品の保護の意味も兼ねています。主屋全体がそうなのですが、湿度が80パーセントぐらいと高めで、時どきストーブを焚いては湿度調整をしているというわけです。
下の写真の右がドアリラ(=ドアハープ。ドアに取りつけて、ドアの開閉によって音を鳴らす)の製品ラインナップ。
左の3点のディスプレーは、いずれも本物のマンドリン、バラライカ、バイオリン。弦楽器って、それだけで美しいですね。美しいものは、空間を変えていきます。
*
山に夕闇がせまる
子供達よ
ほら もう夜が背中まできている
火を焚きなさい
お前達の心残りの遊びをやめて 大昔の心にかえり
火を焚きなさい(略)
火を焚きなさい
人間の原初の火を焚きなさい
やがてお前達が大きくなって 虚栄の市へと出かけて行き
必要なものと 必要でないものの見分けがつかなくなり
自分の価値を見失ってしまった時
きっとお前達は 思い出すだろう
すっぽりと夜につつまれて
オレンジ色の神秘の炎を見詰めた日々のことを(略)
「火を焚きなさい」
山尾三省/詩集『びろう葉帽子の下で』野草社1993
上は、屋久島の詩人・山尾三省(1938-2001)の作。写真は、山尾三省著『ここで暮らす楽しみ』山と溪谷社1999の、高野建三氏撮影の表紙裏から。
筆者は山尾三省氏とわずかながら親交を持っていて、2000年の夏に家族(を含め、サークルの仲間も加わって計8名)で屋久島は一湊白川山(いっそうしらこやま)のご自宅をお訪ねしたものです。
詩「火を焚きなさい」は、風呂焚きの場面ですね。山尾家の風呂は今にしたら古風な五右衛門風呂で、風呂焚きの仕事は子どもたちに任せていたよう。その情景を太古からのひとの営みと現代の表層の消費文明とを交差させながら、抒情よろしく謳いあげている作品だと思います。
山尾家の子どもたちもみんな大きくなって、「虚栄の市へと出かけて行き」、「自分の価値を見失ってしまった時」があるのか(あったのか)どうか。日々に火を見つめた経験が心の底に横たわっているという、何にも代えがたい宝物がきっと己を支えることもあるはず。
夏場に小さな子どもを連れた家族が遊びにきたりする時など、子どもたちが夢中になるのは夜の火、焚火です。いつも決まって、まるで興奮状態になります。そうでしょうね、直に燃えさかる火を見つめるなんて、人生はじめてのことだろうから。
我が家も子どもたちが小さかった頃はよくキャンプをしながらの旅行をしていて、食事つくりの際のかまどの火に夢中だったものです。
我が家のストーブが薪ストーブであったということの意味も、年を重ねるにつれ増していくのかも。
*
下は、薪小屋のひとつ“キツネ小屋”の様子。このひと区画で約6立米(㎥)の容量、隙間なく積まれれば約2.7トンほどの重量です。キツネ小屋は3区画あるので、全部で約18立米、重さは約8トンにもなります。
ひと冬で、4つのすべてのストーブを合わせての消費量は、だいたい、この区画でひとつと半分ぐらいでしょうか。
薪は、外に雪のない時期は一輪車で、雪が降ればそりで運びます。時に、ちょっとしたものは薪トートバッグで運んだりします。
運んだ薪は、昔の箱ぞりのような薪入れ箱(キャスター付き)に入れてストーブのそばに置きます。
外の雪景色(これは2013年のもの)。今冬は異様なほどの気候で、一輪車での薪運びができるほど(笑い)。
吹雪がおさまって。
ストーブの上に載っているのは、MORICOの刻印があるヤカン。
ある目利きがいらした際、このヤカンを見てすぐ、“森”の名品だと言っていました。骨董屋から購入の純銅製品。
よくもこうヤカンが、と思うでしょうが、筆者の家族は冬分は湯たんぽを使っていて、湯がふんだんに要ったのです。湯たんぽというのはいいものですね。
左端の重々しいものは、かの民藝運動を主導した柳宗悦(1889-1961)が認めた「羽前山形のはびろ鉄瓶」(『手仕事の日本』靖文社刊1948)。その昔、茅葺屋根のしたの囲炉裏で、自在鉤に吊るされたものですね。骨董屋で求めたもの。でもこれは我が家での使い勝手(容量、湯たんぽへの注ぎ勝手)はよいとはいえず、今は手放してここにはありません。町場の骨董屋に持ち込むと、5,000円で引き取ってくれました。
下のヤカンは、柳の長男でインダストリアルデザイナーの柳宗理(1915-2011)のデザイン。
その座りの安定感といい、全体の重さやフォルムといい使い勝手といい、実にうっとりするデザインです。値段は10,000円ほどだったと思います。我が家の宝物のひとつです。美しいものは、こころをやさしく潤していきます。
お訪ねした家で、フライパンだとかミルクパンだとか、ソウリ(宗理)の作品を目にすると筆者は瞬時にその家をそして住むひとをリスペクトしてしまいます。
何を見て何を所有するか、それはそのひとの人生が育んだ審美眼の紛れもない反映というもので。
ストーブの上に載るのは、ヤカンだけではありません。鍋も同様。シチューやカレーの煮込み、今の季節なら何と言ってもブリ大根!、ゆっくりじっくりと食材に熱が加わっていきます。
下は、カナダはカフラモ社製の“エコファン”という製品。
ストーブの上に置いておくと、温度の上昇にともなってファンが自然に回る優れものです。熱が電気を作り、その動力で回る(ゼーベック効果というらしい)のだそうで、ファンが回ることによって空気が攪拌されていきます。これで14パーセントの暖房効率が上がるということです。
一見ちゃちな玩具のように見えましょうが、決して安価ではありません。このタイプで20,000円ほどです。
なお、この製品が認知されるようになって様々なまがい物が出回りはじめているのも事実。値段で、4~7,000円くらいと格安ですが、性能は定かではありません。
実は、工房のファンはまがいものです。これを同じストーブで同時に試した時、正規のものより回りだすのがずいぶん遅く、回転量も少なく、したがって作られる風も弱いものでした。まあ、ご注意ということですね。
薪ストーブの友、マッチ。このクラシックデザインのツバメがいいですね。
薪ストーブを使っている家で着火道具としてライター派がどれだけいるのか知りませんが、筆者はマッチがいいです。軸が燃えさしになるのですよ。
リビングのストーブ回りのグッズ類。
木製チリトリは手製、金属のものは100円ショップのもの。灰受けは懇意のガソリンスタンドでもらった20リットルのオイル缶に白スプレーをかけて。
壁にさしてある竹は、火吹き。買ってきた白竹(2メートルで150円くらい。ほどよい乾燥と熱湯処理がなされていてカビが生えない)で作ったもの。これは火起こしに重宝します。
*
筆者が暖房を薪ストーブにこだわるというのは、暖を取るのに金銭をかけないという経済的なことはあります。そしてまた、どうせ暖を得るならできればひとの感性に伝わってくるような詩的なものでありたいというのは大きな理由です。
発した熱がじわじわと身体を少しずつあたためてくれ、ぱちぱちと薪のはぜる音の心地よさはどんな音楽にもまさり、火は揺らめいて火は時に舞踏をはじめたりもするのです。もうこれだけで、こころは満たされてゆく。
また、暮らしのつつましさが薪ストーブにはあるということです。
原木を得(もらい受け)、原木を運び、チェンソーをうならせて玉切りし、玉にしたものを斧で割り、(かつては)子どもたちにそれを運ばせ、運び、積み、最低1年という時間を要して乾かしてようやく薪はでき、できたそれをストーブ近くまで運び、それをくべる…。着火してもすぐにはあたたかくはならず、消そうにも瞬時というわけにはいかない…。
つまり、“あたたまる”という行為これだけにして、こんなに手間がかかる、でもこれが生きて暮らしていることの実感のひとつだと思えるのです。こういうめんどうなことをあえて行う暮らしこそが、ひとに知らず知らずに忍び寄ってどうにも振り払うことができなくなってしまう思い上がりを消してゆくと筆者は思っています。
筆者は、原子力発電が嫌いです。不幸ばかりを生み出すから。
ちょうど最初の子どもが生まれた1986年、当時のソビエトのチェルノブイリ原子力発電所が過酷な事故を起こしました。放射能は世界中にばらまかれ、一例、はるか日本の、北海道にも降りそそいでその牧草を食べた牛のお乳から放射性物質が検出されて、良心的なブランドであった“よつば3.4牛乳”が出荷停止となりました(森永と明治など大手の牛乳からは検出されなかった事実は、与えていた餌がどういうものかが暴露されたということでもありますね(笑い))。静岡のお茶も一部、出荷禁止でした。それをみんな、日本への影響など取るに足らぬほどに一部、事故は遠い遠い場所での出来事…と思った。だから事故など簡単に忘れていった。そのみんなの積もり積もった忘却があの過酷事故、2011年3.11の福島第一原子力発電所の爆発につながったのでしたね(筆者の大切な知人も、関連死という括りで、あまりに早い人生を閉じた)。
その悲惨さは、今も続き、これから何十年、何百年と続き…。
筆者はあの3.11以来、電気を使う時はコンセントの向こう側の風景を思うようになりました。思い上がりたくないからです。
その年の9月だったか、反原発全国大集会が明治公園で開かれて参加したのですが(公園からあふれるばかりの参加者の数、そしてその熱気のすごかったこと。上の写真はその時のもの、筆者撮影)、その夜の東京の街の光景を忘れることができません。あの甚大な事故があったというのに、まるで変らぬ真昼のような夜です。真昼のような、電気を通した大音声。反省も自制もあったもんじゃない。
その夜につくづく思いました。自分で使う電気ぐらい自分のところで作れ(そんなに電気が必要で原発が必要だと言うんなら、立地は東京湾がいいんじゃないのか)! 原発で出たゴミは自分のところで保管しろ(自戒のために一部でも東京電力本社敷地にまずは置くべきだ)! これ以上、地方を犠牲にするな!
昨年の夏だったと思うけど(いやあ、暑い夏でした)、工房で作業しながら何気にNHK第1の“Nラジ”を聴いていた夕べ。暑さ対策がテーマであったものか、識者か評論家かは忘れたけどそういう立場の者が番組に登場し、ぬけぬけと、のうのうと、しゃあしゃあとこう言い放ったのです。
「私の家では、日中誰もいない時でもエアコンはつけっぱなしにしています。帰った時、涼しくて気持ちいいでしょう。電気代もそう高くつくものではありませんしね」。これにはムッときました。公共の電波を使って、ですからね。
クルマなしの田舎の暮らしが成り立たないのと同じように、電気のない暮らしも筆者にしても無理です。現在の生業(ドアリラの製作)も電動工具なしにはありえないことです。けれども、自分の中でここは減らせる、ここはなくていい、少なくとも暖房にはできるだけ電気は使いたくない…、これも薪ストーブにこだわる理由のひとつとして大きいのです。
さらに言えば、これからは地球温暖化、地球の気候変動はさしせまった喫緊の課題なんだろう。薪を暖房に使うということの大きな意味のひとつは、燃料にすでに固着した二酸化炭素である木材を使うということでもあります。
まあ以上、思い上がらずに暮らすことができる、そのステージが森だということに尽きる話ではあります。
下は、ヘンリー=デイビッド=ソロー(Henry David Thoreau 1817-62)の肖像。ヒュッテに飾っているものです。
何せ、筆者の森行き、森住まい、森の生活の先導者ですからね。
ソローって本当にまじめで純粋で、その人生たるや清澄と言ってもよいくらい。
約200年も前のひとなのに、今に受け入れられ語り継がれ読み継がれているというのは、現代という時代が混迷の度を深めてどん詰まりのところまで来ているということの裏返しでもあるんでしょう。ソローの思想は普遍的にして本質的なのです。ソローは今後も、多くのひとに大いなる示唆を与え続けるのではないでしょうか。
このシリーズで彼の言葉を何回かはさんだけど、最後の締めにも。
私が森に行ったのは、思慮深く生き、人生の本質的な事実のみに直面し、人生が教えてくれるものを自分が学び取れるかどうか確かめてみたかったからであり、死ぬときになって、自分が生きてはいなかったことを発見するようなはめにおちいりたくなかったからである。人生とはいえないような人生は生きたくなかった。
『森の生活』飯田実訳、岩波文庫
これで、薪ストーブの話は「その3」をもってひとつの区切りとします。
とはいえ、薪ストーブに関する話はまだまだ尽きません。また、いつの日かです。
*
「その1」「その2」と同じですが、youtube「薪ストーブ篇」の動画を貼っておきます。