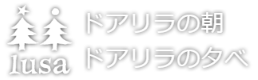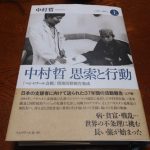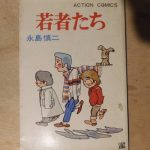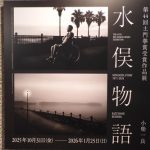本日は(2025年)11月4日、快晴です。
ルーザの森では今が紅葉のピーク、ビューポイントの笊籬(ざる)橋からのながめもさることながら、あたりはどこも黄色や赤に染まってとてもきれいです。

そして、毎年この日あたりを境に彩りは褪せはじめ、同時に落葉が進んでいきます。
あと10日もすれば木の葉は大方散って日光が林床までとどき、森は一気に明るくなります。これがブナ帯/夏緑樹林帯/落葉広葉樹でおおわれる東北の森です。この森が好きです。
あと1カ月もしたらここにも雪が来るでしょう。それまでにささまざまな雪迎えの準備をしなければなりません。
今の束の間の休息、晩秋の秋田にでかけてきました。
今回のsignalはその小旅行から、題して「泥湯晩秋」です。
*
出発したのは10月28日のことでした。
相棒は、数日前から顔を合わせるたびに「気をつけてよ!」とばかり。出発までにそれは、計32回だったか(笑い)。
連日のクマに関する報道から彼女は、パブロフの犬のごとくに条件反射です(笑い)。なんでこんな時期に、わざわざ秋田、とでも思っているんだろう。
9時頃に家を出て秋田県に抜け、雄勝から国道108号(鬼首街道)で秋の宮温泉郷方面から入って、目的地の泥湯をめざしました。
秋ノ宮から泥湯までの13キロの山道は、どこも紅葉真っ盛り。
黄色が目立つのはブナ(山毛欅)が多くを占めているからです。
泥湯まではもうすぐの、川原毛地獄。
川原毛地獄は、青森の恐山、富山の立山とならぶ日本の三大霊場のひとつです。
ここは塩酸酸性の熱水の噴出により広範囲にわたって凝灰岩が珪化し、灰白色の景色となっているのです。死を思わせる、まさしく地獄のような景色の連続。
そんな景色に中に、若いカップルがポツンと、なにやら楽しそうにしていたっけ。
ここが泥湯です。
旅館は2軒のみですが、筆者がお世話になる小椋旅館は立ち寄り湯だけの営業で、現在、宿泊者は取っていません。
筆者はなじみの常連ということで、特別に頼み込んで泊めてもらっているのです。
もう1軒は有名な奥山旅館ですが、どうしたろう、臨時休業のよう。
のちに外作業の従業員に聞けば、今はとにかく人手不足で1週間を回せないのだそうで、こうして週に2日程休みにしてようやくしのいでいるのだとか。
(もう30年も前にこの奥山旅館に家族で泊まったことがあったけど、その時の宿泊料金は8千円程度であったはず。今は何と1泊で4万とか5万とか。いったいどうなってんの?)
2年前に登った高松岳(1,348メートル)にはもう雪が降ったようでした。
ここは米沢に比して緯度が高い(北緯37°58′/39°01′)とはいえ、たかだか1,300メートルの山に、もう雪です。
今年の冬の訪れは早いのかもしれない。
泥湯晩秋。
まったく人気のない温泉場。
泥湯は、唯一あった蕎麦カフェは閉じ(奥山旅館の出店)、店はなし、温泉以外何もなし。つげ義春もクラクラするようなわびしさです(笑い)。
いいなあ、この風情(笑い)。

宿泊(自炊)棟の入り口。
何とも言えず落ち着くたたずまい。
さっそく、湯につかりました。
熱くもなくぬるくもなく、ちょうどよい湯加減です。
源泉は65℃、泉質は単純酸性泉とのことです。
3泊の滞在中に12、13回は入ったろうか(笑い)。
誰もいないことをいいことに、ここでバタフライ、ヨコ泳ぎ(古泳法)(笑い)。
4部屋あるうち、どこでもどうぞということで。
暖房はないので、カーペットの敷いてある6畳間をチョイス。
夕食はメスティン(洋式飯盒)にて、鶏肉(缶詰)にナメコとエノキ(瓶詰)を加えて炊き込みご飯をつくりました。
米は事前に1合分を用意してきました。
メスティンは必要に応じて日常づかいだけど、今回もとてもスムーズな炊き具合。そしてとてもうまかったです。
夕食の残りは翌日の昼用にと取っておきました。
暖のない部屋、バーナーの火も熱源として貴重なのです。
ここでついでに滞在中の食事の一部を紹介すれば…、
翌日の夜には袋ラーメン、コンビニの生野菜を入れて。
「明星チャルメラ」は筆者が幼少の頃からなじんだ味で、なつかしくて涙が出てきます(笑い)。
おやおやチャルメラを吹く夜鳴きそば屋のおじさん、いつのまにか膝のつぎあてがなくなったのですね。
現代は、貧乏くささが問題なのですかね。筆者はこういう風潮に断固アンチです!(笑い)
ボロをまとった哲人や賢者は少なからずいるのですよ。それを見抜くには眼の訓練が必要ですがね(笑い)。
ある朝はシリアルと、生野菜に1個売りだったリンゴ(王林)を粗く刻んで混ぜてサラダに。なかなかのものでした。
ある朝は、バターロールに箸を突きさして、バーナーで焼いて。これはグッドアイデア!(笑い)
山小屋(避難小屋)暮らしを何度も経験していると、こんなこともすぐに思いつくわけでして(笑い)。
これに、ボイルしたウインナーソーセージにコーンスープ、これだけで十分な食事です。
たっぷりある時間に、新聞を舐めるように読んで。
せめてラジオぐらいはと思って持ち込んだものの、電波はきわめて弱くAMは入らず。ならばせめてFMの電波を少しでも拾おうとメスティンの縁にアンテナを掛けて(笑い)。
FMはアンテナを金属にふれさせると、その金属もまたアンテナの役目をしてくれて感度が増すのですよ。 
ラジオとともに持ち込んでいたものは、『中村哲 思索と行動』(ペシャワール会2023.6)という本です。
普通出かける時はこういうシリアスな本は携行しないのだけれど、今回は特別、今読み進めている最中なので。
中村氏の実直で感傷に流されない姿勢は静かな感動をかもして心地よいのです。
次々と立ちはだかる困難の前になぜに彼は退かないのか、不動なのか。
「われわれの行動は氷河の流れのごとく」(悠久の時間の流れにあってわずかしか動かない=けれどもわずかでも確かに動く)と語る彼の信念の強さとうつくしさを思うのです。
たっぷりの時間に、ずいぶんと読み進みました。
*
29日、泥湯を一旦下って小安(おやす)温泉郷へ、いざ栗駒へ。
泥湯から11キロの小安峡、大噴湯。
大噴湯は、V字に深く切れこんだ皆瀬川から噴き上げる熱水と蒸気です。
大噴湯を谷底の現場から。
先ほど見下ろしていた景色はこの頭上の橋から。
朝から大勢のひとが繰りだしていました。
今回は結果的に泥湯に3泊となったけれども、当初の計画では泥湯は1泊だけ、あとはうつくしい栗駒山を湖面に映す須川湖キャンプ場あるいは高原温泉近くの須川野営場にテント泊と目論んでいたのです。
それは当然にして栗駒山登山あってのこと、紅葉のピークが過ぎているのは承知だけど、飴色の栗駒もよかろうと。
ところが国道398号の小安、奥小安大湯を抜けて、いざ栗駒へと向かえば「通行止め」の制止看板です。
で、仕方なく町まで引き返して増田(横手市)のある店で女将と話していると、「同じことを言っている人がいたよ。小安からだめなら東成瀬(国道342号)から入る手もあるね」という情報です。
ではそれは明日にでも。
翌朝、30日の外気温はマイナス2℃。クルマのガラスがガチガチに凍っていました(-_-;)。
その上で案内の通り、東成瀬の国道342号から栗駒をめざしました。
しかし早々にも「積雪のため、12月28日より通行止め」という電光表示を目にして、これであきらめがついたのです。
結局、登山も、キャンプもできませんでした。
せっかくの遠出、とても残念でした。
*
東成瀬からの道をあきらめて戻った増田で、まんが美術館に行きました。「釣りキチ三平」で有名な矢口高雄(1939-2020)はこの増田の出身、それにちなんだ施設です。
入館は無料(企画展は有料)、しかも膨大な蔵書が読み放題、巨大なマンガ喫茶の趣きなのです。
マンガファンなら垂涎の場所です。
で筆者は、なつかしい永島慎二の名作『若者たち』(双葉社1973)を手に取って読みふけりました。
『若者たち』は筆者の学生時代の愛読書でした。
描かれるのは60年代後半の悩み多き青年の群像…、切なくもおおらか、貧しくも夢あふれ…、そんな青年たちの姿は当時のほろ苦い日々の自分を映していたことも確かで(笑い)。
昼となって腹が減って、近くの中華料理の店・謝謝(シェーシェー)にて、話題の「横手焼そば」を注文。
とてもおいしかったです。
これで500円ですからね、財布にもやさしかったし。
そうしてまた戻って、読みふけって数時間、読了しました(笑い)。
で、次の機会には、ちばてつやと決めています。
ちばが少年漫画誌ではなくまだ少女誌に描いていたころのものに傑作が多いのです。
「ユキの太陽」63年、「島っ子」64年、「みそっかす」66年、「風のように」69年、「螢三七子」72年…、名作ぞろい。
「ユキの太陽」はかの宮崎駿がアニメ化をもくろんだものの、(著作権の問題だったか、アイヌを題材とするゆえに微妙な判断が強いられたか)実現に至らなかった過去もあったはず。
筆者はちばのこの時代のものをだいぶ所有しているけれども、手に入らなかったものもそろっていたのです。
老若男女、遠くからのお客さんもおいでで、思い思いに読みふける姿の数々。
*
泥湯晩秋。
圧倒的な紅葉に包まれる泥湯。
筆者の愛車だけがポツンと。
 女将も年を重ねました。
女将も年を重ねました。
あと何度、お世話になれるだろう。
それではまたの機会に。どうぞ、お達者で。
*
31日、旅の最後は海がいいなあと、庄内は酒田に出ようとしました。
秋田・湯沢を南下して山形県の金山町に出て、そこから国道344号で向かうも通行止め(-_-;)、
引き返して高速(新庄酒田道路)の表示が出たので、それに乗っかれば反対方向だし(何やってんだか!)、
高速に乗り直して進み、高速道の未整備により一般道(国道47号)に出れば、道路工事中にて片側交互通行の大渋滞…。
まったくついていないと言ったら(-_-;)。
酒田で立ち寄りたかったのは土門拳記念館。ここは何度来てもいいです。
そして運よくも、この日から第44回土門拳賞受賞記念作品展・小柴一良『水俣物語MINAMATA STORY 1971-2024』がはじまっていたのでした。ラッキーでした。
ご承知のように、水俣病は化学工場から海や河川に排出されたメチル水銀化合物を魚介類が直接吸収し、あるいは食物連鎖を通じて体内に高濃度に蓄積、これを日常的にたくさん食べた住民の間に発生した中毒性の神経疾患です。
高度経済成長期の負の側面が現代にも延々とつづいている現実です。
以下の写真は、撮影フリー。
作者が水俣病患者に出会って寄りそい、拒まれ、逡巡し、投げ出し、揺れ動きつつ収めた被写体の数々…、水俣を映す風物…、モノトーンの光と影が被写体のリアルと作者の心象を映しこんでいて圧倒されました。
胎児性患者の話を聴く少女たち、2007年。
写真の力。
土門拳記念館にはイサム・ノグチが中庭に彫刻とベンチを寄贈、勅使河原宏の庭園デザインも見事というほかなく。
そうして満足の時間を過ごしたわけですが、もうヘトヘトに疲れてしまい(「水俣物語」の写真に向き合うにはエネルギーを要した)、このまま家に戻るのは体力的につらく、もう1泊を追加。
最後は、新潟は山北(さんぽく。村上市)の笹川流れの海辺で。
夕食を済ませ、いつものようにワインでほろ酔い気分になって早々にシュラフにくるまって休んだのです。
が、しだいに低気圧が急速に台風並みに発達、雨風強くなりどんどんと天候は悪化、しまいに暴風雨となってそれが一晩中がつづいたのでした。
荒れ狂う海…、参りました。
眠るなんてとんでもないこと、暴風で車自体がグラグラと揺れるし、自分が重しになっていなければすぐにもテントはバラバラになって吹き飛ばされそう、もうまったく生きた心地がしない一夜でした(-_-;)。
夜明けの荒れた海。
這(ほ)う這うの体(てい)で、逃げるように家路を急いだのです(笑い)。
*
何とも波乱万丈の4泊5日の旅…、でもちっともコリゴリではないのです、楽しかったです(笑い)。
そうして現実に戻りました。戻って翌日には大量の広葉樹をもらい受けて、軽トラで何往復もして運ぶ作業をしはじめました。
来春、雪が消えてからの薪割りの材料たちです。

おまけは、11月5日のスーパーフルムーン。
よい月夜でした。

それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。