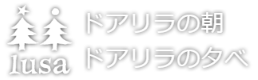本日は(2025年)10月6日、中学の(古希の前祝いの)同窓会からもどった朝です。
なつかしい顔と思い出につられてずいぶんの深酒をしました(笑い)。
筆者が10代20代の頃、70歳というのはヨボヨボ・ヨタヨタ、顔シワくちゃの、もうすぐあの世というイメージでしたが(ちょっと大げさだけど)、自分がその年を迎えようとしている今、そんなのはとんでもないことです(笑い)。
さて、そんな日の2日前に、奥羽脊梁山脈の一画、吾妻連峰の東端の浄土平から一切経山(いっさいきょうざん)に登ってきました。
今回のsignalはその山行記録、題して「一切経は秋」です。
※筆者がここで使う「一切経」は一切経山を中心として、酸ヶ平湿原、鎌沼、鎌沼に隣接する前大巓や蓬莱山、姥ケ原を含む広いエリアをさしています。
*
筆者の山行の大方はソロです。
地元の山の会にでも入ればみなで楽しい道々でしょうが、普段の工房仕事の合間にフラッと出かけるスタイルはやはり無理がなくていいのです。
でも、時に相棒といっしょに、時に友人を交えて、または友人と、そしてまれに大きなパーティーに混ぜてもらっての山行もあります。
大きなパーティー…、この7月の旭川の「ひぐま大学」(NGO大雪と石狩の自然を守る会の一部署)の山行ツアーで登った富良野岳(1,912メートル。十勝岳連峰の南西部)はその例です(→signal「花の山旅、富良野岳」)。
これは忘れえぬ山旅、実に感動的でした。
この夏の北海道旅行に際して、その富良野岳ツアーに誘ってくれたのは旭川在住の(ひぐま大学のスタッフ、小中学の同級生の)ノリコさん。
で、彼女がこの5日の同窓会にはるばる参加すると聴いていたので、ならばと、その機会に一切経にいっしょに登らないかと、今度は筆者が誘ったわけで。
我が家に着いてすぐ、近くの、20分そこそこで登れる鑑山(かがみやま)にノリコさんといっしょに。
鑑山のトップは標高420メートルほど、そこから赤い屋根の我が家(350メートル)が見えます。
歓迎の晩餐は、里心つくようにと、ささやかながら米沢地方の郷土料理で。
あけびの姿焼き(キノコと肉味噌を詰めて焼いたもの)、芋煮、ぜんまいの煮つけ、そして冷や汁…。
翌朝6時、いざ、愛車ジムニーにて登山基地の浄土平へ。
7時半には着いたのですが、収容400台の駐車スペースの半分ほどはすでに埋まっていたような感覚です。早朝にしてこれ、それほどに紅葉の時期の浄土平は人気が高いのです。
この時間、客の3分の1ほどは一切経に向かうでしょうか。あとは手軽な吾妻小富士や周辺散策でしょうか。
ノリコさんと、相棒のヨーコさんと。
噴煙立ち昇る一切経山を背景として。
もうすぐ古希、合わせて138歳のツーショット(笑い)。
歩きはじめて約40分ほどで酸ヶ平(すがだいら)避難小屋です。
この小屋はいつもは休憩場所として利用しているのですが、あいにく修理の工事が入っていて使えませんでした。
この小屋には立派で清潔なトイレが併設されています。
小屋を過ぎればちょっとした急坂、それを登りつめると巨大なフジツボが顔を出します(笑い)。吾妻小富士です。
吾妻小富士は絵に描いたような爆裂火口です。
吾妻小富士が見えれば登山道はなだらかとなって、ほどなく一切経山(1,949メートル)のピークです。
小屋からピークまでは40分ほどの登山、したがって登山基地の浄土平から一切経山には約80分で登れるということです。
浄土平の標高が1,600メートルでピークまでの差は350メートル、80分で標高差350メートルとは手軽な山というものです。
ピーク!
山の天気は変わりやすく、山頂はビュンビュンと冷たい風が吹いていました。
そして、山頂より見下ろす五色沼、別名・魔女の瞳。
ノリコさんは北海道は旭川からわざわざ、でもきっと、来た甲斐ありの、魔女の瞳だと思います。
みんなみな、このブルーアイ見たさにヒーヒー言いつつ登ってくるのです。
いやあ、魔女の瞳はいつ見てもうつくしい。山頂で見る湖のすばらしさ。
何だろう、この安堵感、解放感。
何だろう、この清浄感。

下は、今年5月初旬の魔女の瞳。
4年前の、9月半ばの魔女の瞳。
まだ雪残る春の魔女の瞳もいいし、夏のそれも秋口もいいけど、紅葉のころの魔女の瞳はまた格別です。
時間を忘れてずーっと、ただぼーっとたたずんでいるひとも多く。
五色沼の湖岸はナナカマド(七竈)やミネカエデ(峰楓)、それからダケカンバ(岳樺)が彩っているよう。
濃いみどりのオオシラビソ(大白檜曽)との対照のうつくしさです。
下山のショット。
背景は高層湿原の酸ヶ平湿原です。
酸ヶ平湿原をおおう薄い紫は、(和製ブルーベリーの代表格の)クロマメノキの紅葉です。
この微妙な紫を伝統色より拾えば、菖蒲(あやめ)色なのだそうで。
クロマメノキ(黒豆木/ツツジ科スノキ属)。
この液果はとてもおいしいです。  一切経の山肌。
一切経の山肌。
池塘のまわりの葡萄(えび)色は、ヌマガヤ(沼茅)の枯草色と中に入り込むクロマメノキの菖蒲色との混色です。 
一切経の紅葉の特徴のひとつは、童話の国のような配色にあります。ただ単に赤い、黄色いではないのです。
山肌を矮小化したチシマザサ(千島笹=ネマガリダケ/根曲竹)の白緑(びゃくろく)色を背景として、くっきりとした濃いみどりのオオシラビソ、赤いナナカマドやミネザクラ、黄色なミネカエデ…、ひとつひとつが浮かび上がるように配置されるのです。
こんな紅葉の景色はまたとないのでは。
紅葉もこうなると、神がこしらえたのではとしか言いようがなくなるのです。
そう、神の植林場、神の庭。
鎌沼湖畔の彩り、クロマメノキにチシマザサ。
ガンコウラン(岩高蘭/ツツジ科ガンコウラン属)の茂みにクロマメノキが入り混じったうつくしさ。
どちらもたくさんの液果をつけています。
ハイネズ(這鼠/ヒノキ科ビャクシン属)のみどりとクロマメノキの菖蒲色との対照のうつくしさ。
クロマメノキに入り混じるチシマザサの淡いみどり。
立ち枯れているのは、夏には白い花をつけていたコバイケイソウ(小梅蕙草)です。
きっと勢力争いをしているのだろう、クロマメノキとチシマザサがせめぎあって。
このマーブルのうつくしさ。
湖畔の、ムラサキミズゴケ(紫水苔/ミズゴケ科ミズゴケ属)とチングルマ(稚児車/バラ科ダイコンソウ属)とクロマメノキの暖色のハーモニー。
真っ赤に紅葉したチングルマ。この赤がいいなあ。
中央のみどりはコケモモ(苔桃)のようです。
チングルマは白い花よし、花後の、風になびく老人のヒゲのような実よし(名前からすれば、本当は稚児のうぶ毛)、そしてこの真っ赤な紅葉よし。
ひと粒で2度おいしいアーモンドグリコも真っ青、こちらチングルマは3度おいしいのです(笑い)。
シラタマノキ(白玉木/ツツジ科シラタマノキ属)とガンコウラン。
シラタマノキの実はスースーしてサロメトール(サリチル酸メチルエステル)の味です。
湖畔にたたずむエゾオヤマリンドウ(蝦夷御山竜胆/リンドウ科リンドウ属)。
あとはもう、色あせ枯れゆくばかりの、最後のうつくしさ。
これって、あこがれの、人生の最期の姿を映していると思いません? 華あって朽ちてゆく、朽ちてゆくときにも華がある、という。
ネバリノギラン(粘芒蘭/キンコウカ科ソクシンラン属)のうつくしい紅葉。この色をあえて言えば、柿色、ゴールデンオレンジです。
ごいっしょしたノリコさんは植物への知的好奇心旺盛。
このネバリノギランがめずらしいらしく、何度も反唱/復唱しては覚え込もうとしています。そして忘れぬうちにとノートにメモしていきます。
 赤いナナカマド、黄色なミネカエデ。
赤いナナカマド、黄色なミネカエデ。
オオシラビソの濃いみどりやチシマザサの淡いみどりに引き立てられながら。
湖畔のナナカマド(七竈/バラ科ナナカマド属)。
一切経の紅葉のうつくしさを演出するのはこのナナカマドの赤、他ではなかなかお目にかかれないあざやかな赤です。
一切経を背景にして、ハイマツ(這松/マツ科マツ属) に引き立てられるナナカマド。
ミネザクラ(峰桜/バラ科サクラ属)の真っ赤な紅葉。
手前は常緑のハクサンシャクナゲ(白山石楠花/ツツジ科ツツジ属)です。
チシマザサの湖に、ぽっかりとした浮島のような赤いミネザクラ。
オオバスノキ(大葉酢木/ツツジ科スノキ属)の黒熟した実。
これも和製ブルーベリーの一種で、おいしい果実です。
紅葉したオオバスノキ。
紅葉途中のハナヒリノキ(嚏木/ツツジ科イワナンテン属)。
ハナヒリノキはこれから干しブドウのような灰みの濃い紫に染まっていきます。
ノリコさんが、この実は何だろうと問いかけました。
筆者もこれまで何度か気になっていて調べて分かっていたことには、これはマイヅルソウ(舞鶴草/キジカクシ科マイヅルソウ属)。
この熟した実は甘くておいしいのだそう。自分はまだ口にしたことはないので、今後が楽しみです。
マイヅルソウは高山植物と目されがちですが、市中の郊外、標高が250メートルの低地でも群落を発見したことがあったものです。
垂直分布の広い植物、生き延びる力のすごさです。

ガンコウランとコケモモ(苔桃)に囲まれた中の、孤高のゴゼンタチバナ(御前橘/ミズキ科ミズキ属)。
白い花も赤い実もきれいだけど、紅葉の赤も格別です。
紅葉したゴゼンタチバナの群落。
マルバシモツケ(丸葉下野/バラ科シモツケ属)の紅葉。
そして、一切経の紅葉のトリはオオカメノキ(大亀木/ガマズミ科ガマズミ属)です。
黄色やオレンジ、はたまた深紅にも染まるオオカメノキは山を歩く者を楽しませていきます。
そうして浄土平に戻れば、これから紫に変わろうとするムラサキミズゴケのあざやかなみどりです。
みどりの中に茎立ちするたくさんの枯れ姿はいったい何だろう。
そして浄土平では高地のために矮小化したススキ(芒/イネ科ススキ属)が風になびいていました。
深まりゆく秋に、ススキも自分もと紅藤(べにふじ)色に身を染めて。
*
実はこの朝、浄土平に着く1キロ手前あたりで、ツキノワグマ(月輪熊)に会いました。
遠くがよく見える相棒が(クマという単語が出て来ずに)「黒いもの、黒いもの!」と興奮気味に言うのです(笑い)。見れば、磐梯吾妻スカイラインの道路わき約25メートルのところにその黒いもの、ツキノワグマがいたのです。
クルマがひっきりなしに通り過ぎるのもお構いなしに何やらむさぼっています。
そして、あとで画像を拡大して植物を見れば、それはガンコウランと分かりました。
クマはたわわについたガンコウランの液果を無心に食んでいたのです。
相棒はこれまでもう何度もツキノワグマを見てきているけれども、今年目にしたのははじめてのことでとてもうれしそう。
筆者もこれまでさまざまな場所で見てきているけれども、こうして撮影に成功したのははじめてのこと、やはりうれしかったです。
筆者たちは基本、クマが生息できる自然環境の中で暮らせる幸せを感じているということ、クマは森のカミとしてリスペクトさえしているということがあります。
巷ではクマが市中の中心部に出没したとかで大騒ぎ、でもツキノワグマは東アジアにあっては絶滅の危機に瀕している希少動物であるのも確かなのです。
クマ君よ、どうぞ君はこういう高山の主であり続けてください。
下界はヒト属の、快楽ばかりをむさぼっている決してうつくしくはない場所、君の活動する場所ではありませんよ。
下界は怖いところです。捕まれば銃で撃たれたり、槍で一突きですよ。そして決して、弔ったりしないし。
やはり、山がいいですよ。山は平和です。
*
どこまでも青い魔女の瞳、彩りあざやかな一切経の、神の庭…、かけがえのない友と相棒との心地よい時間が過ぎました。
相棒が言うには、「やはり一切経の紅葉は最高。紅葉のピークはあと一週間先では」。その時にはさらなる極上の風景が広がることでしょう。
紅葉が過ぎればほどなく枯れ色がひろがって、やがて色という色があせて無彩色になっていきます。
そうして一切経に雪が舞って、冬がきます。
季節の正しいめぐりです。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。