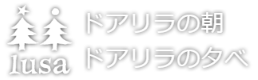本日は(2025年)7月22日、いやあ連日ものすごい暑さですね。
何とかして乗り切らないとと思うけど…。
とにかく今は草刈りをするにしても町内関係の業務にしても身体を動かすのは朝の涼しいうちと決めています。
麦わら帽子が友だちです。
さてこの夏、7月半ばに、(2016年以来)ひさしぶりに北海道に渡って1週間ほど滞在したのですが、signalではその思い出の書きとめ、道中こころにひびいたことのいくつかをピックアップして記してみたいと思います。
今回はその1、道央は美唄(びばい)にある彫刻空間、アルテピアッツァ美唄に遊んだこと、題して「アルテを渡る風」です。
アルテピアッツァ美唄の「アルテピアッツァArte Piazza」はイタリア語で芸術広場を意味しているとのこと。
以下使用する「アルテ」は「アルテピアッツァ美唄」を(筆者が)略したものです。
写真はほぼ筆者(および同行の相棒)の撮影で、使用した写真には前回16年時のものも混じっています。クレジットのあるものはネットからのありがたい借用です。
*
そこはかつての炭住街の一画、閉校してしまった小学校跡地。
そして今そこはなつかしい風景と一部の建物を残しつつ彫刻作品を点々と配するアートの広場に生まれ変わったのでした。
下は1962年撮影という、かつての炭住街に面した美唄市立栄小学校の全景です。国土地理院によるものです。


アルテは旧栄小学校の校庭と校舎の一部を残して整備し、美唄出身で今はイタリアにアトリエを構える安田侃(かん)(1945~)の彫刻作品40点あまりをぜいたくに配した彫刻展示スペースです。
「彫刻展示スペース」や名の意味の「芸術広場」という言い方は的を射ているかどうか。ここはそれ以上に適切な表し方があるような。
あえて言えばここは、過去の歴史を孕み、今を見つめ、未来の希望を育むような、自然とひととアートが融合した空間、とでもすればよいのかどうか。
敷地面積はおよそ7万平方メートルとのこと、坪換算で約2万1千坪と広大、これは国立競技場(建築面積)より少し広く、東京ドーム2個分より少し狭いイメージです。
筆者にとってアルテは前回の渡道の際に最も印象に残った場所のひとつ、その時の感動が忘れられずにもう一度訪れたというわけです。
当時受けたここちよさとは何だったのか、その思いはなぜに時間に耐えながら続いているのか、それを確かめてみたかったのです。
校庭の上方から忽然と泉が湧いて、川となって流れ、水の広場をつくり、やがて池につながっていきます。
前回はここで大勢の幼稚園児たちが戯れていたっけ。
ここは1994年に安田がイタリアから同行した石工のジョルジョ=アンジェリらとともに製作、設置したのだとか。
川底も池の底もすべてが白い大理石、苔が生えるわけでなく水が淀んでにごるわけでなく。
相当に手を加えて作品を維持していることが分かります。
配された安田の作品はどれも主張をしていないのです。
作品が主張しないのではなく周りの景色が主張を拒んでいる、または主張を消しているのかもしれない。
だから、ひとは立ち止まって作品と向き合う必要はないし、作品との会話さえも不要で、ただ通り過ぎるだけでよい。
でも、それでいてここちよい何かがこころに積もっていくのです。不思議です。
安田という作家は、その、無意識に紡がれる精神的な美(価値)を意識しながら製作しているのかもしれません。
運営する団体(認定NPO法人アルテピアッツァびばい)の職員に伺ったところによれば、すべての作品は安田が現場で立ち合い、場所や位置、設置の仕方や向きまでも指示を与えていたとのこと。
安田にしたら、こんな思いのままの空間を得て、己の魂を吹き込んだ作品の生かされ方を自由に決定できるなんて生涯最高の仕事であったことでしょう。
園地を整備するひともアートのひとつのピースのようで。
ていねいに刈り取られた天然の芝草とシロツメクサ(白詰草)の足元はやわらか。
 作品には一応題があるようですが、それが銘板などに記されているでなし。
作品には一応題があるようですが、それが銘板などに記されているでなし。
感じ方、受け止め方はそれぞれの自由、この自由さが実にここちよいのです。
渡る風は気持ちよく、ひとは、無心に、気の向くままに、思い思いに歩いてゆきます。

この丘を登り切るとてっぺんは角錐状に掘られていて、そこに真白い物体が鎮座しています。
雨が降ってもたまったりせずにこのままの形状なんだろうけど、水を抜く装置はどうなっているんだろう。

広場の周囲には人為的なものはほとんどなく、もとからそこに生えていた木や草やが生い茂り。
クマザサ(隈笹)を刈った場所に立つ彫刻。
広場に隣接するトドマツ(椴松)と思しき林には散歩道がめぐらされ…。
時に、こんな注意書きも。
感心している場合ではないけど、この看板も実にうつくしいデザイン。
注意書きひとつも決して風景を汚してはいないのです。
アルテに渡る風がここちよいのです。
林の片隅に卵。
トドマツたちが円い石を引き立て、円石がトドマツを生き生きとさせています。
アルテに渡る風がここちよいのです。
雨に濡れたらさらにうつくしさを増しそうな。
オニグルミ(鬼胡桃)の大樹。
大きなフキ(アキタブキ/秋田蕗)と、ボクはコロボックル(笑い)。
*
そらのあお
くものしろ
みずのあお
いしのしろ
たいようのきんいろ
くさのみどり
きぎのあか
ひとのいろいろ
うつくしいうたの
はるなつあきふゆ
ビバ美唄
アルテピアッツァ
谷川俊太郎
一九九九年九月十五日
「ビバ美唄」ねえ(笑い)。
昨年(2024年)亡くなった谷川俊太郎もここを歩いて、求められるままに?即興でことばを紡いだよう。
足どり軽く、こころ軽くして快活となり、ことばは泉のように湧いてきたのでしょうか。
ふと思って、後日アルテに電話して伺いました。
それによると谷川はイベント(「谷川俊太郎&Divaー詩の朗読と音楽の夕べ」1999.9.15)があって来場していますが、その他にも複数回訪れているはずとのこと。
紡がれたことばは積もった思いの表れでもあったのかも。
アルテに渡る風がここちよいのです。
筆者はこれまで彫刻公園ともいうべきもの、たとえばそれは箱根の彫刻の森美術館であったり、札幌芸術の森美術館であったり、それから長野県上田の美ヶ原高原美術館にも行ったことがあるけど、ここはそれらとは趣きが違います。少し似たような雰囲気で言えば、イサム・ノグチが監修した札幌はモエレ沼公園があげられましょうか。
端的に言ってアルテは、歩いても疲れを覚えないのです。アルテを歩くとどこからかエネルギーが降ってくるよう、湧いてくるようなのです。
何だろう、この力。
*
校舎をまるごと使って。
2階の窓から見える景色。
体育館もギャラリー。
作品が体育館を再生させているようで。
天井のアーチ構造もアーティスティック。
そして、林に隣接してカフェ(カフェアルテ)が建てられています。

歩いて、歩いて、そして休憩です。

ここでいただくコーヒーのおいしさは格別です。
*
エネルギーの転換という時代の波に呑まれ、美唄の炭鉱は1973年までにすべて閉山し、
ピーク時には児童が1,250名いた小学校は1981年に閉校となり(最終年の児童数は62名だったという)、
炭鉱で栄え衰退していった土地の記憶とひとの思いを、
自然とアートが融和した空間が受け止めて、
アルテは今、静かに佇んでいます。
芽吹きの頃も、春も、初夏も盛夏も、そして秋の入り口もいいだろうな。
紅葉の頃も晩秋もきっと素敵だろう。そして当然にして凍てつく冬はさらによいかも。
アルテピアッツァ美唄は変わらずに静かに佇んで、希望を紡ぐひとをいつでも待っているはずです。
これがこれからどんなに多くのひとびとの幸いに寄与することか。
ここはまるで、宮澤賢治の「虔十公園林」のよう、いやいや公園林をしのぐ存在かもしれず。
アルテピアッツァ美唄は安田ひとりではない美唄という町が再生の祈りを込めてつくり上げた世界に誇り得る傑作ですから。
*
アルテピアッツァ美唄の入場料は無料。ただし任意による寄付のお願いがあります。
休館は火曜日、祝日の翌日となっています。
問い合わせは、認定NPO法人アルテピアッツァびばい、電話0126-63-3137。
それじゃあ、また。
ビイバイ!(笑い)
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。