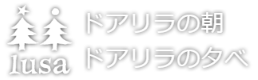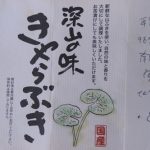本日は(2025年)6月17日、いやあ暑いですね。
まだ6月だというのにこの暑さ、梅雨をすっ飛ばして一気に7月下旬の真夏に連れていかれたよう。
ずいぶん地球が痛めつけられているんだろうな。
5月半ばからここ1か月の筆者といったらまったく忙しなく、自分の時間を確保するのがやっとやっとという感じでした。
そんな1か月の記憶からとどめておきたい画像と出来事をかいつまむ中で、今回のsignalは題して「蕗沼」です。
蕗沼という沼があるのではなく、自分は今ぞっこん、フキ(蕗)の沼にはまってしまっているということです(笑い)。
そんなフキをメインに、春から夏にかけての、山の暮らし、森の暮らしのあれこれ。
*
ここルーザの森は野鳥の森、野鳥の楽園といってもいいと思います。その豊かさは日本のどの森にもひけを取らないのではと思うほどです。
以下は、前々回のsignal「コゴミを採りにゆく」で紹介した鳥たちとなるべくダブらないようにして。
甲高い声のホトトギス(不如帰)が啼いたのは5月15日のこと、ホトトギスはまったくまったく初夏の使者です。
ホトトギスが啼くごとにあたりのみどりが冴えざえとしてくるようです。

5月5日のこと、薪割りなどの一日の仕事を終えた夕べ、隣接の林のわきを通る小さな渓流を見下ろす段丘に腰を下ろすと、何とオオルリ(大瑠璃)がやってきました。そして、うつくしい声で啼きはじめたのです。
その梢までの距離は約5メートル、警戒心はまるでゼロです。
筆者はもううれしくなって、そのうつくしい歌にじっと聴きいっておりました。
たぶん一生忘れない、夢のような時間でした。
オオルリは本当にきれいだ。

キビタキ(黄鶲)。
ワラビ採りが文字通り朝飯前の日課となりはじめた頃、野原にはキビタキの、鉦(かね)をたたくがごとくの金属的な声が響きはじめました。この歌は実に楽しいです。
キビタキは最近、我がヒュッテにもよく顔を見せています。
何とうつくしいオレンジ!

一筆啓上仕り候、イッピツケイジョウツカマツリソウロウ…、
そういう聞きなしのあるホオジロ(頬白)。
ごていねいにも1筆どころか10筆も20筆も書いていきますがね(笑い)。
今回の野鳥の写真中、これだけがオリジナルです。
サンコウチョウ(三光鳥)が来ていたのは6月のはじめ、鳴き声の末尾のホイホイホイが何ともほほえましいです。
それにしても朝起きたばかりの、寝ぐせと無理して見開いた目は愛嬌(笑い)。

野原でフキを採った帰りの6月13日、小さな沼近くでスイレン属のヒツジグサ(未草)を見ていた時のこと、上空を大きなアオサギ(青鷺)が羽ばたいていきました。ガオー、ガオーと犬の吠えるような声で啼きながら。すごい迫力!
アオサギは湖沼や田んぼなどで何度も見ているけれども、声を聴いたのははじめてでした。

森の王者フクロウ(梟)。
オホ、オッホオッホ、オホ、オッホオッホ…、夜にこの声を聴いたのは5月15日のこと。
フクロウが棲むには森の生態系が豊かでなければなりません。
今年も来てくれていることがとてもうれしいです。

夜半から朝方にかけて、ヒー、ヒューと悲し気な笛を吹くのはトラツグミ(虎鶫)。
その声は幽霊を誘うようで(または、幽霊のようで)気持ちが悪いというひともいますが、これはこれでうつくしい声です。
時に、(男女のペアなのか)啼き交わしているのが聴こえます。

ご存じ、宮澤賢治の「よだかの星」の主人公、ヨタカ(夜鷹)。
ヨタカは、同じ音域(音程)で節をつけることなく、キョキョキョキョキョキョキョと啼きます。
不思議なのは、この特徴的な声が「よだかの星」にはひとつも登場しないのです。唯一登場する鳴声の“キシキシキシキシキシッ”ではまるでちがいます。味噌をつけたような顔、口が大きく裂けているなどその形態は確かにヨタカなのに、です。
ある鳥の専門家は、賢治はヨタカとオオジシギ(大地鴫)を混同しながら物語を書いてしまったのではと指摘してもいます。どうなんでしょう。

ヒュルルルルー、ヒュルルルルー…、と溪にうつくしい声を響かせるのはアカショウビン(赤翡翠)。
今年やってきたのは6月5日のことで、それはもうすぐ梅雨ですよという前触れのようでした。

筆者に野鳥の声が入ってくるようになったのはここ数年のことなのだけれど、それは人工的な音を意図してシャットアウトしているからかもしれません。
人工的な音よりも、自然の中にある音の方が心地よいのです。
最近はテレビからは遠く、ラジオさえ聞かなくなっています。主にトキオ(TOKYO)から発せられる音(情報)の不健康さがイヤになってきているというのはあるわけで。
*
森の暮らしの、我らの春のクライマックスは何といっても干しゼンマイつくりです。
今年は3回ほどしか採りには行けなかったけど、それでもたくさんの収穫がありました。
家に戻れば、1本1本のゼンマイを確かめて茎の堅い部分を折り取り(これがやっかいな、ムサい…めんどうくさくて根気がいる…仕事なのです)、それから茹でて、干して、揉んで、揉んで、揉んで、干しあげて…、
そうして今年も干しゼンマイが出来上がりました。
冬以降の食材としてこれは貴重なもの、森暮らしにあって、ゼンマイのない暮らしは考えられません。
干しゼンマイつくりはとても手がかかるものですが、それは同時に豊穣な時間を与えてもらえるということでもあります。
まるで笛を吹くようなうつくしい声で啼くカジカガエル(河鹿蛙)の棲む渓流の近くで、ポッキン、ポッキン。
もう20年以上も使って底を含めて数か所の穴があいてしまったので、煮炊き用にとあたらしい(新潟のホンマ社製鉄板)薪ストーブを買いました。その使い初めです。
*
何とかふたつ、山に登ってきました。
ひとつは5月24日、吾妻連峰東端の一切経山(1,949メートル)。
春先の一切経登山はもはや我が家の恒例行事、今年も冬の眠りから目覚めた魔女の瞳(五色沼)に会うことができました。
下はまだ十分に雪が残っていた麓の鎌沼にて。
ひとつは6月7日、朝日連峰の一画を占める、(置賜)葉山(1,237メートル)。
こちらは登りはじめから下山までの時間、約6時間の長い行程でした。
高校時代の学校登山以来51年ぶりの葉山、とてもなつかしかったです。
ブナ(山毛欅)の芽吹き。
清新なブナ林。
清浄な空気はここからつくられているよう。
頂近くの山小屋にて。
昼食にと湯を沸かしてカップ麺を食べたけど、うまかったなあ。
*
そして、フキ(蕗)です。
5月半ば過ぎ、ワラビ採りが佳境を迎える頃にフキの季節がやってきます。
フキは雌雄異株、その蕗の薹。
雄株。花粉をつくって、花が終われば枯れてしまいます。
こちらは雌株。
花粉を受けて、どんどん成長し、タネをつくってタネを飛ばすまで枯れることはありません。
ここ米沢を含む置賜(おいたま、おきたま)地方では、丸々とした蕗の薹から少し育ったものが産直の店で売られたりします。
なぜと思うでしょうが、置賜ではここ10数年で、薹の立った茎の食べ方が浸透してきたからです。この茎を煮つけにするとプーンとした春の匂いが漂っておいしいです。
それがため、我が家でも茎の伸びた蕗の薹を(特に相棒が)せっせと採ります。
背丈がグンと高くなり…、
タネをつくった雌株。
他の草の背丈よりもさらに伸びて、よい風を受けられるようになるとタネを飛ばします。そうしてタネは遠くに飛んでゆきます。
フキは賢いです。
そして地下茎でつながったフキの葉が育ちます。
葉は光合成によって栄養をつくって株を大きくしていきます。
すっくと伸びた葉柄のすこやかさ。
フキ(蕗/キク科フキ属)は日本原産。
分布は日本全土のほか、サハリンや沿海州、朝鮮半島や中国東北部にも自生するとのことです。
欧米ではフキの食材としての偉大さを知らない訳だ。エッヘンだ(笑い)。
米沢のフキの利用はほぼ一択、何と言っても炒め煮です。
筆者も幼い頃から食べているものではあるけれども、どんなに季節が巡ってもどんなに年を重ねても、このフキの炒め煮の魅力は減じることがありません。
フキは栽培したものではなく、野原や山に自生するフキに限ります。自生種に独特のアクの強さが持ち味だからです。
採ってきた蕗の根元を切り落とします。これは皮を剥(む)く時の、むきやすさを考えてのことです。
ものの情報ではフキの下ごしらえとして塩をまぶして板摺りをするってあるけど、こんなめんどうくさいことは筆者は無視です。塩を入れて茹でればそれで済むことです。何か問題ありますかね。
湯を沸かし、沸騰したらフキを投入し、再沸騰してから4分…、これが筆者が行き着いたフキの茹で時間です。
フキの1本1本にはそれぞれ個性と個体差があって一筋縄とはいかず、いろいろと試行錯誤をしてきたのですが、これ以上煮ると煮崩れを起こしがち、これ以下だとフキの身(特に太いものには)に堅さが残ります。
冷水にとって身を引き締めます。
ここで水にひたしておくのはせいぜい10分が限度、それ以上だとせっかくのフキの風味が損なわれてしまいます。筆者は水にひたし過ぎて風味を損ねて失敗してしまったことがあります。
フキの皮むきはムサい仕事ですが、1本1本ていねいに処理していきます。
筆者の場合、フキの皮むきは工房のコンクリート土間で行います。
むいた皮は床に無造作に落とし、あとはまとめて捨てればいいので。
ラジオもつけず、ただ入ってくる山の音、森の音を聴きながらのフキの皮をむく時間はいいものです。
静かなひと時です。
筆者の、フキの炒め煮スペシャルレシピを記すと(笑い)…、
茹でて、皮をむき、5センチほどに切ったフキ500グラムに対して…、
植物油大さじ2で軽く炒めてから、生醤油(白だしを半量)、酒、みりん各大さじ2を加えて煮つめ(味を見て、醤油をひと回しすることも)、鷹の爪を投入、煮汁が飛んだら白ゴマをかけて出来上がり、という何の変哲もないお定まりです。
そうしてできあがったフキの炒め煮。
フキ500グラムを1回の単位として、この季節でもう6回はつくっていますかね(笑い)。
猫に木天蓼(マタタビ)ならぬ、てっちゃんにフキの炒め煮です(笑い)。
筆者の場合、フキの利用はずっとしばらく炒め煮一辺倒だったのですが、去年の6月はじめ(尾瀬の燧ケ岳登山の帰りに)、福島県の辺境・檜枝岐村の土産店で何気にきゃらぶき(伽羅蕗)を買って食したのが運命でした。
きゃらぶきってこういうものだったのだ、こんなうまいきゃらぶきがあったんだ、それは衝撃的なものでした。
それがこのパッケージ。
きゃらぶきはフキの佃煮ですが(きゃら/伽羅は色の名称なのですね、ただし実際の伽羅色はくすんだ肌色という趣きです。今回はじめて知りました)今までに口にしたものはしょっぱ過ぎて甘過ぎて、しかもフキの身が堅いし、どうも口に合わなかったのです。
ですが、舘岩村(現・南会津町舘岩)の平野物産店で製造されているこのきゃらぶきはあきらかに違いました。味つけも堅さやわらかさもちょうどよく決まっていたのです。
それで、どうせフキを採るならばときゃらぶきつくりに挑戦することにしたのです。
最近知り合いからたまたまきゃらぶきをいただいたのですが、聴けばそのレシピは…、
フキ500グラムにつき、皮はむかず、醤油1カップ(200cc)、ザラメ100cc、みりん50ccでじっくり4時間をかけて煮込むということでした。これは植物学者夫人の秘伝とのこと。
ん~ん、でも申し訳ないけど、やはりこちらのイメージではない。

そこでものの情報を調べていろいろと試したのちの、筆者の(今のところの)きゃらぶきベストレシピは(笑い)…、
フキ500グラムにつき…、
筆者は茹でて皮をむき(皮をむく派とむかない派はふた手に分かれていて、どちらかと言えばむかない派の方が多いよう。皮をむのくがめんどうというのがあるかもしれないし、剥くと煮崩れを起こすという懸念もあるようで)…、
5センチほどの長さに切って…、
醤油60cc、砂糖(きび砂糖)120グラム、酒50cc、そこに山椒の実を適量投入して煮詰めて(ほぼ煮詰めてから味を確認、しょっぱさが足りないときは醤油をひと回し、ふた回しして)、汁が飛んだら終了です。
きゃらぶきに山椒の実は必須だと思います。
下は左から、いただきもののきゃらぶき、中央が筆者の1回目、右が2回目。
左から順に。
よく見ると、微妙に色のちがいがありますね。
いずれも食す前に、白ゴマを散らすのがよいみたいです。
来年以降、また挑戦してみます。
そして平野物産店製造のきゃらぶきに少しずつ近づいていきたいと思います。
これで人生の目標がまたひとつ増えました(笑い)。
*
溪は緑を濃くし、ヤマボウシ(山法師)の白い花もそろそろ終わるよう、もはや盛夏の趣きです。
そして笊籬橋のたもとに、ここら山形県南の置賜では希少種と呼ばれるバイカツツジ(梅花躑躅/ツツジ科ツツジ属)の可憐な花が、昨日咲いたのでした。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。