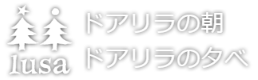本日は(2025年)4月末の30日。
ちょうど50年前のこの日はベトナム戦争の終結した日、アメリカが参戦してはじめて敗けた戦争で、新聞の一面には北ベトナム軍の戦車が首都サイゴン(現ホーチミン)に入場し、国を挙げて歓喜する様子を伝えていたものです。そうして南北のベトナムが統一されたという記念すべき日。
当時筆者は18歳、大学に入学してすぐの、実に刺激的なニュースでした。この戦争で日本は実に恥ずかしい行動を取っていましたしね。
この冬はたいへんな大雪、ここらではピーク時で240センチの積雪を記録したものです。200センチ越えは久しぶりのこと、植物も動物もひとも大いに苦しめられました。
そのひとつ、懇意にしている栗園の枝折れがひどく、このままでは園地の草刈りもできず、ということは収穫もままならないということで、筆者はボランティアのつもりで3日ほど通いました。
ここはもうすぐ御年98歳になる現役の農婦まささんがひとりで守っている園地です。息子さんは勤めの合間を縫って町場から通って手伝いに来ますが、この枝折れは尋常ではなく、チェンソー使いができる筆者が自ら処理を買って出たのです。何せ筆者は、まささんの大ファンでして(笑い)。
太いところは筆者がストーブの薪用に持って帰りますが、細いところはまささんがノコギリで適当な長さに切って、ナタをふるって刻み、風呂焚きの燃料にしていきます。たいしたバアバです、人間国宝に推挙したいくらいです(笑い)。

高い場所の太いところの枝折れも多く、その伐採は危険をともない、いろんなことを想定して慎重に作業を進めました。
玄関口のしつらえにと飾った枝垂桜の枝。枝は近くの施設からいただいたものです。
この花活けは我が家のかつての二槽式洗濯機の脱水槽の再々利用、中に、果実酒の長い瓶を入れています。
傘立ての役目も終えて、第3の人生です(笑い)。 
この27日には海外からのお客様が大勢いらっしゃいました。
まだ残る雪にみんなが大はしゃぎ。 

そんな春のはじまりの中、今回のsignalは「コゴミを採りに行く」。
本格的な山菜の季節が到来し、もう筆者のアドレナリンホルモンはマックスなのです(笑い)。
雪国に暮らすニンゲンにとって、山菜採りというのは春が来た喜びを全身全霊、全感官を研ぎ澄ませて感じ取るもの。たぶんそのワクワク感、ドキドキ感は他所からはとうてい分からないものだと思います。
*
朝は5時に起き出してさっと着替えて10分後には家を出る“実益ウォーキング”をはじめたのは、この23日のことでした。
約50分ほど歩いて、今はタラの芽(タラノキ/楤木/ウコギ科タラノキ属)やコシアブラ(漉油/ウコギ科コシアブラ属)を収穫してきます。よい運動です。


上の山菜バッグは今年新調したもの、秋田は湯沢にあるマルサンカバン店というところの製品です。
いままで20年も使っていた山菜バッグはリサイクルショップで100円で買ったもの(笑い)、ずいぶん世話になったけど、帆布の生地が弱くなり、繕ってもつくろっても裂けてきて用をなさなくなったのです。
で、いざホームセンターやネット通販で探すもいずれもちゃちで実用的とは言えず、そうして行き着いたのがマルサンカバン店でした。
山菜王国秋田の、地元に愛される山菜バッグ、やはり職人が丹精込めてつくった品は違います。
ちょうど食べごろのコシアブラ。
「大好きなので、採ってきてけろ!」というリクエストにもお応えして(笑い)。
コシアブラは家の周りにいくらも生えているので、10分もすれば大量の収穫です。
ただしコシアブラは陽気によって葉が一気に展開するので、採り頃は4~7日ぐらいと非常に短いのが特徴です。よって口に入るというのは幸いなことなのです。
山にコゴミを採りに行く。
あおいコゴミを採りに行く。
めざすコゴミ場は筆者の家から歩いて20分ほど、そこはスギ林の中でほとんど無音の世界です。
スギ林の土というのは非常にやせていて菌類や土中生物や昆虫も乏しく、したがってそれに引き寄せられるべく鳥も獣もいないのです。これが落葉広葉樹林と大いにちがうところです。
コゴミ場はそうでも、その道々はコナラ(小楢)を主とした広葉樹林、その楽しいにぎやかさ。コゴミを採りに行くというのは、野鳥のさえずりのシャワーを浴びるということです。
(以下、鳥の画像はネットからの拝借です。せめてもの礼儀として、最小限ですがクレジットを入れています)。
黒のネクタイがお似合いのシジュウカラ(四十雀)。ツピツピツピ、と。

ツツピーツツピー、ツツピーツツピーと啼くのはヤマガラ(山雀)。

何とも表音しにくいけど、抑揚よろしくうつくしくくりかえして啼くのはイカル(鵤)です。
うつくしい声に反していかつい顔つき、種名の“鵤”は角のように丈夫な嘴(くちばし)に由来するとのこと。

日本の野鳥の中で最もうつくしい鳥のひとり、オオルリ(大瑠璃)。日本三鳴鳥のひとり。
体長は15センチほどで、名に“大”とつくけど決して大きな鳥ではありません。
様々な節回しを連続して響かせて、林の中の明るさを一層際立たせています。

日本三鳴鳥のもうひとりはウグイス(鶯)。
よくよく聴いていると、個体個体で鳴き方が微妙に違います。声の質も抑揚も。
宮澤賢治に「セロ弾きのゴーシュ」という物語があって、そこでカッコウがそれぞれはちがう鳴き声を持っていると主張する場面があるけれど、本当にそう。
人間だれしも違った顔、ちがった声、ちがった心持ちであるのと同じく、鳥もまた同じことだとつくづく思わされるのです。
ちなみにですが、三鳴鳥の残るひとりはコマドリ(駒鳥)。残念ながらルーザの森にコマドリはいません。

ミソサザイ(鷦鷯)。
体長が11センチと小さな鳥ながら、ものすごく甲高い声で口早に連続して啼いています。一度聴いたら耳から離れない美声です。
渓流に多く、ああここはミソサザイに選ばれた場所なのだと思わされたりします。

ツツドリ(筒鳥)の、まさに筒を吹く時のような、ホホウ ホッホ ホホウの平和なこと。この鳥のホホウに見送られていく山道のうれしいこと。
ツツドリとカッコウ(郭公)とホトトギス(鵑)はともにカッコウ科カッコウ属の兄弟ともいうべき鳥たちで、姿かたちが非常によく似ています。けれども、それぞれに鳴き声はまったく違うし、名前にして違います。おもしろいことです。

山にコゴミを採りに行く。
あおいコゴミを採りに行く。
ちょうど、コゴミ場に出る手前に、フキノトウ(蕗の薹)の雄花と雌花が並んで出ていました。
上の写真が雄花で、下が雌花です。
やがて雄花の茎は枯れてしまいますが、雌花の茎はグングンと背をのばし、よい頃合いを見てタネを放出して風に運んでもらいます。
フキノトウはフキ(蕗/キク科フキ属)の早春の花茎。
我が家も天ぷらでいただきました。
オオウバユリ(大姥百合/ユリ科ウバユリ属)のみずみずしい若葉。
オオウバユリの球根はアイヌの重要な食料のひとつで、でんぷんを採取してさまざまな料理に用いていたということです。
*
山にコゴミを採りに行く。
あおいコゴミを採りに行く。
今年はじめてのコゴミ採りはこの25日のこと、様子見のつもりで行ったのだけれど採取の時期がぴったりでした。
ほうけている(展開している)ものはほとんどなく、まさにこれからが採り頃という感じでした。
こんなグッドタイミングははじめてのことかもしれない。
昨年の古い葉の中から今年のあたらしいいのちがわいてきています。
このコゴミのあおさ(青さ、緑さ)、このみずみずしさ。
ここはコゴミだらけで、まるで誰かが栽培した畑のようです。
きっと、神がこしらえたんだと思います。
筆者はここまでコゴミ(屈)、コゴミとしてきたけれども、コゴミの標準和名はクサソテツ(草蘇鉄/オシダ科クサソテツ属)です。
でも東北にソテツ(蘇鉄)はないしソテツに親しみがないために、コゴミをクサソテツというひとは誰もいないと思います。不適切な命名の例と思いますがね。
標準和名のゼンテイカ(禅庭花)をニッコウキスゲ(日光黄菅)と言い換え、標準和名チシマザサ(千島笹)をネマガリダケ(根曲竹)とあえて呼ぶのと同じことではありますが。
展開したコゴミ、かつての写真から。
実においしそうなコゴミたちです。
ちょうど採り頃、食べ頃です。
コゴミは今スーパーや道の駅にもワンサと並びはじめているようだけど、パック詰めされたもののような展開ものは筆者は採らないですね。伸びすぎていると思います。
これはアブラコゴミ(油屈)。
コゴミに似ているからこう呼ばれているだけで、コゴミとは別属別種です。標準和名はキヨタキシダ(清滝羊歯/メシダ科ヘラシダ属)と言います。
アブラコゴミは株立ちをしないことが特徴、ということは収量が乏しく、マーケットに出回ることはほぼないのではと思います。
下は今回のものですが、このような立派な群落に出会うというのは実にまれです。
なぜアブラコゴミなどと言うのかといえば、同じおひたしにしても、アブラコゴミの方がコゴミよりもほのかに甘い感じがするのです。食べ比べもおつなものです。
山菜バッグがいっぱになればリュックに移し替えます。
このリュックはこれでバッグ2杯分です。
*
山にコゴミを採りに行く。
あおいコゴミを採りに行く。
コゴミ採りに行くというのは早春の花々と出会うことでもあります。
下は、貧相な土壌にも育つエンレイソウ(延齢草/シュロソウ科エンレイソウ属)。
大きな三つ葉が特徴的です。
やがて花の部分に大きなボール状の実がなって、熟すと甘くておいしいです。
と、一昨年の月山登山で知り合った新潟は田上(たがみ)にお住いのHさんが最近北海道の函館山を散策してきたのだそうで、めずらしいエンレイソウの画像を送ってくれました。
濃いピンクの花びらの愛らしいエンレイソウ、名をコジマエンレイソウ(小島延齢草)というのだそうな。
コジマは渡島小島(おしまこじま。北海道松前町に属する無人島)から来ていて、北海道(特に松前)と南樺太に分布があるのだそうです。うつくしいです。
ちなみですが、尾瀬にはシロバナエンレイソウ(白花延齢草)があったような。
ショウジョウバカマ(猩猩袴/メランチウム科ショウジョウバカマ属)。
ここはたかだか標高が500メートルそこそこだけど、2,000メートル級の山にも、かたや200メートルほどの米沢の町場でも見かける非常に垂直分布の広い植物です。
スミレサイシン(菫細辛/スミレ科スミレ属)。
筆者にとってスミレサイシンはコゴミ採りとセットです。
貧相な土壌のスギ林の中に、うつくしい青いひかりを放って咲いています。
キブシ(木倍子/キブシ科キブシ属)。雪国の早春を代表する花です。
若い頃はこういう花は目に入らなかったと思うけど、年を重ねるにつれそのうつくしさが沁みてきています。
カスミザクラ(霞桜/バラ科サクラ属)。これは広葉樹林の道々で。
カスミザクラは自生するサクラの一種で、オクチョウジザクラ(奥丁子桜)のあとに咲いてきます。
大きなものになると、満開の頃は霞がかかったようになることからの命名と思います。
この27日の夜のことでしたが、外出から戻った相棒と筆者は、暗闇の中に何だかパンパンという連続音がするのに気づきました。あちこちで豆鉄砲の撃ち合いでもしているふうなのです。そうして思い当たりました。それはフジだと。
フジ(藤/マメ科フジ属)はある定められた早春の一日(たぶん夕方から夜にかけて)、自らの豆の鞘(さや)を思い切りねじって、鞘ごと飛んでタネをばらまくのです。パンパンはその時の音です。10メートルくらいも飛ぶ者もあるよう。
種の拡散戦略のひとつ、こういうのを目にすると感動をさえ覚えます。
コゴミ採りからの帰り道で見つけたたくさんのフジの鞘。タネがひとつ、鞘の内側についていました。
家路、デデッポッポ デデッポッポというキジバト(雉鳩)に送られながら。

突然の羽ばたきにびっくりしたヤマドリ(山鳥)。
2~3メートルぐらいの近くまで行かないと危険を察知せぬのか、ヤマドリは警戒感が乏しく、親しい鳥です。

*
山にコゴミを採りに行く。
あおいコゴミを採りに行く。
そうして2時間ほども歩き回って、家に戻りました。
収量はご覧の通り! リュックの重さにモックラカックラして(よろよろして)(笑い)、ようやく自宅に辿りつきました。
この大量のコゴミなどはふだんからお世話になっているひとに配ります。そしていつも品物を届けてもらったりこちらから送ったりしている知人、友人に送ります。日ごろのおつきあいの感謝を込めた筆者からの気持ちです。自家消費なんてほんのわずかなものですし。
その梱包と発送の作業もまたたいへんなものでして(-_-;)。
そうして我が家では…、コゴミとアブラコゴミとコシアブラをおひたしに。それから左みっつにタラの芽を加えたものを天ぷらにしました。
東を向いて、オホホホホと笑って。…これは初物を恵んでくれたお日さまへの感謝です。
下は、ある日の晩の食卓。
と、賢治仲間ともいうべき宇都宮のHさんがさっそく料理に使ったと、その画像を送ってくれました。
コシアブラのおひたしはちくわとの和えものに。タラの芽、コゴミ、アブラコゴミ、コシアブラの天ぷら。コゴミはさらに胡麻和えに。いただきものの筍を定番ニシンと山椒の実で煮物に。それに筍ご飯、なのだとか。
彩り豊かバリエーション豊かな山菜の使いようです。そして相棒と乾杯した、という報告です。
ん~ん、ワンダフル!
山菜は時間を追うごとに次から次へと移り変わっていきます。
これからは、ハリギリ(針桐) やタカノツメ(鷹爪)や木の芽(アケビの萌え)が加わり、そのうちゼンマイ(薇)が出てきます。どうしてだろう、山菜採りの中でも、ゼンマイ採りは特に興奮します。
そしてワラビ(蕨)とフキ(蕗)の収穫が一段落すると梅雨がやってくるのです。
そうしてルーザの森の季節はめぐっていきます。
新緑のうつくしい季節になってきました。どうぞ、それぞれがよい時間を持てますように。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。ただし今回に限り、一部拡大を意図して制限しています。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。