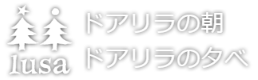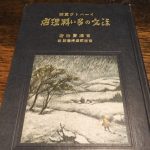本日は(2025年)1月17日、阪神・淡路大震災からちょうど30年の日です。
そのとき1995年1月は我が家が市中からここルーザの森に越してきて1年余りのこと、朝のラジオから聞こえてきた巨大地震のニュースには驚くばかりでした。
30年前の当時の日記に当たれば(筆者は中学1年より日記を書いている)、ここでは14、15、16日と3日連続の大雪に見舞われていたよう、そんな中で届いたニュースでした。
そして今年も、雪はずいぶんと降っています。あきらかに昨年のあまりの少雪の反動です。
今回のsignalは雪のこと、題して「雪だなあ」。
*
雪だなあ。
雪は8日夕方からひっきりなしに降り続け、ようやく収まったのが10日の朝のことでした。
ニュースでは警報級の降雪とは言っていましたが、その通りでした。雪には慣れているはずだけれど、ちょっと怖いぐらいの降りようでした。
3日にもわたって雪が降り続ければ、それを迎えるこちらがいくら頑張っても除雪は追いつかず、体力は奪われるばかり。疲れました。
米沢の大雪がテレビの全国ニュースで流れていたらしく、特に太平洋側の都市部に住む友人や知り合いから、大丈夫か、とか、被害に至らなければいいのですが、とか心配やらお見舞いやらの電話やメールが入りました。
気遣いはうれしかったです。
とはいえ我々は雪には慣れているし、決してヤワではないし、知恵を出しながら体力勝負で日々をしのいでいます。大丈夫!
幼い頃(1960年代初頭)を思い出します。
筆者の生まれ育ったのはここから約30キロ先の、宮内町というところの(現 南陽市宮内)やはり山あいの集落でした。
まだ家々に自動車というものがない時代のこと、幹線道路(とは言っても砂利敷きの)に除雪車がようやく入るようになってきたという記憶があります。
けれども家から幹線道路までは約400メートルほど、雪が積もれば道つけ(歩き道の確保)が必要で、それは隣組(下組)2軒1組の輪番となっていたものです。
道つけは学校に通う児童生徒のため、家々の生活道路の確保のために7時ころまでには終えるようになっていたと思います。
親が作業に出られないときは10歳そこそこの筆者もその任に出されたものです。
長靴の下にカンジキをつけて、踏みしめ踏みしめ…、足の片方ずつを炭俵につっこんで歩く大人のひとと組んだ記憶もあります。
そうしてひと汗かいて、家に戻って朝食をとって、それから約3キロの道のりをたどって小学校まで行きました。
そんな時代、それが普通のことでした。

休みの日など寒くて布団からなかなか抜け出せないときには、母親に叱られたものです。「いつまでもカナしがっているな!」と。
“カナしがる”は“悲しがる”でしょうが、寒さのために身が縮こまって何もしたくない面持ちの方言だと思います。が、これは米沢では使わないので同じ置賜(おきたま)地方でも宮内の、ともすると母親個人だけの言い回しだったのかも知れず。
(※ ↑ 上は筆者の認識不足。置賜一円の方言でした)。
そう冬場、雪国のニンゲンはこのカナしさとの闘いの日々と言っていいのかもしれない。
少年時代、小さな集落ながら同級生が6人、小学生だけでワンサといた時代、いつもどこからか誰ともなく集まってはこっちで遊びあっちで遊びして、日が暮れるとそれぞれが家に帰っていくという時代でした。
冬の遊びはほぼスキーでした。
その頃のスキーは、スキー板の裏にようやくエッジというものがつきはじめ、そのエッジは1本が約1尺ぐらいの長さの継ぎ合わせで、ところどころ木ネジでとめてあったような。靴はまだ長靴で、うしろをバネの開閉式のバックルで留めていたような。
雪が積もれば、1キロくらい先のゆるやかなスロープのあるブドウ園にはよく行ったものです。
上から下まで100メートルくらいを滑走したり、ときに小さなジャンプ台をつくって飛距離で競ったり…、楽しかったなあ。
誘いに乗ってくる友だちがいないときはひとりでも滑っていたことも。ときに遊び疲れてウトウトしてしまい、雪がコンコンと降る中で眠ってしまって、ハッとして目覚めたら身体に雪が積もっていたなんてこともあったっけ。今思うとゾッとしますが(-_-;)。
そうそう、雪で思い出すのは小学校2年生ぐらいの2学期末のこと。
終業式前日のことだったと思うけど、古い木造校舎の1階の(机と椅子を廊下に全部出した)教室に外の雪を大量に投げ入れて、クラスの大勢がスケートをするように動き回るのです。
そうすると板張りの床の汚れで雪はみるみる汚くなり、その汚れた雪をスコップなどで掻き集めて今度は窓の外に放る…、そうすると木の床は見違えるほどに白くなる…、これが“雪入れ大掃除”というものでした。
なつかしいなあ、楽しかったなあ。
ついでながら記せば…、
時代そのものがちがうので、自分や当時の子どもたちと比較はしないけれども…、
雪が止んだ休日に町に出れば、家のまわりに屋根にとひとがくりだしてはまるで巣を突かれたアリのように一生懸命に除雪にいそしんでいます。というのに、不思議なことは子どもの姿はほとんど見られないのです。
つまりこれは、親が労働力として子どもに、働けという指示をしないということ、一緒に働こうと誘わないということでしょうか。それに対して子どもは甘えてしまっている。
こういうのって、子どもの成長のせっかくの機会を親自らが摘んでいるようでやりきれないのだけれど…。
これは筆者の不当な憶測、思い過ごしというものでしょうか。
*
雪が少し降りやんだこの10日、積雪は早くも150センチを超えていました。
このあたりで150センチ超えは決してめずらしいことではないのだけれど、時期が早すぎます。1月の末ならこれは分かるのです。
除雪車が来て、道の雪を掃いていきます。
普段はここの場所での除雪車の通過は朝のまだ暗いうち5時45分ごろのなのですが(筆者は5時半に起き出して除雪機を動かしはじめている)、この時点で7時を過ぎていました。それだけ雪が大量に一気に降って除雪車の働きもままならず、作業は遅々として進まなかったということでしょう。
道の両側の木も雪の重みで垂れ下がって。
笊籬溪(ざるだに)の雪景色。
*
雪だなあ。
雪について書かれた物語で、宮澤賢治の「水仙月の四日」(童話集『注文の多い料理店』に収録)を超えるものがあるのかどうか。
物語の時期としては3月末から4月はじめの、春がもうそこまで来ているというあたりが舞台ですが、すさまじい吹雪、荒れ狂う空、ずんずんと雪が積もって風景を変えながら、ひとつの小さな命をめぐって精霊たちのそれぞれの思いが交錯する…、その迫力は圧倒的です。
決してファンタジーに収まらない本当の雪について知りたいのなら、まずはこの物語を読んでから、でしょうか。
下は、知人にいただいた『注文の多い料理店』の復刻版です。表紙が「水仙月の四日」ですね。
これが復刻版ではなしに本物で、「なんでも鑑定団」に出品されたのなら、1億円は下らない額がつくのでは(笑い)。
当時は1千部つくったけれどもどうにも売れないものだから、運動会の景品にもしたという逸話も残っているほどで(笑い)。それが今や、です。
雪といえば、木版画の斎藤清(1907-97)。
福島県会津坂下(ばんげ)町出身の斎藤が木版画として制作した「会津の冬」シリーズほど雪の本質をとらえたものはないかもしれない。
この日本海側気候内陸部特有の鉛色の空、あたりを覆いつくす綿のような、毛布のような分厚い雪の白、点景の黒いひと…。雪とその下で暮らすひとびとに愛着を込めた斎藤の版画は文句のない傑作です。
福島県は奥会津に位置する柳津(やないづ)町には町立の斎藤清美術館があって、筆者は年に1度は斎藤の作品群に見入っています。

*
筆者は実は集落29戸の町内会長を務めています。
本当はこの12日に、斎燈焼き(サイドヤキ。どんと焼き)と(感染症明けの久しぶりの)新年会を予定していたのですが、この突然の大雪で急きょ中止の判断をしました。
斎燈焼き周りの環境の整備(除雪)が追いつかず、駐車場の確保がままならなくなってのことです。
秋の萱刈りと斎燈焼き塔の設置にはじまり、食材の調達計画や目出度い席の「謡い」のリードの願いなどさんざんに準備を進めてきた中での決断はとてもむずかしいものでしたが。
それで各隣組長を回って説明し、文書をつくって全戸配布の手配に動き回ったのが晴れ間がのぞいた10日の朝のことでした。
10日の朝の、雪がおおった笊籬沼(ざるぬま)。
右手に笊籬沼、この先に笊籬橋があります。
よく積もりました。
と、町内を回っている途中、キジ(雉)が道端で何かついばんでいましたよ。
除雪で見えた土の中にミミズでも見つけたものか。
そして、道路わきにカモシカの子どもがたたずんでいるではないですか。
あたりに母親は見当たらないことから、年齢は2歳弱、餌場のテリトリーから追い出され自立を促された子どもかと思います。
カモシカはこちらが近づいてもその場を動こうとはしませんでした。立ち上がっては腰を下ろし、何とか動こうとするのですが、それができないのです。けがをして傷ついているようでした。
この、助けを求めて哀願するような眸。
かわいそうとは思ったけれど、筆者にはどうすることもできず。それで市役所に通報することにしました。
市役所では担当部署(教育委員会社会教育文化課)に話を通して対処するとのこと。カモシカ(羚羊/ウシ科ヤギ亜科カモシカ属)は国指定の特別天然記念物、保護規定にのっとって元気になったら山へ返す、弱ってしまって死んだ場合は所定の場所に埋葬する、それで了承してほしい、ということでした。
気になって、数日して後日談を聴けば、職員が現場に向かったものの、すでに姿はなかった、移動したようだとのことでした。
そうか、動いたのか。
あのカモシカ、今どこで、どうしているだろう。
*
雪だなあ。
L字形になっている我が家の主屋の内側のコーナー。
ガラス窓には板を渡して落雪から守っていますが、それももう限界です。
相棒が雪の山を上からスコップで崩して、自分は下から崩し、崩したものがたまれば待機する除雪機で飛ばし…、このくりかえし。
この場所の除雪は今冬で3度目です。
と、大切なカリン(花梨)の木が雪の重みに耐えかねて大きく傾いていました。かわいそうに。
スコップで掘って枝を雪中から引っ張り上げて、救出。
今回もセーフ、でした。ヤレヤレです。
春になったら、支えの棒を取りつけて傾きに耐えられるようにしたいと思います。
屋根から雪が落ちて、下の雪と屋根の雪がくっつくようならこれが除雪の最終的なサインです。
そのままにしておけば雪が嵩(かさ)を減らしていくときにものすごい力が加わって、場合によっては建物の構造を歪めてしまいます。
雪は、積もって上から重量を圧しつけるだけでなく、大気がゆるんで沈み込むことも要警戒なのです。
この時期、雪折れのリンゴの枝が話題になりますが、これも同じこと。そのままにすれば雪に枝が引っ張られて幹が裂けたり太い枝でも折れたりします。カリンを救出したのはこのためです。
下はヒュッテの西。もうこれで2度目のことです。
除雪機が前進するためのアプローチを切り拓くことがまず難関です。
除雪機が直下まで到達し、スコップで崩しながら少しずつ屋根の下の雪を除いていきます。
車庫の雪。
難儀するのは、何と言っても主屋の大屋根の北側の雪。
ここは道路に面しているため、落ちた雪をそのままに放っておけば、あとは道路に落ちるばかり。そうなればクルマの通行に支障が出るのでここは何としてもある程度の落雪で除雪が必要になります。
下は、大屋根の下までのアプローチを切ったところ。
大屋根の直下。
薪小屋(キツネ小屋)。
下は、雪をスコップで切ったために屋根にかかっていた雪が一気に落下した図です。
この雪切りの作業はけっこう危険がともないます。万が一のため、とっさに後ろに飛びのくシミュレーションをしてからの作業となります。要注意です。
日当たりがことのほか悪く、年末から一度も落ちない一番東の小屋に上がって、雪下ろしをしました。
深いところでひきしまった雪が100センチにも達していました。
下では、相棒のヨーコさんがスノーダンプで除雪車が置いていった砂利交じりの雪を片づけています。
とまあ、いろいろと書いてきたけど……、
町場ならまだしも、なぜにそんな不便な、大変な山あいに好き好んで住んでいるのかと首をかしげるひとはきっといると思います。
雪は確かにたいへん、でも、強がりを言うようだけれど、雪かきも楽しいことよいことはあるのです。
身体を動かして、暮らしの現場をどうにかよい状態に少しでも変える…、これはものつくりの喜びに通じることです。汗して働いた後の充足感、そうしてひとは手と足に働きかけてこそニンゲンセイをかみしめてきたのでは、とも思うのです。ごはんもうまいし。
そして、筆者は一度だってここがイヤだと思ったことはありません。第一に、季節のうつろいのうつくしさは格別なのです。
愛読しているタウン誌(出羽庄内地域文化情報誌)に「Cradle」(クレードル)というものがあるのですが(これは持ち出し自由のフリーペーパーながら読み物としてすばらしい質を持っている)、この冬号は特集「山にまつわる聞き書き」として山棲みのひとたちの暮らしを取り上げていました。
特集冒頭、朝日連峰の麓、旧朝日村大鳥(現 鶴岡市)に住む工藤朝男さん、昭子さん夫妻が語っていたことに相槌を打ちました。
この人(夫)が、春の芽吹きど秋の紅葉がいいがら町さ行がねって言ったんだ。 …昭子さん
芽吹き見れば長い冬も何もかも忘れる。自然の中に生きでるどそういう心持ちになるんだがもな。 …朝男さん
夫妻は、冬の苦々しさはあれど、春のうつくしさと秋の彩りはすべてにまさるというのです。
そう、自然のうつくしさはすべてを凌駕するということです。
除雪作業の自分へのご褒美、それは決まってビールとワインです(笑い)。
こうして、窓の外のミニバスケットに差しておけばキンキンに冷えるというわけで(笑い)。
日が沈んで働くことができなくなったらビールに手が伸び(笑い)、夕食後にはワインが待っています(笑い)。
*
雪だなあ。
この13日、夜なのに窓の外が妙に明るいなあと思って外に出てみると、うつくしい月夜でした。
真夜中だというのに、月のひかりだけでこんなに明るいのです。
これなら懐中電灯なしでも外を歩けます。
幼い頃、用あって、人家のない雪の月夜の道を隣の町まで、父と歩いたことを思い出しました。あの白さ、あの明るさがなつかしいです。
この林のすぐ先が溪谷、V字に切れこんだ笊籬溪(ざるだに)が走っています。
除雪車に押し上げられた雪の山に登って、少し上のアングルから撮った我が家。
手前がルーザの森クラフトの工房とヒュッテ。
夜の青空!
主屋を南側から。
*
彩りうすい冬にあって、室内だけでも彩りをと。
主屋内の製品の展示ギャラリーに飾ったノイバラ(野茨/バラ科バラ属)のドライ。
この赤い実は利尿や便秘の薬に利用されるのだとか。
我が家では飾るほかに、果実酒として漬け込んでいます(笑い)。
冴えた黄水晶のようなうつくしい色になります。
玄関口のしつらえに、道端からもらってきたツルウメモドキ(蔓梅擬/ニシキギ科ツルウメモドキ属)を飾っています。
この赤もいいものです。
そして小正月の、いつもの団子木飾りを。
敷地に自生するミズキ(水木)の枝を伐って、船せんべいを下げて。
こうした彩りこそは、はやく春よ来いと願う雪国の民衆の素朴な願いが形になったものだと思います。
いつもリビングに果実酒が4本ほど。
左から、カリン(花梨)酒、いただきもののローゼル酒、いただきものからつくったユズ(柚子)酒、ナツハゼ(夏櫨)酒。
それぞれにいい色を出していますが、味もなかなかなものです。
自生するクランベリー(ブルーベリーなどのツツジ科スノキ属の総称)の一種のナツハゼは、格別においしいです。
テーブルの上に。
このあいだ来客があって、お持ちいただいた干し柿。
冬の、この自然な甘みのありがたいこと。
白粉を噴いた干し柿も、彩りのひとつ。
あと1か月の我慢と辛抱。
あと2週間もすれば、雪が引き締まる上に表面が凍って堅雪ができます。そしたら雪渡りもできましょう。林を抜けて、白い広場を縦横無尽に行きましょう、凍った沼も渡れましょう。それは楽しみです。
それから今年は、スノーシューで歩いて西吾妻の樹氷を見に行ってみたいな。
2月の20日ともなれば、あとは吹雪が来ようが積雪があろうが知れたものです。
あとはただ、春のにおいを待つばかりとなります。
嗚呼、また、雪だなあ。
*
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をさらにクリックすると写真が順次移りかわります。