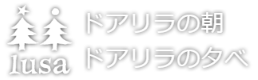本日は(2025年)10月24日です。
北海道の知り合いによれば、大雪山系の旭岳や富良野岳には初冠雪があったとか。今朝の新聞には我が月山にも初雪、もうそういう季節です。
こちらの今朝の外気温は2.5℃、ここまで下がるともはや薪ストーブの本格稼働です。
この、寒くなって薪ストーブがほしくなる時期が好きだなあ。
薪ストーブを焚けるうれしさ、筆者にとって薪ストーブは人生のかけがえのない友だちなのです。そのための森暮らしと言ってもよいのです。
さて、この19日には町内会の自主防災組織の避難訓練(地震想定の避難と安否確認)と抱き合わせの芋煮会、さらには近隣三町内会の交流会も併せての行事を行いました。ビッグイベントでした。
それは、縮小を続ける地方のコミュニティーに咲いた、ひと時の華というべきものだと思います。
筆者は町内会長として(隣組の輪番です)その企画・計画と指揮のトップにあったわけで、すべてが無事に終了してほっとしています。
大勢のお客様をお迎えして。

そんなこともあって、昨日23日に、息抜きの山歩きをしてきました。
その何でもないいつもの山歩きながら、予期せぬうつくしい光景に出会った…、今回のsignalはその書きとめです。題して「霧氷の山」。
*
筆者のホームグラウンド、西吾妻のロープウェイとリフトの(夏季の)営業ももうすぐ終了です。その日までに西吾妻に向かわなければならない大事な用がありました。
大事な用というのは、西吾妻山への取りつき、西吾妻最大のお花畑の大凹(おおくぼ)にある水場の看板の回収をしに行くことがそれです。
自分でこしらえた看板ゆえに、ここ数年、冬季は家に持ち帰って保管することにしているのです。いくらかでも長持ちさせたいと思って。
下は、スクラップ同然になっていた、かつての水場の看板。
オリジナルを再現して新たにつくった看板。2022年8月。
この看板の製作のくわしいことは、かつてのsignalを見ていただければ幸いです。signal「水場の看板」
朝、ロープウェイ下駅でなじみの従業員のSさんに、「リフトの上(1,810メートル)の気温はどのくらいだろう」と聞けば、「氷点下のようだよ。氷が張っていると言ってた」とのことでした。
寒さを覚悟して、事前にレイヤーを重ねました。

リフトの係員には、「上は雪が降ったようだ、気をつけて」と声をかけられました。
そう言われてみれば、3基の最終リフトから見える中大巓(なかだいてん。1,963メートル)は白くなっています。
ん~ん、ワクワクです(笑い)。
まだ11月にもならないというのに、雪に会えるってすごいじゃないですか(笑い)。
けれども歩きはじめて分かったことは、その白いものは雪ではありませんでした。
ではと思いをはせれば、かすかに遠くから、「霧氷」ということばがやってきました。
でも、自分が知っている霧氷とはあきらかにちがう。
これが筆者が知っている霧氷。2月半ばの家の近くで。
霧氷は空気中の水蒸気が冷やされて凍り、空気の動き(風)によって樹木などに付着するものです。
登山道には今まで聴いたことがないようなインストゥルメンタル、やさしい響きの連続です。
シャリリリ…、シャリシャリシャリ…、シャリリンシャリリンシャリリン…、パリパリパリパリパリリ…シャシャシャシャシャシャシャシャ…、パリリンリン…。
まず、この魅力的な音に驚きました。氷片が音立てて次から次へと降ってくるのです。
樹上高くより舞い落ちる、うすい氷片。
日が差してきて、空気があたたまって、シャリシャリ音の鳴り響く登山道。
なんとうつくしい、天楽だろう。
そしてこの、造形のうつくしさ。
霧氷。
「霧氷」といえば、橋幸夫(笑い)。
筆者は小学3年、我が家にテレビというものが入って1年目のことでよく覚えているのだけれど、さかんに流れていたなあ(笑い)。
今、歌詞を追っても意味は分からず(笑い)。初冬の恋?? 恋はすぐ溶けて一瞬、ということ??(笑い)
霧氷。
霧氷。
西吾妻を代表する樹木のオオシラビソ(大白檜曽)の霧氷。
やがてオオシラビソは樹氷(アイスモンスウター)を形づくっていきます。
調べれば、樹氷というのは霧氷のひとつなのだとか。この関係は知らなかったなあ。
ガンコウラン(岩高蘭)の霧氷。
ハイマツ(這松)の霧氷。  そして地面には、長く伸びて盛り上がった霜柱です。
そして地面には、長く伸びて盛り上がった霜柱です。
人形石より見える霧氷の山。
霧氷の山は、やがて樹氷の山になります。
西吾妻は知られざる樹氷の名所なのです。
西吾妻山方面。
中ほど、開けている場所が大凹で、ここが最大のお花畑です。
もう冬です。
山にはもうすぐ雪が来ます。
*
日が高くなって、尾根筋には霧氷はとけてなくなっていました。
褪せつつある大凹の彩り…。
ゴゼンタチバナ(御前橘/ミズキ科ミズキ属)が凍みていました。
クロマメノキ(黒豆木/ツツジ科スノキ属)の紅葉。
まだ果実をたくさんつけているよう。
クロマメノキとガンコウラン(ツツジ科ガンコウラン属)の赤と緑の妙。 
イワカガミ(岩鏡/イワウメ科イワカガミ属)の深い臙脂(えんじ)の紅葉。
イワカガミは常緑とされるけれども、冬に向かえばこんなふうに色変わりします。
あたたかな色に変わって、身を守ろうとしているのかもしれず。
チングルマ(稚児車/ダイコンソウ科チングルマ属)の紅葉。
本来のビビットな赤からはだいぶ色褪せています。
高層湿原をおおうヌマガヤ(沼茅/イネ科)は、晩秋にふさわしい枯れ色です。
池塘に生えたミヤマホタルイ(深山蛍藺/カヤツリグサ科ホタルイ属)も枯れ色。
そして向かった先は、大凹の水場です。
本当は看板はオリジナル通りに水の流れの左に置いていたのですが、水が降りかかるのを避けてか、登山者のだれかが位置を変えてくれていました。
看板を回収したところで仙台からいらしたという(筆者と同年代と思しき)ご夫婦とあれこれと山談議、高山植物談義。晩秋の晴天にあって、ご夫婦して心から山歩きを楽しんでいるようでした。
実はここで、うすぼんやりしていた霧氷のことがはっきりしたのです。
夫君はこういう山の自然現象にくわしいらしく、いろいろと解説してくれたのでした。
霧氷は自然現象が整わないとできないもの、湿った空気、急冷、そして強い風…、この3つの条件がそろってはじめて霧氷はできる…、昨晩は一帯に濃いガスが発生し、それが冷やされ、強風が吹いた、それで霧氷が育ったということ…、今日はとてもラッキーと言っていました。やはり、ラッキーだったんだ。
下は、看板わきの氷結。
水しぶきが飛んで枝が凍りついています。
*
帰路、下りのリフトからの彩りです。
天元台のリフトは3基で、総延長2,500メートル。標高差500メートルをゆっくりと下っていきます。
天元台は、さながら移動植物園、移動紅葉園地なのです。
オオシラビソに入り混じるダケカンバ(岳樺/カバノキ科カバノキ属)の白い幹。
風雪に耐えて屈曲することしきり。
ダケカンバの若い木とまわりの彩りと。
不思議なことですが、広大な吾妻連峰はダケカンバの美林でおおわれていると言っていいけど、同属のシラカンバ(白樺)は1本もないのです。
赤はナナカマド(七竈/バラ科ナナカマド属)、
緑はコメツガ(米栂/マツ科ツガ属)、
クリームイエローはタムシバ(田虫葉/モクレン科モクレン属)でしょうか、
黄色はミネカエデ(峰楓/ムクロジ科カエデ属)。
ダケカンバの白い直線もピリッとしている。
ナナカマドにミネカエデ。
右上の緑はハクサンシャクナゲ(白山石楠花/ツツジ科ツツジ属)のよう。
赤はサラサドウダン(更紗灯台/ツツジ科ドウダンツツジ属)、
緑はタムシバのようで。
ウリハダカエデ(瓜膚楓/ムクロジ科カエデ属)のオレンジ。
望遠は色が褪せはじめた山肌です。
天元台の紅葉は今、リフトの中ほどを駆け下りているみたい。
今年は色づきがとてもよいと思います。
そしてこれから、彩りを増していこうとするロープウェイライン。
*
霧氷の白い景色には感動しました。シャリシャリの音、氷片のうつくしさ。
めったに出会えないことに遭遇できた幸運を思います。
東北の紅葉があざやかなのは、やがて来る白く冷たい季節の前に、それを乗り切るために、せめてこころには色彩をいっぱい貯め込んでおきなさいという神の差配のようにも思うのです。
もう冬支度のあれこれを思案する季節となりました。
雪が来るまでのこれから約1か月が勝負、しなければならないことを数えて、しっかり準備していきます。
そしてまた、雪に立ち向かっていかなくちゃ。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。