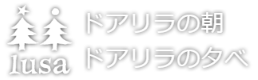本日は(2025年)9月27日、ずいぶんと涼しくなりました。22日の朝の外気は10.5℃でした。
涼しいというより、寒い。暑い暑いといってもそこはやはり秋分です。
家では、薪ストーブの点検とガスケットロープの張り替えなどのメンテナンスを終えて、試し焚きもしました。
9月に入ってから今日までというもの、筆者の日常はパタパタ、バタバタ。
公私にわたってさまざまな課題があって、その解決に追われていたという印象です。
町内会長として、集会所(公民館)わきの、今は不要になっているポンプ小屋を住民たちだけで解体したのは大きな事案でした。
業者に頼めばゆうに15万とか20万という請求が来そうな作業を、費用を一切かけないで成し遂げたのは大きかったです。コミュニティーの力です。
ついての廃材処理やら、慰労会やら…。
そんなせわしない日々がひと段落、秋分の日に山を歩いてきました。
コースはいつもの西吾妻でも西吾妻山とは逆方向、人形石より先の縦走路の、風光明媚な池塘群・小凹(こくぼ)の手前まで。
登山というよりハイキング、なにせ気分転換ゆえの。
ということで、今回のsignalは、題して「秋分に、小凹への道」です。
色づきはじめた山のたよりを少しばかり。
*
秋分の日、休日とあって、8時20分のロープウェーの第2便に乗ろうとすれば約60台収容の天元台湯元駅の第1駐車場はすでに満杯(それほどの人出)、しかたなく第2にまわって、それからの出発でした。
雪が降ればゲレンデとなる天元台は今、ススキの銀の穂波。
乗り継いだリフトをリフトトップ(1,820メートル)で降り、人形石方面への直通ルートを歩いてみました。何10回と登っている西吾妻にしてはじめてのことです。
下りでは何回も通っているのにコースを逆に進むことの新鮮さ。逆に進むと、風景もちがっていました。
歩いて約30分、ほどなく岩海の人形石(1,964メートル)です。
西吾妻は池塘(ちとう)群がうつくしいところでもあり。
池塘も秋色です。

池塘を取り囲む植物は、ヌマガヤ(沼茅/イネ科?属)と
キンコウカ(金光花/キンコウカ科キンコウカ属)らの入り混じり?
と、ほどなく、登山道上で大きな獣の糞に出くわしました。
これは大きさからしてクマ=ツキノワグマ(月輪熊)の落とし物ですね。
巷では今、町場へのクマの出没で話題沸騰のようで。
西吾妻にツキノワグマが生息しているのは分かっているけれど(西吾妻スカイバレーを運転中、親子のクマに出会ったことがある)、登山道上に糞というのははじめてのことです。
糞を興味深く観察すれば、用を足して1日か2日経っているもののようだけど、クマ特有にして匂いがしません。クマは基本、草食だからです。
内容物を見てみると、ナナカマド(七竈)の実がそのまま、それからハイマツ(這松)やオオシラビソ(大白檜曽)の松ぼっくりをたくさん口に入れていることが分かります。
たぶん、松ぼっくりはタネ以外はおいしくないはずで、それさえも手を出してしまうひもじさということでしょうか。
でも、たぶんここからは見えないけれども、クロマメノキ(黒豆木)を代表とするツツジ科の果実(液果)は大量に含まれていたでしょう。今が最盛期ですから。

そしてこれはクマがタネの散布者ということがよく分かる図です。
クマは噛んで咀嚼をくりかえして胃に落とすのではなく、ほとんどは丸呑みしてじっくりと消化しているようです。液果のものも含めて消化しないタネは糞として出されて移動する。
そうして山や森は、タネがクマのような散布者によって蒔かれ、豊かさを育んでいくのです。
登山道にクマの糞、怖くないかって?
特には感じないですね。
よく響く熊鈴を身につけてヒトのいるのを知らせているし、第一ここは森林限界、クマは隠れようがないので、今はぐっと標高を下げて行動しているはずです。ある調査によれば、クマは一日で35キロほども移動するそうです。
たとえこういう森林限界の場所に現れるとして、夕暮れや早朝に限られるでしょう。
下は、クロマメノキ(黒豆木/ツツジ科スノキ属)。和製ブルーベリーの代表格です。
3粒、4粒といただいたけど、いつもながらとてもおいしいです。
クロウスゴ(黒臼子/ツツジ科スノキ属)。
葉も実もオオバスノキ(大葉酢木)によく似ていて区別がむずかしいけれども、筆者は、実の先端のおおきく裂けているのがクロウスゴ、淡い五角形に見えるのがオオバスノキと思っていますが、どうでしょう。
これもとてもおいしい。
ガンコウラン(岩高蘭/ツツジ科ガンコウラン属)。
これは液果の典型、とてもジューシーでしかもおいしいです。
コケモモ(苔桃/ツツジ科スノキ属)。
今が旬の高山の果実の中でもこの味はピカイチ、絶品です。
ハイネズ(這杜松/ヒノキ科ビャクシン属)の実。
秋の西吾妻といえば、エゾオヤマリンドウ(蝦夷御山竜胆/リンドウ科リンドウ属)。

花屋に見られるのはリンドウは、エゾリンドウ(蝦夷竜胆)の園芸種です。
エゾリンドウは茎のところどころから花をつけるのに対して、エゾオヤマリンドウは頭頂部にかたまってついています。
頭頂部にかたまって花をつけるのはオヤマリンドウ(御山竜胆)の特徴ですが、大きさとしてはエゾリンドウよりは少し小さい。
この両方の特徴をあわせもったのがエゾオヤマリンドウです。
天元台のゲレンデコースにはおびただしい数のエゾオヤマリンドウが咲き誇りますが、もうシーズンも終盤のようです。 
と、白いエゾオヤマリンドウです。
実は、今回の登山(ハイキング)はこの花に合うのがひとつのめあてでした。
今年も咲いてくれました。うれしいです。

この白種はエゾオヤマリンドウの突然変異と思われますが、白種が自生するのは西吾妻では(筆者の確認した限りでは)縦走路に2箇所だけです。
栗駒国定公園内に位置する高松岳(秋田)ででも出会ったこともあります。
いずれにしても希少です。
 この白いリンドウをひとり愛でていると、ソロもふくめて20人ほどの集団が通りがかって話が弾みました。
この白いリンドウをひとり愛でていると、ソロもふくめて20人ほどの集団が通りがかって話が弾みました。
大方はボランティアの方々、小凹の先、高層湿原の弥兵衛平では登山道わきの裸地化が進んでいて、植生の回復作業を担っていらっしゃいます。
お疲れ様です。
通りがかりのひとの中に県のパトロールの腕章をつけた方がいたのですが、その方が言うには、
「どっかの町場のおっかあが数年前、折って取っていきやがった。戻ってみるとないんだ。がっかりしたものだ」と。
そう言われてみれば、最後に筆者が確認したのは3年前でしたが、今回の株はそれよりはぐっと小さくなっているという印象です。
根が掘り取られなかったのはこれ幸いです。まったくまったく、ひどいことをするものです。
下は22年の時のもの。
下は、西吾妻の東方、一切経山に至る縦走路と小凹。
白種のリンドウはこの眺望が得られる一画にあります。
紅葉しはじめていたクロマメノキ。
春に小さな花を咲かせる、常緑のミネズオウ(峰蘇芳/ツツジ科ミネズオウ属)。
シダ植物の範囲ながら、独特の姿のヒカゲノカズラ(日陰鬘/ヒカゲノカズラ科ヒカゲノカズラ属)。
コバイケイソウ(小梅蕙草/シュロソウ科シュロソウ属)の花後、果実が飛び散った後。
シラタマノキ(白玉木/ツツジ科シラタマノキ属)。
実を口に含むと甘さと同時にスースーします。メントールの香りです。
ハナヒリノキ(嚏木/ツツジ科イワナンテン属)の紅葉のはじまり。
色は黒紫にまで変化します。
チングルマ(稚児車/バラ科チングルマ属)の紅葉が進んできました。
クロマメノキ、ガンコウラン、コケモモ、ミネズオウ、シラタマノキ、そしてこのチングルマ…、草と見まごうこれら背丈の低い植物はいずれも小低木、樹木の仲間です。
そしていずれもが氷河期が去るまえに高山に逃げ込んだ氷河遺存種です。
こういう膨大な時間を有する植物に会うことができる幸いを感じます。
ネバリノギラン(粘芒蘭/キンコウカ科ソクシンラン属)の紅葉。
いつもながらこのオレンジのあざやかさ。
ミネザクラ(峰桜/バラ科サクラ属)の紅葉。
ミネザクラは最も高いところに自生するサクラです。
かの松尾芭蕉も6月の月山でサクラを愛でていたと思いますが(『おくのほそ道』)、それはきっとミネザクラですね。
ミネカエデ(峰楓/ムクロジ科カエデ属)の紅葉。
やがてこのミネカエデとコミネカエデ(小峰楓)が紅葉の主役になっていきます。
オオカメノキ(大亀木/ガマズミ科ガマズミ属)の紅葉。
山の紅葉に欠かすことのできない存在感があります。
登山道より西吾妻山方面。
吾妻連峰最高峰の西吾妻山はちょうどこの陰になっています。
カモシカ展望台からの帰り道、ご婦人ふたりから声をかけられました。
「あら、あなた、雪山であったひとよねえ」。
そういえば思い出しました。筆者より少しだけ年上に見えたアクティブなおふたり、筆者はスノーシューでハイキング中、ふたりはこれから山スキーで滑走というところだったと思います。中大巓の山頂でのこと。
お互いにサングラス姿、よく分かったものと思いますが、伸びた白いヒゲが頭に残っていたということですかねえ(笑い)。
おふたりは福島市にお住いのようだけど、天元台・西吾妻が気に入って、夏季冬季通しての年間パスポートを購入したのだとか。
夏場は登山、冬場は山スキー、年中アウトドア、これまたすごいね。
*
西吾妻のちょっと歩きはこの辺でおしまい。
来週には福島の浄土平から一切経山に登って魔女の瞳に会いに行きます。紅葉も楽しみ。
一切経山行きは、冬前の憩いのひと時となりましょうか。
10月半ばともなればこちらは冬の準備がはじまりますゆえ。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。