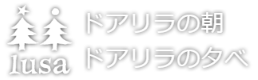本日は(2025年)9月15日、敬老の日です。
筆者は現在、町内会長とともに地区委員(行政委員)を兼ねているのですが、地区委員は同時に地区の福祉協議会の役員にもなっています。
福祉協議会の大きな仕事のひとつは敬老会の主催、おとといはその下準備の会場づくりや資料綴(と)じ、景品の仕分けを行ってきました。
昨日は、各戸を訪ねてお祝いを述べ、会への不参加者に景品の鯖(サバ)缶を手渡してきました。
なぜにサバ缶?
米沢でサバ缶は重宝する食材(山形県内陸部に共通しているよう)、春の山菜汁やたけのこ汁にサバ缶の投入は欠かせません。ひっぱりうどんやそうめんの具にも最適、缶詰そのものがおかずのひと品としても。
つまりサバ缶は味噌や醤油と同じくらいに大切な必需品なのです。我が家でも年中ストックしています。
県民のサバ缶愛はハンパではなく、たぶん、サバ缶消費量は全国1位だと思います。
よって敬老会の景品にもサバ缶一択なのです(笑い)。ただ、時節柄、これまでの3個が2個となって、ご老人の落胆やいかに(笑い)。
さて、本題です。
今回のsignalも前回に引き続き(本意にあらずも)、水がテーマ、題して「水、その後」です。
というのは、8月11日に濁(にご)りはじめて15日にようやく元の水になったのでしたが、9月10日にまたにごってきてしまったのです。今度はさらにひどいにごりよう、よって。
今後のためにもできるだけ考え、つきつめておかないと。
*
前回のsignalでは、この土地を形成する凝灰岩の巨大な一枚岩を通ってくる伏流水をイメージしました。
と同時に水のにごりには我が家から1.5キロ先のスギの大規模な伐採作業の影響も考えましたが、実際に現場に足を運んでみればそれはなさそうでした。
けれども、ここに住んで33年ではじめての水のにごりと、近くでのはじめての大規模な伐採作業、この時間的なかぶりに何か関連はないのか。
それから、梅雨の時期にしてはあまりの雨の少なさとカンカン照りの日々、そして水がにごった直前の土砂降りの雨は大いに関連がありそうです。事実、今回の2回目のにごりの直前の9月9日、10日にやはり一気の大雨が降っています。
以上が今回のsignalの前提と新たなさぐりの糸口です。
下は9月10日夜の、浴槽にためた水の、にごりはじめ。
その下が、比較対照のために、夜の水をそのままにして11日朝に撮影したもの。
右に映る円いものは底の水抜き栓です。これが透明度を測る指標に使えそうです。
11日朝にいったん水を抜いて改めてためた水、7時36分。
にごりは相当です。水抜き栓はこの時点で見えません。
よく見ると、水は単に濁っているだけでなく、泡のような浮遊物も確認できます。
12日8時26分。これがにごりのピークのよう。
前回のピークのものと比べて、この状態はさらにひどいものです。泥水といっても過言ではないような。
 12日16時50分。
12日16時50分。
にごりが引きはじめていることが分かります。水抜き栓が見えてきました。
13日7時36分。 ずいぶんと透明度は回復してきたけれど、この、油とも思えなくもない浮遊物は何だろう。
ずいぶんと透明度は回復してきたけれど、この、油とも思えなくもない浮遊物は何だろう。
どの家庭でも同じことですが、きれいな水は飲料に、料理用にといろいろなところに必要です。
そして、水がにごってからというもの、にごった水で洗わざるを得なかった食器類の最後の仕上げとして、きれいな水での濯(ゆす)ぎも必要になってきます。
前回からの経験でそれは、2リットルの湯を沸かして、きれいにした洗い桶に張って、約1リットルの水で割ってのゆすぎと湯くぐし…、そうして、我が家では1日に最低10リットルのきれいな水が必要ということがわかりました。
逆にいえば、きれいな水が10リットルあれば普段の暮らしは何とかできるということの証明です。
ただしこれは水が汚れた場合のことあって、断水なら比べようもない量の水を必要とするでしょう。
ゆすぎと湯くぐしをした食器類。
台所の入り口に備えた10リットルの水タンク。
このようなタンクは我が家には3つ備えてあります。元々は焚火の際の消火用のものがふたつ、それに家族でのキャンプに使っていたものがひとつです。
これらが今回、役に立っています。
きれいな水は(天王川の右岸に位置する)懇意にしている約1キロ先の栗園で、3日間ほど、ありがたく分けてもらいました。
*
今回着目したのは、約1.5キロ先の伐採現場ではなく、家のすぐ近くの貯木場(=土場。以下、土場)です。
現場で伐り出された木が1カ所に集められ、運び出しを待っています。
木材が崩れないよう、タテとヨコを交差しながらの両端の処理して積み上げる方法は見事。
我が家の薪積みはこの方法を応用しています。 
写真をクリックして拡大すると(サムネイル版表示によって左右が切れて映らない部分が見える)分かるのですが、土場は我が家のすぐ近く、すぐそば。
運搬の下請けの業者が朝の4時から積み込み作業をはじめた日には、まいりました。
それでこちらは睡眠を妨げられ、起きてしまいました。
このことについては、発注元の土地の所有者(市内町内会)の依頼先の「やまがた森林と緑の推進機構」(=機構。元の林業公社)に抗議しました。
水のにごりと、この土場の関係がどうもあやしい。
そして思い出しました。
我が家の伏流水は…、
方角的にはほぼ東から西に(道路に対して約20度の角度で)山の方からゆるく流れていると、主屋の施工にあたった工務店の社長が言っていたことを。1993年の夏のことです。
社長は約6メートル下の井戸の底を覗いて、何らかの浮遊物の移動があったことを認めたのでしょう。あるいは葉っぱでも落としてその動きを見たものか。
だとして、この伏流水の流れの上流方向に貯木場があります。井戸からちょうど50メートルです。
下は2005年当時の、花壇サークルをつくっていた時の写真。手前の円形が井戸。
そしてもうひとつ着目したのが、我が家のコンテナ小屋のことです。
このコンテナ(国鉄C20形コンテナ)は1995年ころに薪小屋用にと、当時の国鉄清算事業団から購入したものです(輸送代を含めてひとつ12万円ほどだったと記憶しています)。
ところが薪を入れておくと、室内の高温多湿ゆえに薪はすぐに更けてしまい使いものにならないのでした。大失敗でした。
ということで、不経済ながらもう1ケをさらに注文して、屋根をかけて物置小屋にしたのです。
この屋根掛けが筆者の大工仕事の本格的な第一歩、2001年のことでした。
こうすれば、中間の空間も利用できます。

基礎は独立基礎として、ひとつにつき基本ブロック6つを積んで、その上にコンクリート板を乗せる…、そのようにしてつくった基礎の上に、主屋の近くに置いてあったコンテナを(手配した)クレーンで吊って移動して設置したものです。大がかりな作業でした。
独立基礎に設置した国鉄コンテナ。
左の基礎に対して、右の基礎の上にはさらに2枚のコンクリート板が載っていますが、これはのちの作業です。
10年ほどして、コンテナが少しずつ傾いてきたことに気づきました。右側(南側。道路の反対側)が沈み込んできたのです。
水準器を当てれば今は水平を保っていますが、設置時よりも9センチ沈み込んでいました。
基礎の上にさらに2枚のコンクリート板が載っているのはそのためなのです(両コンテナを少しずつジャッキアップしてコンクリート板を差し込みました)。
コンテナひとつの重量(自重)が1.1トン。ふたつで2.2トン。
中のしまってある材料や荷物それに基礎を含めれば、総計2.5トンくらいの重量が掛かれば、10年ほどで徐々に9センチ沈み込んだということ。
これは、筆者自らが雑木林を開拓したここは軟弱な地盤(畑のような土壌)だという証明です。
と同じ地続きの地盤に土場があり、この巨大な材木の量です。
機構の職員に聴いたところによれば、ひと棚が10トントラック2台分、すなわち20トンとのこと。

ここに最大3棚が置かれた時には60トン、それに重機や運搬車などが入ればおよそ70~80トン。これが狭い面積にのっかればどうなるか?! ?! ?!
2.5トンのコンテナ小屋と、80トンの重量の貯木等との対照…。優に32倍! あまりのちがいです。
これが地盤を圧しつけ、伏流水の流れに影響を与えないという証明ができましょうか。関連を否定できましょうか。
80トンの重量がかかれば、当然ながら地盤は沈み込むでしょう。
この沈み込む場所は伏流水の流れの道すじに当たっている…、
急な大雨が降って伏流水として流れる水量が一気に増えた…、
その増えた流れに(流れの速度も増して)、圧しつけられて沈み込んだ地盤の底(空洞の天井)が触れて削られさらわれた…。
よって水が濁った。
筆者の推理はここまで。
たぶん、当たっていると思うなあ。
12日には機構の職員に濁った浴槽の様子を見てもらったし、さて機構ではどんな判断をするか、どんな対応をするものやら。それは今後大いに注目です。
この伐採作業はすでに終了、あとはわずか木の根っこ等の残材を運び出すだけとなりました。地盤が残材と機材のすべての重量から解放されるのもあと少しです。
そのあとに、そうしてしばらくしてまた一気の大雨が来て水が濁ったとすれば、筆者の推理は怪しくなりますが(笑い)。
と一旦は書いたけど、下の追記(18日)で分かるよう、地盤が重量から解放されたとて大量の伐根があったわけですから、また濁りは生じるかもしれない。
下は13日7時46分。
ほぼ元に戻っていますが、まだわずかながら濁りが確認できます。
そうして14日朝、ようやく元の透明な水に戻りました。7時58分の画像です。
今回も約5日間の水騒動、ヤレヤレです。
水の濁りはもう2度とごめんだけれど、でも、いい勉強をしましたよ。
・・・・・・
以下、追記。
このsignl「水、その後」は9月16日の午前中にアップしたのでしたが、アップしたあとに大きなことに気づいたのでつけ足します。
下は、18日の朝のこと。
この日早朝よりまたもや急な強い雨が降ってきて、また水が濁ったらかなわないと思って、タンクを総動員、別の場所に置いてある10リットルタンクを含めて、33リットルを備蓄しました。
いやなことだけど、3度目のにごりが来ても大丈夫なようにしました。
備えあれば憂いなし、です。
と、重大なことに気づいたというのは、貯木場の平坦地を確保するために、相当数(機構=「やまがた森林と緑の推進機構」の職員は80本と言っていたろうか)の樹木(多くはスギ、アカマツや一部広葉樹も含まれている)を伐採し、しかも地中に張った根をすべて引き抜いていたわけです。
そうすると、我が家の伏流水の濁りについては、(くりかえしもありますが)こんなふうにまとめることができると思います。
①我が家は33年ここに住んで、水が濁ったことはない(渇水は1度あった。2012年秋)…、
② 伐採と貯木、運搬の一連の作業は今年6月半ばから行われた…、
③ 作業現場(土場)は我が家の井戸からわずか50メートルの近さである…、
④ 作業現場は我が家の伏流水の流れの道すじに当たっている…、
⑤ 80本もの樹木を伐採し伐根したことによって、地盤を支えていた組成に大きな変化が生じ、軟弱な地盤はさらに軟弱に、いわばスポンジ状になった…、
⑥ そうした軟弱な地盤に、約3か月の長期にわたって、80トンもの重量を掛けた…、
⑦ 急な大雨が降って伏流水として流れる水量が一気に増えた…、
⑧ 雨が降って、スポンジ状になった地盤の、伐根のポイントポイントからも土中の成分が溶け出し、しみだした…、
⑨ 伏流水の増えた流れに(流れの速度も増して)、圧しつけられて沈み込んだ地盤の底(空洞の天井)が触れて削られ、さらわれた…。
よって水が濁った。
どうだろう。
この推理をくつがえして、水の濁りと作業場(土場)は関係なしと言えるだろうか。
以上が正しければ、あとは安全な生活を脅かされたことへの断り(いっさい何もないので)とその償いが残されますね。
およそ事業にはリスクはつきもの、ましてやすぐそばで暮らす者への配慮が最大限必要なのは当然のことです。
近くで暮らす者に、迷惑をかけたままにして知らん顔は通用しませんのでね。
・・・・・・
米沢の水瓶の水窪ダム(8月30日)の様子。
この時の貯水率は15パーセントでしたが、9月8日時点では13.4パーセントまで落ち込んでいます。今はもっと下がっているのでは。
山形県米沢に限っては、雨はまったく足らないのです。
この冬も夏場の反動で、大雪かなあ。
*
水をめぐる話はこのへんでおしまいです。第3弾とはならないことを願います。
水がなければ生きていけませんよね。水が当たり前にあることに安穏とせずに、ありがたく貴重なものということを思わされた8月と9月、これからも水を大切にしていきたいと思います。
そうそう、我が家をお訪ねの時は、おいしい伏流水でコーヒーを淹れてさしあげますよ。
そしてペットボトルでも持参され、どうぞ自慢の水をお持ち帰りください。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。