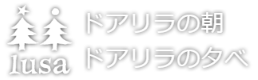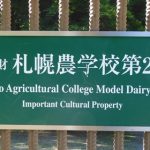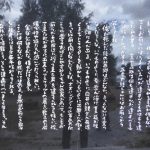本日は(2025年)8月7日です。
自分の今の生活が薪づくりなどの単調な暮らしに戻っているせいか、8月の日めくりには羽がついているよう、まったく日々の過ぎ去りが早いです。
さて、この夏の北海道旅行については、シリーズで3回をつづっておしまいとしました。
けれども出発した日からそろそろ1カ月も経とうというのに、まだまだ北海道の残像がいっぱい(笑い)。
振り切って次に進もうにも、どうもスッキリしないのです。
そこで今回のsignalは、そんなあれこれを番外篇としてつづって気持ちの整理です。おつきあいください。
題して「旅の余話」。
これで、ほんとうにおしまいにしたいです(笑い)。
*
まずは7月12日、同行のヨーコさんのリクエストで、前回(2016年)に続いて再訪した旭川近郊の上野ファームのこと。
散策路に何気なく置いてある、水に浮かべた花。
筆者は春先、水を張った大きな器に蕗の薹(とう)を浮かべるのですが(早春の彩りとしてうつくしい)、これはとびきり贅沢にして豪華。
大規模なフラワーガーデンならではのことです。
この木の葉はカナダの国旗の葉に似ていると思うけど、メイプル(サトウカエデ/砂糖楓)?
散歩道によい木陰をつくっていました。
上野ファームは2001年から自宅の庭園を開放してはじめたイングリッシュガーデン。
それにしてもオーナーの上野砂由紀さんのガーデンデザインの巧みさ、センスのよさ。

作業に当たっているスタッフに聴いたところ、広い園地(約2,000坪=東京ドーム約半分)に7名ほどで整備を担っているとのこと。
古くなりそうな花を摘んだり余計な枝を落としたり、枯れて落ちた葉を拾い集めたりと、見せるための工夫に余念がないという印象でした。

写真はひとをあえて避けているけど、本当はものすごい人出です。
中華系の言葉もずいぶんと飛び交い、少々喧噪の感もあります。
園地の一画、シラカバ(白樺)の林にて。
相棒に言わせれば、前回に比べたら雑草(自生の植物)が多くなって残念、とのこと。
筆者に言わせたら、オカトラノオ(丘虎尾)にせよ、オオウバユリ(大姥百合)にせよ、野にあるものを巧みに取り込んでいるふうでもあり。
*
北海道に渡った7月10日の夕方、札幌農学校第2農場に行きました。
札幌農学校第2農場は今回の渡道で最も楽しみにしていたひとつ、大都市札幌のど真ん中にありながら、牧歌的な牧場風景が広がる開放的な場所です。
これはどこかのガイドブックなどの情報ではなく、筆者自身のネット検索からの発掘です。
初代校長がかのウィリアム=スミス=クラーク(クラーク博士)、新渡戸稲造や内村鑑三といった日本の近代化に欠かせない泰斗(たいと)が輩出した札幌農学校…。
札幌農学校の農場は道内に第8まであったようです(ちなみに第8は富良野市)。第4農場までが札幌にありましたが、直営の第1第2以外は戦後の農地解放や売却によって現存していないということです。
ただし第3農場跡地は市民有志で「大学村の森」として公園として再生整備され、こちらもよい雰囲気のよう。
それにしても、日本の酪農の草創期を物語る巨大木造建物群のすばらしさ、うつくしさ。
100年以上前の時代にタイムスリップです。
広大な敷地には池が配され、設立当時からと思われるハルニレ(春楡)の巨木が建物群を取り囲んでいます。

何気に、心をからっぽにして、思い思いに歩く…、
札幌農学校第2農場とは、ただそれだけで気持ちが解放されていくようなところです。
この雰囲気はアルテピアッツァ美唄に似ています。とても静かです。
札幌農学校(現・北海道大学農学部)の創立が1876(明治9)年、これらの建物群は翌77年から造営されています。
レンガ造りの建物は精乳所(1911年)。
道内最古、全国でも最古の部類に属するレンガサイロ(緑飼貯蔵室)(1912年)。
下は、穀物庫(1911年)。
牧牛舎(1909年)。
仔牛と草を食む母牛はグラスファーバー?による造形物(笑い)。
風景にマッチしてますよね。
下は、模範家畜房(1877年)。

いやあ、想像にたがわぬすばらしい場所でした。
本当は敷地内の建物外観だけでなく内部も見学したかったのですが、訪問した時刻が公開の時間外であったため今回は叶いませんでした。
次回は内部をじっくりと見学し、施設の概要や当時の用具や道具について思いをはせたいと思います。
札幌農学校第2農場公開データ
屋外公開 通年 8:30~17:00
屋内公開(模範家畜房、穀物庫、牧牛舎) 4月29日~11月3日 10:00~16:00
休館 毎月第4月曜
入場料無料
大都会の真ん中にある第2農場のこと、駐車に戸惑ったらかなわないと思い、クルマは札幌の親戚(従兄)のM義さん宅に置かせてもらって、甘えて同行をお願いしたのでした。
M義さんは先のS一さんの一番下の弟に当たります。
この夜は M義さん宅にお世話になりました。
M義さんは筆者のひとつ上、過ごしてきた時代が同じなのです。
ほろ酔い加減になればギターを持ちだしてきて、楽譜も見ずに次から次へと弾くのはすべてたくろう(吉田拓郎)ナンバーです。
それに合わせて筆者も空で歌えるわけで…。
ふたりの青春(笑い)のかたわらで、口ずさんでいた奥様のS子さんと相棒のヨーコさん…。
4人の青春(笑い)がよみがえった夜とでも言っていいのか、よい時間でした。
*
富良野岳に登る前日の12日、旭川の友人夫妻に連れて行ってもらったのは、旭川東高校敷地にある宮澤賢治の詩碑です。
この詩碑は、旭川在住の賢治研究者である松田嗣敏さんを中心とした旭川宮沢賢治研究会の熱い思いの結晶として、2003年8月に「旭川東高校全日制百周年、定時制八十周年記念事業」として建立されたものです。
この詩と碑をめぐるご著書『宮澤賢治×(かける)旭川―心象スケッチ「旭川。」を読む』(未知谷2023)を松田さんご本人から頂戴していたご縁もあって、この機会にぜひお目にかかりたかったのですが、筆者には著書の理解がまだ十分ではなく(まだ半分しか読み進めておらず)、それは次回への持ち越しとしたのでした。
なまじ知っていて、思いのたけを表現したひとに、いい加減な気持ちでは会えない。
旭川。
植民地風のこんな小馬車に
朝はやくひとり乗ることのたのしさ
「農事試験場まで行って下さい。」
「六条の十三丁目だ。」
馬の鈴は鳴り馭者は口を鳴らす。
黒布はゆれるしまるで十月の風だ。
一列馬をひく騎馬従卒のむれ、
この偶然の馬はハックニー
たてがみは火のやうにゆれる。
馬車の震動のこころよさ
この黒布はすベり過ぎた。
もっと引かないといけない
こんな小さな敏渉な馬を
朝早くから私は町をかけさす
それは必ず無上菩提にいたる
六条にいま曲れば
おゝ落葉松 落葉松 それから青く顫えるポプルス
この辺に来て大へん立派にやってゐる
殖民地風の官舎の一ならびや旭川中学校
馬車の屋根は黄と赤の縞で
もうほんたうにジプシイらしく
こんな小馬車を
誰がほしくないと云はうか。
乗馬の人が二人来る
そらが冷たく白いのに
この人は白い歯をむいて笑ってゐる。
バビロン柳、おほばことつめくさ。
みんなつめたい朝の露にみちてゐる。
『春と修羅』補遺所収
賢治はこの詩「旭川。」を詩集(心象スケッチ)『春と修羅』には収録しなかったけれども、詩集の中の詩群「オホーツク挽歌」に含まれる一篇にちがいはありません。
最愛の妹のトシが病死し、長い焦燥を経て、きっとトシは北の方角へ行ったはずと思い込んで樺太への旅に出た、その旅の途中の旭川での感慨です。
詩は、旅中の「青森挽歌」や「津軽海峡」といった詩に表れる重々しさから解放されて、その先の旅に明るさをもたらすような、心の軽ささえも感じるような…。
賢治は、1923(大正12)年7月31日、樺太に向けて、東北本線青森行き花巻駅発14時28分に乗車しました。
以下の足取りは…、8月1日、青森発7時55分の青函連絡船に乗船、12時55分函館着。13時45分発網走・根室行き列車乗車、翌2日4時55分旭川着、市内周遊。宗谷線稚内行き列車11時54分に乗車、21時14分稚内着。
それから当時就航したての(就航開始は6月8日)(稚内―樺太・大泊間の)稚泊連絡船「対馬丸」に乗船して、3日7時30分大泊に着いた、という記録が残っています。
そうして賢治はこの旅を通してカタルシスを得て、立ち直っていったように筆者には思えるのです。
参考:『宮澤賢治 童話と〈挽歌〉〈疾中〉詩群への旅』宮澤哲夫著、蒼丘書林2016
*
富良野と来れば、とてもベタだけど、「北の国から」でしょう。
もう五郎さんも中畑木材の和夫さんもこの世にいないけど、ずっと筆者(たち)の心の中に住んでいるわけで。
今までにずいぶんとロケ地まわりをしたものだけど(笑い)、今回ははじめて、「2002遺言」で使われた「拾ってきた家」を訪ねました。
15日のことでした。
3人のスチール写真。
五郎の遺言。
すべてはシナリオの倉本聰の言葉だけれど、筆者にいまいち響かないのはことばのもてあそびが多いから?
言わんとすることは分かるんだけど。
「北の国から」というドラマは「2002遺言」のずっと前、「’87初恋」で終わっていたと思うな。
筆者とすれば、あの尾崎豊の「I LOVE YOU」が通奏低音のように響いた「’87初恋」が最高傑作です。
あとはシリアスな展開でも滑稽に思え、コミカルなところでもどうもちぐはぐな感じは否めず。それで次第に期待がしぼんでいって、それが番組の打ち切りにつながった理由と思っています。
純と結の家。
この瓶によるあかり取りは、筆者の家づくりでも構想にはあったもの。
このあとロケ地近くのラーメン屋に入って、麓郷を離れました。
上富良野のラベンダー畑。
美瑛の、風にそよぐ麦畑。
*
各地をめぐっていて、印象的だった植物をいくつか。
ミヤママタタビ(深山木天蓼/マタタビ科マタタビ属)。
もう10年も前のことになるだろうか、西吾妻スカイバレーを抜けて裏磐梯に行こうとしたところ、峠を越えたあたりで白化したいつもの葉ではなくピンク色のそれが目に入って、牧野もビックリの新発見かとざわついたのです(笑い)。
調べればそれはマタタビの高山型(でも希少でめずらしい)だったのですが、その別種のマタタビが富良野の一般道で普通にいくつも見られたのはショック(笑い)。
ガガイモ(蘿藦/キョウチクトウ科ガガイモ属)。これは上野ファームの丘の(未開墾の)東斜面にあったものです。
実はルーザの森でも一度見ているのですが、もう消滅したのか見当たりません。
宮澤賢治の童話「鹿踊りのはじまり」に、鹿たちの手ぬぐいの感触として「ごまざいの毛」が出てきますが、ごまざいはこのガガイモのことです。
セイヨウオニアザミ(西洋鬼薊/キク科アザミ属)。
富良野で、祝津の海岸で。こんなアザミをはじめて見ました。
セイヨウオニアザミは外来種で、1960年代に北海道ではじめて確認されたとのことです。
ミヤマウツボグサ(深山靫草/シソ科ウツボグサ属)。
キャンプをしたキトウシ(岐登牛)のテントサイトにあったもの。
あれ、こんな花も背丈も小さなウツボグサは見たことがない、きっと種がちがうと思って調べたら、やはり別種でした。
普段目にするウツボグサは背丈が40センチにもなるのにこちらはせいぜい15センチ程度。
*
ミヤマウツボグサつながりで、旭川の隣町の東川にあるキトウシの森。7月11日。
そこにキャンプ場があって、テントを張って一夜を過ごしました。

テントサイトは広大、清潔なトイレや炊事場が充実していて、クルマで走って2、3分のところには温泉施設もある…、そんな環境にあって利用料はひとり500円と格安です。
よいキャンプ場にめぐりあったものです。


筆者は登山の前後、ひとりのテントもだいぶあるけど、相棒にしたら子どもたちがまだ小学生だった頃に経験して以来のことのはず。
ふたり用テントも買ってあることだし、今回は8泊のうちせめて1泊はキャンプと思っていたのです。
経費の節約っていうのもあるけれど、野外で過ごす、テントで眠るっていうのもいいものであり。

筆者たちは林間のサイトにしましたが、芝生サイトには大勢のキャンパーがテントを張っていました。
まるで小屋のような大型のテントを持ち込み、まるで引っ越しのような大量の荷物を運んで…、たいへんだ!
こういう風景はわれわれにはちょっと、です。
筆者たちのテント(nature hike製)はコンパクト、重量は1,000グラム未満、設営は約5分くらいで完了です。
ふたりがギリギリ寝ることができる狭いスペースの、小型のものです。山中にも適応できます。
価格は2万円と少しぐらいの安価なものだけど、耐久性・耐水性十分でとても気に入っています。
夕食は簡単なもの。おにぎりと、じゃがバターを湯煎してあたため塩辛をのっけておかずに(笑い)。
これで十分、これがうまいんです。
それから、余市名産の、これはめずらしい鰊(にしん)とばを肴に、晩酌は赤ワインでカンパーイ!(笑い)
ちなみに朝は、パンに生野菜サラダにコーヒーでした。
こういう場所で飲むコーヒーのおいしさは格別です。
夕方に入浴に行きました。
行き先は、オープンしてまだ2年も経ってない東川町営の温泉施設「きとろん」。
入浴料は1,000円と高めだけど、とてもよい湯でした。
日が沈む方角は旭川の先、留萌でしょうか。
きとろんから見たうつくしい夕日です。
*
キトウシの森からそう遠くない「北の住まい設計社」を、筆者のリクエストで再訪したのは翌日12日のことです。
閉校した小学校を家具工房として活用する北の住まい設計社、ここでつくられる製品はいずれも秀逸です。
ショップには全国の手業の逸品の数々。
筆者は島根は出雲にある出西(しゅっさい)窯のコーナーが好きで、今回も見とれていました。
出西窯はかの柳宗理(そうり/本名はむねみち)がディレクションした歴史を持ちます。
実は宗理は1962年にはじめて出西窯を訪れていますが、目的は前年に亡くなった父(民藝運動の指導者の)宗悦(むねよし)の骨壺の製作依頼だったとか。
筆者自身、ものづくりにおいてこのビッグなふたりの影響はやはり大きいのです。
併設されているカフェにて。
1,800円と値は張ったけど、とてもおいしかったパスタ。
名はイカとホタテの夏野菜ペペロンチーノだったか?
ここに冷製コーンスープと焼きたてのパンが添えられていました。冷製コーンスープは再現できそうだけど、この味の奥深さはどうすれば出せるんだろう。
パスタもスープもパンも、実に滋味深い味でした。
15日、麓郷は「富良野とみ川」で食べた石臼挽き中華そば。
行き当たりばったりで入った店にしてはおいしかったです。
壁に目を移せば、ここにも倉本聰の言葉が…(笑い)。
「富川のラーメンは働いたものへの天の馳走である」、天の馳走ねえ(笑い)。
北海道最後の16日は、親戚に強くすすめられるままに、石狩の「らーめん信玄」に行きました。
土砂降りの雨の中というのに(渡道以来、この日はじめて雨が降った)、平日に関わらず、開店の11時にはすごい行列でした。
おすすめの一番人気の「信州(コク味噌)」をふたりして注文、クリーミーで味わい深い味噌に黄いろなちぢれ麺がからんでとてもおいしかったです。
石狩の信玄って、北海道民のラーメンの聖地のようであり(笑い)。
「旅の余話」はこのへんでおしまいにします。
*
ここ2、3日、たくさんの雨が降ったけど、最上川の源流のひとつ天王川=笊籬溪の水量は回復せず、谷底をわずかな水が這っている程度、まったく不十分です。
降った雨は乾いた土にどんどんと吸収されるのが精いっぱいの様子、まだまだ雨は足らないです。
雨がほしい、もっともっと、ほしいです。
と、鹿児島では線状降水帯が発生して大雨となり、災害につながっているよう、うまくいかないものです。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。