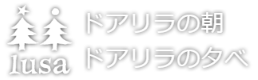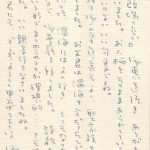本日は(2025年)7月27日、ものすごい暑さです。
昨日などは(山形県)米沢では気象観測史上最高の気温38.4度を記録したのだとか。それは膚感覚とも一致していて、いやはやなんともです。
ここの標高は町場よりも120メートルほどは高い(352メートル)し、すぐわきを溪谷が走り、森の中でもあるので多少の手加減はあると思うけどそれにしてもです。
暑さを乗り切る筆者の工夫のひとつは就寝前のシャワーと寝床づくり。
寝床はキャンプマットの上に1畳ほどの茣蓙(ござ)を敷くのみ、枕は固形保冷剤を凍らせたものふたつを2枚のバスタオルで包んだもの、そして掛けるタオルケットの中には(枕と同じようにしてつくった)湯たんぽならぬ「氷たんぽ」を入れておく(笑い)。
これは安眠を約束します。このアイデアは我ながら特許申請したいほどにすばらしいと思う(笑い)。安眠こそが、まずは暑さを乗り切る第一歩です。
何より、安上がりなのがいいです(笑い)。
さてこの夏、7月半ばに、(2016年以来)ひさしぶりに北海道に渡って1週間ほど滞在したことはすでにお知らせの通り。
signalはその思い出の書きとめのひとつ、今回はその2として海の景色、題して「ブルー、シャコタンブルー」です。
*
太平洋からも日本海からも同じくらいに遠い山形県南の米沢を含む置賜(おいたま、おきたま)地方、普段は四方に山しか見えない土地柄で、そういう中で育った筆者にとって海は幼い頃からのあこがれでした。
置賜のひとは誰彼みんなそうかもしれない。
磯の香り、干し網、小さな港に停泊する漁船…、
軒先の漁具、日干しのスルメイカ、ひしめき合う民家、狭い路地…、
夏の海の家、砂浜、磯浜、そして広い海、青い海…。
父親が今は鶴岡分になっている温海(あつみ)の山五十川(やまいらがわ)出身であるゆえ、数年に一度、幼い頃から連れられて実家に行っていたものです。
実家から海までは約4キロ、楽しみは従兄たちと行く海水浴でした。
三瀬や小波渡(こばと)、由良や鼠ヶ関(ねずがせき)の海…、なつかしいです。
下のハガキは、1989年4月に、今は亡き茨木のり子から頂戴していたもの。
この年に筆者は私家版にて父親の川柳集を出版し、読んでほしくてのり子さんに送っていたのですが、ハガキはそれへのごていねいな返信でした。
この時でしたかね、詩人茨木のり子は庄内地方と縁を結んでいることを知ったのは。
来年2026年は茨木のり子生誕100周年、鶴岡には顕彰の会ともいうべき「茨木のり子 六月の会」というものがあって、生誕100周年を大きなイヴェントとすべく着々と準備を進めているようです。
茨木のり子と来て、海と来れば、言わずと知れた初期の代表作「根府川の海」でしょう。
所収は第一詩集『対話』(不知火社1955)。
根府川
東海道の小駅
赤いカンナの咲いている駅
たっぷり栄養のある
大きな花の向うに
いつもまっさおな海がひろがっていた
中尉との恋の話をきかされながら
友と二人ここを通ったことがあった
溢れるような青春を
リュックにつめこみ
動員令をポケットに
ゆられていったこともある
燃えさかる東京をあとに
ネーブルの花の白かったふるさとへ
たどりつくときも
あなたは在った
丈高いカンナの花よ
おだやかな相模の海よ
沖に光る波のひとひら
ああそんなかがやきに似た
十代の歳月
風船のように消えた
無知で純粋で徒労だった歳月
うしなわれたたった一つの海賊箱
ほっそりと
蒼く
国を抱きしめて
眉をあげていた
菜ッパ服時代の小さいあたしを
根府川の海よ
忘れはしないだろう?
女の年輪をましながら
ふたたび私は通過する
あれから八年
ひたすらに不敵なこころを育て
海よ
あなたのように
あらぬ方を眺めながら……。
のり子の敗戦は二十歳、戦争で塗り固められた時間とともにあった青春、それを見ていた海、相模のまっさおな海、根府川の海。
詩は、戦争が終わって、日本人みなが欠如していた精神の自立と時代への凛とした意志を愛しい根府川の海に誓ったということでしょう。詩人の出発でもあるような、瑞々しい感性です。
そして今日も、海に今の自分を映すひともいるだろうこと。
*
筆者と相棒がクルマごとフェリーに乗り込んだのは7月9日のこと、新潟は山の下埠頭、正午発の新日本海フェリーでした。
北海道にフェリーで渡るには仙台―苫小牧航路もあるけど、筆者はほとんど新潟―小樽航路を選択しています。
港町の小樽の風情が好きなのと、時おり見える島影もいいのです。
はるかな甘い匂いのする「デルス・ウザーラ」の世界・沿海州に思いをはせることもできるし、日本海は夕日もいいですし。
フェリー利用のこれまでというのはずっと、だだっ広い大広間での雑魚寝、そんな最低ランクの乗船だったけど、そういうのはいつの間になくなっていたのでした。時代ですかね。
今は最低でもプライベートに配慮した個室なのにはびっくり、カプセルホテルに毛が生えたようなところでも筆者たちには極楽でした(笑い)。
沈みゆく夕日。
豪華なフェリーで、夕日を見ながらの豪華な晩餐!(笑い)
おいしかったなあ!(笑い)
*
小樽に着いたのは朝の4時半。
この日の午前中の予定は余市のニッカウヰスキー工場の見学だったのですが(ここで触れておけば、ニッカウヰスキー余市工場の見学はよくなかった。立地は宮城峡のように山懐にあるわけでないので風情に乏しく、予約のツアーならまだしも飛び込みゆえに見学場所は極端に制限された)、開場までの時間はたくさん、それでまずは朝の静かな運河を歩きました。
筆者は運河がまだ手つかずのドブ川だった頃の様子も知っており、その頃(1975年)は運河をすべて埋め立てて道路を大幅に拡幅するか、それとも全体を保存に努めるか、開発と保全の議論が町中をざわめかせていた時代でした。
結局、両方のいいとこ取りをして(運河の幅半分を埋め立てて道路を拡幅し、半分は運河として残すという)現在の形になったのです。1986年のことです。これでよかったのだと思います。
朝のひんやりとした空気の中の、筆者と相棒以外は誰もいない静かな運河、この早朝の散策はいいです。
昼ともなればここは、観光客でごった返すはず。
下は筆者の学生時分の、埋め立て前の小樽運河。拙い絵です。
小樽の町はずいぶんとシリーズで描きました。
嗚呼、なつかしきかなです。
余市に向かう途中の、大川海岸にて。
海を目の前にしての、簡単な朝食とコーヒータイム。
そうして空白の時間を埋めるべく向かった先は、積丹(しゃこたん)の島武意(しまむい)海岸でした。
学生時代に訪れているはずの積丹ですが、この海の、どこまでも透き通る青にはあらためて驚きさえ覚えました。
海は快晴の空を映しているとはいえ、まったく言葉がないほどの青い色、ブルー、
シャコタンブルーその名の通りでした。
おお、ブルー、シャコタンブルー!
島武意海岸から離れて遊歩道を灯台まで歩いたのですが、そこに見つけたのはカシワ(柏)の天然林でした。感激しました。
というのは、宮澤賢治に「かしはばやしの夜」という物語があるのですが、その舞台と思しき小岩井農場周辺にはもはやカシワの林は消滅してしまっています。
土地の地味がよくなり、肥沃になってきたからでしょうか、がっかりしていたのです。
現在は海岸のやせ地に自生のものがあると聞き及んではいましたが、それを積丹の地で見つけたのです。うれしかったです。
なるほど、この木の幹のクネクネは夜ともなれば踊るようで動くようでおしゃべりするようで、森のワイワイガヤガヤがはじまるわけだ。
カシワの林は賢治を大いに刺激したのでしょう。
おお、ブルー、シャコタンブルー!
島武意海岸から遊歩道を歩いて20分ほどのところにある、積丹出岬(でみさき)灯台。
今では全国どこの灯台にも灯台守はいないけど(灯台守は2006年に全面廃止。世の中の流れとはいえ、さびしいことです)、船に沿岸部の情報を提供して安全な航行をサポートする役目は今も変わることはありません。
灯台のある風景が好きです。
 続いて向かった先は、積丹半島は神威(かむい)岬。
続いて向かった先は、積丹半島は神威(かむい)岬。
駐車場のある場所から先端までは約800メートルあり、アップダウンのある遊歩道が続いています。
この岬の海の、何たるうつくしい青であることか。

神威岬は筆者にとっても初めての場所ということもあるけれども、この海の青さには驚きを禁じ得ませんでした。
気持ちがスーッと吸い込まれていくような青、
揺れ動く魂が沈潜していくような青、
そして、混じり気のあるものをかたくなに拒むような清浄の青なのです。

エゾニュウにもハナウドにも似ているけど、これはアマニュウ(甘ニュウ)でしょうか。
神威岬灯台。

慣れたもので、カモメ(オオセグロカモメ/大背黒鴎)はポーズを取りっぱなし(笑い)。
カモメとウミネコのちがいをあまり考えたことがなかったけれど、まずはくちばしの先端に赤と黒の斑紋のあるのがウミネコとのこと。
おお、ブルー、シャコタンブルー!
次は北海道を離れる日に訪れた祝津(しゅくつ)の海です。小樽水族館のあるあたり。
ちょうど鰊御殿(にしんごてん)のすぐ上にある日和山灯台。
今まで見てきた…、
北海道は襟裳の海、知床羅臼の海、礼文は船泊の海、桃岩の海、澄海岬の海、そして天売・焼尻(てうりやぎしり)の海…、やはり北海道が多いなあ。
それから南は土佐の桂浜の海、小豆島の海、屋久島は永田浜の海…、
そして佐渡の二つ亀の海、外海府の海、小木の海…、
一番身近な庄内の海、それから何より好きな新潟は山北(さんぽく)の笹川流れの海…。
笹川流れの海のうつくしさは積丹の海とは異なります。あえていえば、ガラスのような透明な海、青にソーダガラスが溶け込んだようなうつくしさなのです。
旅に重なって、思い出の海はいっぱいだ。
そしてここにひとつ加わるのが祝津を含む積丹の、青い青い海なのは言うに及ばないことです。
*
帰りのフェリーにて。
海は空の表情を刻々と映して変化し、
海は少しずつ暗がりを覚えつつ、
7月16日の夜の海の上、風に吹かれてポーズをとるひともいたのです(笑い)。
それじゃあ、次のsignalでまた。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。