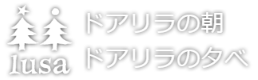本日は(2025年)7月に入った5日、いやあ、暑いですね。
6月の平均気温が(1946年の統計開始以来)史上最高だったというのはとてもうなずけること、6月にしてもう真夏という感じでしたからね。
ここ米沢のルーザの森のホンマ家にはまだ文明は届いていず(笑い)、クーラーというものがありません。
日中のほとんどを在宅している筆者は暑さをどう乗り切っているのかと言えば…、
保温のきく水筒に氷を詰めて濃くつくった麦茶をたっぷりと、
外仕事では吸湿速乾冷感素材の肌着をつけ膚を露出しない(道路工事の作業員は膚を出して作業をしていませんよね、同じことです。膚を日光にさらすと疲れがいや増すのです)、
工房やヒュッテでは扇風機をブンブン唸らせる、
たまらなくなると浴槽に適度な温度の水を張って身体を冷やす、
デスクワークの場合は凍らせた保冷剤をタオルに包んで足のひらを乗せる(足湯と逆の効果ですね)…、それくらいかなあ。
あとは忍耐と根性、これが一番かもしれない(笑い)。
なぜに我慢するのかと不審の向きもあろうかと思いますが、筆者は3.11以来のコンセントの向こうの風景を見てしまったから。多くの者を不幸にしたそのことを忘れたくない、という個人的な思い込みがあるのです。
デンキそのものを否定するものではないけれども、我慢できるところは我慢するということです。
まあ、それはともかく。
さて今回のsignalのテーマは梅雨の風物詩のひとつ、栗とその花について、題して「栗のこと、その花のこと」です。
*
「栗花落」という名字のあるのを新聞で知ったのはもう20年も前のことだったろうか。これで「ついり」「つゆり」または「つゆ」と読むのだとか。
その意味はたぶん、「栗の花が落ちると梅雨入り」ということで「つゆいり」から「つゆり」、「ついり」に転訛したものでしょう。
この名字のひとは兵庫に20人、大阪、奈良、香川、島根に10人ずついるとのことです。
季節の風物詩を名字にするなんて日本の美意識にかなって素敵なことだと思います。
ちなみにですが、その時にいっしょに印象的だったのは「小鳥遊」という名字、これで「たかなし」なのだとか。
「たかなし」は「鷹無し」、「鷹がいないと小鳥が遊ぶ」、だから(笑い)。
こういうのもいいなあ。
水戸の栗の開花日の統計があって、それと関東甲信越の梅雨入りの時期を照らし合わせてみると…、2014年から7年間の栗の平均開花日が5月31日前後、平均の梅雨入り時期が6月7日あたり、栗の開花日と梅雨入りの日の差の平均は7.1日だったよう。
栗の花が咲いて、落ちはじめるまで1週間から10日ほどと考えるとよい感じです。
梅雨入り日を知るための指標として、栗の花は理にかなっているようです。
なお、栗の収穫量の都道府県別ベスト3(2021年農林水産省統計)は、茨城、熊本、愛媛だそうで。その中でも3,800トンの茨城は抜きんでているようです。
(※以上は、「名字由来net」、「暦のページ」、「minorasu」を参考としました)。
*
さて。
相棒のヨーコさんが言うのです。
「(今、)窓からは栗の花がいっぱい。あの細長い花からイガイガの栗ができるのは不思議。どうやってできるんだろう」。

そう言われて筆者は、あの太いひものようなものはいわゆる雄花序(ゆうかじょ)で、雌花(めばな)は目立たずについているはずと予想はしたけれども、自分もその雌花を確かめたことはなく、したがってどのようにして栗の実ができていくのかイメージはわかなかったのです。よって彼女の疑問は自分の疑問にもなりました。
幼少の頃から野山でなじんできたクリ(以下、表記はクリとします)ながら、今までひも様の花とあのイガの中の実しか知らなかったなんて。
もう古希も近いというのに、まったくです(笑い)。
それにしても(少し前には)クリの花はどこも満開で、山肌を見ればどこにクリ(山野の自生種=シバグリ/芝栗、ヤマグリ/山栗)の木があるのか一目瞭然でした。
近くの栗園は花が咲いたがために木はまるで地底から盛り上がるよう、体積が5割増しにでもなったかのようです。
そして当然にして森は、独特な匂いでプンプンです。
あの、タケノコの皮をむいたような、あるいはヒトの精液のような、生臭く青臭い匂いがむせかえるほどに充満しています。
それはまさしく、蒸し暑い梅雨を象徴する匂いです。
ということで、まずはこの目で見ることが大事。
現場に近寄って見て確かめ、野生のクリの枝を折ってリビングの花瓶に差して観察することにしました。

そうして、クリの雌花をはじめて見つけました。
クリの赤ちゃんだ! これがイガイガになるんだ!
雌花の先の白くツンツンしているのはめしべの花柱(かちゅう)、ここに雄花からつくられる花粉がくっつくのだな。
雌花は分かった。
雌花の先に花穂がついていて、それも分かった。
この花穂を帯雌花穂(たいめばなほ)と言うようですが、それは花粉をつくる雄花穂(おばなほ)でしょう。
でも、雌花のつかない方にはまたちがった、よりフサフサの形状の花穂がついているけど、これは何?
これも花粉をつくる雄花穂にちがいはないけど、それならなぜに2種あるのか???
下の写真は2種の花穂のちがいが分かりやすいです。
上にあるフサフサの穂が雄花穂(おばなほ)、クリの実の原形よろしく雌花がついている穂は帯雌花穂(たいめばなほ)です。

この、ともに雄花の2種の花穂の(存在の)理由が分かりません。
茶色くなって枯れて落ち始めているのは、雌花がついていない方の花穂です。
雌花がついていた方の花穂もいつの間に消えています。けれども枯れて落ちるのは雄花穂よりずっとあとです。
よくよく見てみると、落ちたばかりの花穂の軸跡が見て取れます。
そうしてなぜ2種の雄花穂があるのかを自分なりに考えてみるに、気づくのはこの2種の花の咲く時期がちがうということです。
まず雄花穂が咲いて、雌花が咲いて、つづいて帯雌花穂が咲く…、雄花穂が散って、雌花(子房)が大きくなって、つづいて帯雌花穂が散ってゆく…、この時間差2段攻撃(笑い)に特別な意味があるような。これはより確実な受粉をするための2段構えということなのかどうか。
花粉は水分に弱く、雨が降ると死んでしまうそうで、開花の時間差はそうしたことからの防御策と考えられないこともないのかもしれません。
筆者の調べと推測は、今回はここまで。
それにしてもクリは神秘的です。
散り落ちた花穂。
ここで、これまでひとに聴いたり、図鑑やインターネットで知り得たことを簡単に記してみます。
クリ(栗)はブナ科クリ属。
クリには雄花だけから成る雄花穂(おばなほ)と、雄花と雌花のつく帯雌花穂(たいめばなほ)というものがあり、雌花は雄花がつくる花粉を受粉してクリの実になります。
ある栗園主によれば、雄花穂だけがたくさん咲いても収量は少なく、帯雌花穂がよく咲くと豊作になるそうです。
花粉は70~80%ほどは風で運ばれますが(風媒花)、あとはハチなどの虫でも運ばれて結実するよう(虫媒花でもある)。
あの独特な匂いはハチなどの虫を集めるための計算された仕かけのようです。
雌花には3個の子房があり、緑色の鱗片でおおわれた総苞(そうほう)に包まれています。総苞は後にイガになるところです。
子房の先端より伸びた花柱が、総苞の外へ飛び出ています。
3個の子房のうち受粉した数だけ実が成るとのこと。ひとつのイガには普通3個の実が入っているけれども、そういえば2個のものも時に1個のもありますね。
栗園のクリは「自家不結実性」と言って、同じ品種の受粉ではほとんど実を結ばず、近くに異なる品種の栗がないと実は収穫できないとのこと。
これについて筆者の近くの栗園のオーナーに話を聴いたところ、園地ではやはり早生と晩生を両方植えているということです。
栗園のクリは「自家不結実性」があるとして、では野生のクリはどうなんだろう。種にちがいがあるとは思えないのだけれど。
ちなみに栽培もののクリは桜のかのソメイヨシノと同様のクローン100パーセント、したがって病気に弱いのだそうです。「自家不結実性」とはこのことと関係しているのかもしれません。
以上、参考は小田喜商店(茨城)、松尾栗園(能登)のホームページなど。
そして、雄花穂がほとんどが落ちた現在の様子。
子房がずいぶんとふくらんできました。
こうして少しずつ成長していきます。
*
そして秋。
これは数年前の、9月1日の画像。

10月に入ると、栗の実が出来上がってきます。
我が家はとても懇意にしている栗園から毎年たくさんのクリのおすそ分けがあります。
茹で栗にしても栗ご飯にしてもとても食べきれるものではなく、あとは冷凍保存して、ときに季節を問わずに栗ご飯としていただきます。

クリの実を待っているのは何もひとだけではありません。
筆者は森に住んでいるので実感としてよく分かるけれども、クリの実を心待ちにしているのは…、
リス(栗鼠)、ネズミ(鼠)、サル(猿)、タヌキ(狸)、アナグマ(穴熊)、カラス(烏)そしてツキノワグマ(月輪熊)です。
クリは森の大いなる恵み、多くの命を支えているのです。

クリはひとの食材としてはもちろん重要だけれど、木材としてのクリは水にも腐敗にも強いし、広葉樹にしては歪み(狂い)が少なく、加工がしやすく、すばらしい建築材であり造作材です。
我が家の冬の暖房を支える薪の大方は栗園のご厚意、弱ってしまった木を筆者が伐採して薪にしているものです。
クリは堅くもなくやわらかくもなく、薪割りの斧を振るえば、気持ちのいいほどにスパンと割れてくれます。
筆者はこれまでいろんな樹種の薪をつくってきたけど、薪としても上級材であることは確かです。
クリはとても有用、クリ様々なのです。
今年のクリの実は今までとはちがって見えてくることでしょう。
*
そうして季節は巡っていきます。
もう少しすると梅雨も明けるでしょう。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をクリックすると写真が順次移りかわります。