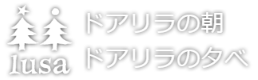本日は(2025年)4月20日、町場のソメイヨシノはあすあさってあたりが満開というところでした。
筆者の幼い頃は5月の連休が満開と決まっていたものでしたが、ここ60年、時代とともにずいぶんと早まったものです。
近くの笊籬溪(ざるだに)はご覧の通り、雪解け水を集めて轟轟と鳴っています。もはや春の景色です。
今回のsignalは、そんな春がやってきているけれども、筆者は春と冬を行きつ戻りつ。前回の3月27日に引き続いての雪山の記録、題して「雪山、もう一丁」です。
*
筆者の山登りの基本は春から秋の無雪期、高山植物の移りかわりを愛でながらの山歩きを楽しんでいます。
けれども雪の下に長い時間じっと耐えている植物を雪の現地で想像するのもいいもの、そういう時期の山の様子を膚で感じてみたいなあと思っていたものです。
ということで、この冬に、天元台高原が発行する「天元台サポートクラブ 冬山シーズン券」を購入したのです。料金は5,500円でした。
通常はロープウェイとリフト利用の1日分パスポートが5,500円で、この券なら2日(回)分のパスポートが手に入り、3回目以降は半額で利用できるというもの、非常に格安です。ただし米沢市民または職場が米沢市にあることが条件ですが。
で、今回は、前回の西吾妻山方面とは逆の、福島の一切経山に連なる縦走路方面を歩きたいと思いました。
本当はすばらしい天気が予想された前日の17日をねらって運行の様子をうかがっていたのでしたが、風強く、早々にも「終日運休」と決まったのでした。それで17日と18日のやるべきことを総入れ替えし、18日朝に「通常運行」を確認して天元台に急いだのです。
と、同じように考えるひとはあまた、駐車場はすでに満車、地元山形に加え、新潟、福島、宮城ナンバーの車が目立ちました。
リフトのスタート地点。
みんなが並んでいて、何で動かないんだろうと思えば、3基のリフトの着地点に雪が足らず(スキーとスノーボードの客がリフトから下りることができず)、人海戦術で雪を運んでの準備中と言うのです。
まわりは多すぎるほどの雪だというのに、スキー場を経営するというのはなかなかたいへんなことです。 
ともあれ、ずいぶんの無駄な時間を食ったけど、なんとかリフトトップへ。
リフトトップの北望台(1,810メートル)から、筆者のように山に登ろうとするひとは第一便で6名、3名が山スキー、自分も含めて3名がスノーシュー組でした。
スノーシュー組の他のふたりの男女は父親と娘という年恰好(親子ではないのかもしれない)、60代後半と40代はじめぐらい。
「どちらから(おいでですか)」と聴けば、「台湾からです」とのこと。これから西吾妻山山頂をめざすのだそうです。
台湾からの客にしてはずいぶん雪山に慣れているふう、身に着けているものはスイスのマムート(Mammut)製だし、スノーシューはいずれもアメリカのMSR。おまけにピッケルも備えている。
筆者などは憧れはしてもとても手が出ない価格帯のものばかりでした。
山スキーのソロの青年は、(山形)県のみどり自然課の職員とのこと。
「遊んでいるように見えるでしょうが、これも仕事の一環です。オオシラビソの先枯れが吾妻にも現れ出していて、その調査。(雪がまだたっぷりとあり、しかも雪が消えかけて樹木の頭が見える)この時期にしか行けないのです」ということでした。この調査が大切なことが分かります。
蔵王は今オオシラビソ(大白檜曽)の枯死がひどくまるで死の山と化し、山としての魅力を急減させているのです。
彼は、上り斜面も滑らずに歩けるよう、スキンシールをスキー板に手際よく貼ってスタスタと先に行きました。
前回は先に歩いたひとの踏み跡をたどったので靴にアイゼンをつけただけで十分でしたが、今回まず目指すは普段は誰も行かない中大巓(なかだいてん)、とにかく道なき道をピークをめざして歩くことに。
こうなるとやはりアイゼンでは用をなさず、スノーシューの出番となりました。2日前に積雪があったようだし。
少しずつ標高を稼げば、オオシラビソの背丈が矮小化し、やはりところどころ枯れている個体も確認でき…、
しまい、中大巓のピーク(1,963メートル)ではほぼ森林限界でした。
中大巓山頂から見た大いなる飯豊連峰の山塊。
山頂より見た、ほぼ南に位置する西吾妻山方面。
右にポコンとコブのように頭を出すのは西大巓(1,982メートル)です。
あの西大巓に行けば、裏磐梯がパノラマです。
この中大巓というのは、夏場には行けない山です。なぜなら登山道がないから。
縦横無尽に歩けるこの時期であればこそのピークなのです。
筆者にとってははじめてのピークです。
中大巓から、ほぼ東に連なる一切経山につづく縦走路方面。
西吾妻の景勝地のひとつ人形石を抜けて、縦走路がよく見渡せるところまで。
ここは夏場なら小凹(こくぼ)という池塘が点在するビューポイント。
夏場に見覚えのあるケルンに出ました。登山道のしるしです。このあたり一帯からハクサンシャクナゲ(白山石楠花)の群生地となります。
わずかにハイマツ(這松)が見え出しています。
下は、夏場のハイマツ。

ハイマツは氷河時代の生き残りで、地球が温暖化に向かう中で高山に逃げ込んだ植物のひとつと言われています。いわゆる氷河遺存種です。
ハイマツにはホシガラス(星烏)という相棒がいます。
ホシガラスはまだ青いハイマツの松ぼっくりをむしり取って、よく木道の上で食い散らかしているのに遭遇することがあります。そうしてその食い散らかしが種の散布につながるのだとか。
ホシガラスも氷河時代の生き残りと言われ、気の遠くなるほどにずっと、友好な関係を続けてきたのだと思います。
こういうことを思うと、クラクラとしてきます。
ホシガラス。

弥兵衛平につづく道。
手前の小山の藤十郎(1,860メートル)を越えれば、東日本では尾瀬に次ぐ面積を持つ高層湿原の弥兵衛平につながっていきます。
弥兵衛平からさらに伸びる縦走路。
東大巓、昭元山、烏帽子山、家形山、そして一切経山へと連なっています。
岩海として名のある人形石(1,950メートル)にて。
深い雪の中、巨岩だけがその一部を出しています。
人形石より見る、たおやかな中大巓。
夏場、ここは高山植物の宝庫です。
コケモモ(苔桃)もガンコウラン(岩高蘭)もクロマメノキ(黒豆木)もミネズオウ(峰蘇芳)もみんなみんな、春と夏の甘い夢を見ているんだろうな。
下は、夏場のクロマメノキ(ツツジ科スノキ属)。
見ての通り、和製ブルーベリー。おいしいのです。

中大巓のピークに戻れば、歩きはじめのときに会ったご婦人ふたりが、スキーから歩行用のシールを外していざ滑走というところでした。
これからの滑走がワクワクするのか、ふたりともとてもうれしそうでした。
やはりゲレンデスキーとはちがう圧倒的な自然の中の滑走はたまらない魅力なのでしょう。
飯豊連峰を正面に見ながらの下山です。
今年の異様なほどの雪を物語るよう、ダケカンバ(岳樺)の太い幹が裂けてみじめな姿をさらしていました。
リフトトップからの眺め。
冬季のロープウェイとリフトの運行は5月6日までとのことなので、あと1回くらい行けるかどうか。
公私にわたってめちゃくちゃな忙しさの中で、そんな時間がつくれるのかなあ。
*
雪が解けてきたので、昨秋にけっこうな時間をかけてつくった薪小屋の雪囲い用の覆い板(壁)を外しました。
4月6日のことでした。
薪小屋の覆い板を収納するための枠棚をこしらえました。
3日ほどかけて木取りをして組み立てて、9日に完成したものです。
この枠棚の底にはキャスターも付けたので、これで移動自由でコンパクトな収納が可能となりました。
雪が解けてきたので、除雪の支障になったり家屋や小屋にかかったりする木を少しずつ伐っていたのですが、枝分かれの部分を利用して、ワイルドな掛けフックをつくりました。
小刀を砥石で研いで切れ味を鋭くし、木の皮を欠き削いでゆく作業のうれしいこと楽しいこと。
やはり自分は手作業がとても好きだし、ひとはこういうときに充足感を得るのだなあとひとり納得した時間でもありました。
このフックは懇意にしている骨董屋のオヤジが教えてくれたものです。
朝食の最中、リビングから見える林にカモシカ(羚羊)がひょっこり現れました。
相棒とふたりして姿勢を正して見入りました。いつ見てもかっこいいなあ、カモシカは。
けれども、胸のあたりに血がついているし、左の角が欠けているし、どうしたろう。
角はオスとメスともにあってこれだけでどちらなのかは分からないけれども、メスをめぐってのオス同士の争いということも考えられます。
血と角の欠けは、いずれにしても生きていくための厳しさを物語っています。
約30年前の朝にも同様に現れたことがあって、そのときは5人が、感動で言葉が出ずにただポカンとして見入っていたものです。それは、町場から森の中に移り住んだという実感がわいたひと時だったように思います。
そのときの5人のうち、母親はすでにこの世にいず、ふたりの幼子は大きくなっててんでに家を出てゆきました。時は廻ったということです。
4月4日の我が家。
今も雪はまだたんまりとありますが、その消え去り方は特にここ数日は加速度的です。
春が足早にやってきています。
今、森にはオオルリ(大瑠璃)が来て、うつくしく啼きかわしています。何とも言えないうつくしい声。
今年はとても早いです。

それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をさらにクリックすると写真が順次移りかわります。