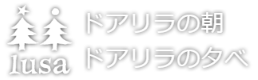本日は(2025年)3月も終わりに近づいた28日です。
朝から靄がかかっているし、すぐわきの谷川の音は雪解け水でマックスに達しているし(グァングァングァンというその音は近くで戦争でも起こっているかのごとくの不気味な音です)、本当に春が来ているなあと思わされます。
で、いつかはこんな時期…、厳冬期を避け、けれども春にはかなり遠い、そういう時期の山を歩いてみたいとかねがね思っていたものです。そしてようやくこの27日にそれが相成りました。
今回のsignalはその雪山歩きのこと、題して「雪山の呼び声」です。
*
山はおいでおいでとずっと呼んでいたし、こちらも雪山を歩きたく思って、西吾妻の玄関口の天元台にはじめに行ったのはこの21日のことでした。
山の天気の長期予報をにらみ、自分の動けない日どりを除くと21日がベストだったのです。降水確率0パーセントで晴天、リフトトップの朝の気温は0度前後、申し分ない条件でした。
ところがです。
今冬の大雪(現在のスキー場の積雪770センチ)で水源からの通水管に故障が生じ、天元台スキー場への生活用水はロープウェイ下駅(湯元駅)から水を汲んでタンクで運んでの営業が続いていたことは承知していました。その水源の工事日が21日とは。工事につき臨時休業と知ったのは到着したあとのことでした。
トホホです(-_-;)。
ならばと予定を変更させてやるべきことを前後させ、22日を空白にして行けば、何と今度は強風のため運行できずとのこと。事前にインターネットで調べて「運行を確認中」とあったので、たとえ風が強くて運行がむずかしい時間帯もあろうけど、小1時間も待てば動くはずと踏んでのことでした。それが着けば、「終日運休」に変わっていました。
参りました(-_-;)。
そうして3度目の正直、朝の情報の「強風のため運行を見合わせ」から「強風につき減速運行」に変わったのが8時30分。その時点でそそくさと用意を整えて天元台へと向かったのです。
上は町場から見る吾妻連峰。吾妻連峰は、米沢の平野部からはどこからでも見えるシンボリックな山です。
写真中央のピークが中大巓(なかだいてん。1,964メートル)で、その陰に百名山として知られる西吾妻山が連なっています。
中大巓のピークの右下の白くなっている部分がスキー場のコース(それは雪形から「白馬の騎士」として親しまれている)で、リフトはコースの最上部の北望台(1,860メートル)まで一気に上がってくれます。
ロープウェイの湯元駅から出発。
この時とばかりにお客さんが繰り出し第1駐車場はすでに満車、筆者は第2の方に回りました。
かつてはレストランとして営業していたホワイト。
なかなか趣のある巨大なフードタイプの暖炉があったものです。今は、休憩所として開放している模様。
このあたりが筆者たちのタケノコ(ネマガリダケ)の採り場でもあります。
リフトトップに着いてからのはじめての雪山歩き、まあ先に歩いたひとのスノーシューの足跡をついていくのが一番安全かと。
そのわきには山の会のみなさまがコースを外れないようにと縄を張っていてくれたのでした。山の会のみなさまに感謝です。
リフトトップの北望台(1,860メートル)で気温は何とプラスの6度、それは事前に分かっていたので、下駅ですでにズボンは脱いで下はレインスーツと厚手のレンギス(スパッツ)だけとしました。
雪山の行動では汗の処理が一番の課題です。汗をかいてそのままにしておけば身体が冷えてしまいます。山中で身体が冷えるのは命取りです。
それからせっかく用意してきたスノーシューだけど、天元台に勤める知り合いに聴けば、「登山者がずいぶん登っているので雪は固まっているはず、アイゼンで十分」、ということでスノーシューも預かってもらっての身軽さです。
吾妻連峰はオオシラビソ(大白檜曽/マツ科モミ属=アオモリトドマツ)のうつくしい樹木でおおわれ、大白檜曽三大美林のひとつとされています。ちなみにあとのふたつは、八甲田山と八幡平とのこと。
今回よく目にし、あらためておどろいたのは、オオシラビソの冬姿。
雪におおわれ枝が雪の堆積や陽気で下に強烈な力で引っ張られても、まるでゴムのようになって力に順応し力を少しずつ逃しているのでした。この知恵は驚異的です。
そうして圧力から解放されると、まるで形状記憶のように枝を張るのです。
であればこそオオシラビソは、過酷な自然環境の中で生き延びてこられたのです。
オオシラビソの樹林帯を30分ほど歩くと、眺望が開けました。
ここでレインスーツの下の、長袖のダウンシャツを脱ぎました。よってレインスーツの下はベースレイヤーの薄手のメリノウールの上に半袖のダウンジャケットだけとしました。動いたので暑くてかなわないのです。
今回、はじめての2,000メートル級の雪山で気を使ったのはこの重ね着、身体の状態によって素早く臨機応変に着脱することでした。こういったレイヤリングを勉強したかったのです。
これは野生で過ごす(生活する)ためのスキルのひとつですね。
前方に開けた西吾妻山方面。
今回はさまざまな試しということもあってひとりの山行であったのだけれど、当日、先の登った形跡はなし、後に誰もついてくる気配はなし…、ということは、この雄大な景色をまったくの独り占めなのです。
独占禁止法違反だと思うけど(笑い)、申し訳ないが気分がいいです。爽快です(笑い)。
でもこんな独り感ははじめてのことかなあ(笑い)。
筆者の今回は、こんないで立ち。
上下のモンベル製のゴアテックスのレインスーツの機能は抜群です。
たぶん高さが5メートルくらいもあろうかという標識ポールがこの状態でして。
西吾妻山方面。中央の奥が西吾妻山。
*
たった10日とか1週間とかわずかな期間しか花を咲かせない高山植物が今、雪の下で安らかに眠っています。重くて冷たい雪の下での、約9カ月という長期にわたっての辛抱です。
筆者は、雪の下の高山植物を思います。
ときに、けな気で愛おしくなるのです。
たとえば、アオノツガザクラ(青栂桜/ツツジ科ツガザクラ属)。
たとえば、ガンコウラン(岩高蘭/ツツジ科ガンコウラン属)の実。
たとえば、コケモモ(苔桃/ツツジ科スノキ属)。
たとえば、コメバツガザクラ(米葉栂桜/ツツジ科ツガザクラ属)。
例えば、チングルマ(稚児車/バラ科ダイコンソウ属)。
たとえば、ヒナザクラ(雛桜/サクラソウ科サクラソウ属)。
ヒナザクラは東北の山にしかない花で、八甲田が北限、西吾妻がその南限です。
そしてたとえば、ミネズオウ(峰蘇芳/ツツジ科ミネズオウ属)。
ヒナザクラ以外は樹木の分類です。
里や野山の植物とは関係性・類似性を見つけるのがむずかしい植物たち。

これらの植物はかつては北方寒地に生えていたもので、氷河期において南下し、その当時はベーリング海も陸続きであったために広まったものです。その氷河期が退いて気候が温暖化することによって高山に逃げ込んだものが今の高山植物と言われるものなのです。
高山植物は気の遠くなるようなはるかな過去の時間を今に伝えています。
すべてを特別天然記念物に指定して国全体が守っていかなければならない貴重な存在なのです。
*
梵天岩にて。
夏山の場合、梵天岩まではダウンしてアップしての高低差がはげしいのだけれど、雪山はさにあらず。傾斜もまるで象の背中のようにゆったりとしたものです。
中大巓から東大巓につづく、一切経山への縦走路の尾根。
梵天岩の標識。
標高は2,000メートル近くとなり。
梵天岩にほど近い天狗岩を望遠で。
中央は石でおおわれてつくられている吾妻神社。
西吾妻山に近づくにつれ、樹氷が現れてきました。
間に合ってよかった!
もう3月の下旬だし、期待は半分でしたので。
冬の西吾妻の美しさは樹氷原にあります。
1,900メートルくらいまでは解けかけていましたが、ここのはまだまだ立派です。
ひとすじふたすじ、シュプールのあともありましたよ。
山岳にも適応するテレマークスキーを担いで登って、山頂から一気に滑ったようで。
小さなスノモン君と一緒に。
スノモンはスノーモンスター、樹氷のこと。
西吾妻山(2,035メートル)山頂にて。
夏山では西吾妻山山頂は樹木におおわれて一切の眺望はなし。それは遠くから来るひとをいつもがっかりさせるのだけれど、冬場はこの通り。
中央にそびえるのは磐梯山(1,816メートル)。
1888(明治21)年の磐梯山の大爆発で堰き止められた檜原湖。左に秋元湖、小野川湖、奥には猪苗代湖さえ望めます。
ちょっとガスっているように見えるけど、真昼の南側はえてしてこんなものです。
それにしても雄大な景色、裏磐梯が一望で、あ、あそこがニッコウキスゲ乱れ咲く雄国沼、あそこが猫魔、そして安達太良だ。
なんてすばらしいパノラマなんだろう。
山頂よりすぐ西に西大巓(1,982メートル)。
福島側からはグランデコスキー場から登って、西大巓を経由して西吾妻山頂となります。
目を北に移せば、蔵王の峰々。
西大巓より少し北寄りに見れば、そこには西吾妻小屋。その奥は雄大な飯豊連峰が控えています。
西吾妻小屋を背景として。
西吾妻小屋。
冬場は2階からの出入りが可能で、トイレも使用できます。
さすがは避難小屋です。
2階部分。
梵天岩、山頂、西吾妻小屋経由で天狗岩…、これは夏山のコース同様のめぐりです。ただし、雪で高低差がわずかとなって平原の移動は自由自在、アイゼンのみの装着とはいえ歩きはスムーズです。
吾妻神社。先ほどは望遠のショットでしたが、帰りには立ち寄ってきました。
厳しい自然環境に中に立つ素朴な神社は原始宗教を宿しているようで。
樹氷群。
中大巓。
弥兵衛平、東大巓方面へ。
冬山登山道を示す標識に戻ってきました。
かもしか展望台にて。奥に飯豊連峰。
うつくしいオオシラビソの樹林帯を抜けて、歩きはじめのリフトトップに戻ってきました。
歩きはじめが10時20分、到着が12時40分、およそ2時間20分の行程でした。
夏場の標準タイムが3時間ちょうどくらいですので、ずいぶんな時間短縮です。
リフトに乗って。
豆スキーヤーがあざやかなシュプールを描いていました。
風景は、オオシラビソからダケカンバ(岳樺)の林へと変わり。
*
しまいに、家の近くの笊籬溪の風景。
3月14日。
3月22日。
3月27日。
春だねえ。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。今回は特に横に広い2:1サイズのものを多用しましたのでなおさらです。また、写真の下にあるスライドショー表示をさらにクリックすると写真が順次移りかわります。