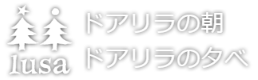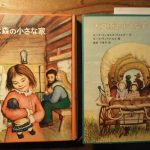筆者が職場通いをやめたのは定年を1年前倒しの59歳のとき、2016年春のことでした。
自分に残された時間(健康寿命)を思ったときに自由になる時間はそう多くはないという自覚はあり、定年前1年というわずかな時間さえとてもいとおしかったのです。その1年は5年分にも匹敵するほどという感じはしていたと思います。
その残された時間を使って木工をしてみたい、とりわけ日本において専門とする者のいない(と思われる)ドアリラ(一般にはドアハープ)製作をしたいと思いました。そうして筆者は工房のひととなったのです。
で、そうなるとこれは、昼飯は自分で何とかするということでもありました。相棒は出勤していって自分は在宅ということですから。
それまでというもの弁当はほとんど相棒任せ、自分がすることなんて食べてきた空の弁当箱を洗うぐらいがせいぜいでした。
というのも、筆者は長らく、男には外仕事や力仕事がある(山暮らし、森暮らしであれば、実際にそうです)、女は内仕事がある、と割り切っていたのです。あの名作ドラマ「大草原の小さな家」でもインガルス夫妻の仕事の分担は明確でしたよね。実に自然なことでした。
でも、これからはそうもいかない。
下はテレビドラマの原作、「インガルス一家の物語」のその1、『大きな森の小さな家』とその2、『大草原の小さな家』(福音館1972)。
このローラ=インガルス=ワイルダーが書き記した原作もいいです。ひとつひとつ、暮らしを手づくりしていくのがいいです。
今でも時々手にとっては読み返しています。
ということで、今回のsignalは筆者が昼食を機とした食に向いた興味、とりわけ冬場の食についてつづってみようと思います。題して「冬はからかい」です。内容とすれば、「冬はからかい、など」ですがね。
“からかい”って、おちょくり?(笑い) ちゃちゃを入れて相手が怒ったり困ったりすることをおもしろがること? 何でそれが食と関係がある?
それはおいおい。
*
我が家の納戸は普段は使わない品物の収納もさることながら、食糧庫の役目も果たしています。
たとえば、さまざまな果実酒類…。
今安らかな眠りについているのは(笑い)…、
ノイバラ(野茨)にハマナス(浜茄子)、ウワミズザクラ(上溝桜)、ガマズミ(莢蒾)、ナツハゼ(夏櫨)、それにユズ(柚子)とカリン(花梨)、オウトウ(桜桃)です。
リキュールに移る野趣のうるわしい芳香…、熟成が楽しみ。
それは馥郁(ふくいく)とした時間を用意してくれるでしょう。
それからたとえば、多くは自分たちで採集した山菜やきのこの塩蔵品…。
アブラコゴミ(油屈=キヨタキシダ/清滝羊歯)、ワラビ(蕨)やフキ(蕗)の山菜類に、ラッキョウ(辣韮)など。そしてクリタケ(栗茸)やナメコ(滑子)、ムキタケ(剥茸)のきのこ類が保存されています。
きのこ類は時たま塩を抜いて、そばやうどんの具として利用したりします。
塩抜きは大きめの器に入れて、2、3時間おきに、3~4回くらい水を換えてやればOK。1回目に水から沸騰させるとさらに時間は短縮できるようです。
そうしてほぼ塩が抜けたものを小分けにして冷凍しておけば、いつでも利用することができます。
下は、ムキタケとナメコを混ぜて塩抜きしたもの、それを小分けしたもの。
1週間に1~2度はつくる、きのこを具にしたうどん。
うどんはうどんでもやはりここは稲庭うどん、稲庭うどんはおいしくて飽きがこないですね。
休日のたまの昼食に相棒に出したり、来客があって(相手がそれでよければ)ふるまうこともあります。
下はある日の昼食のきのこと青物をのせた稲庭うどん、自家製柚子胡椒を添えて。
稲庭うどんは本場秋田ならいざ知らず、米沢では普段づかいの安価なものの入手はむずかしいです。
が、実はガソリンスタンドのチェーン店・東日本宇佐美の米沢営業所内の売店にはかんざし(簪)状のB級品?が置いてあるのです。これは、“知るひとぞ知る”的なものです。
かんざしは麺を棒に引っかけて伸ばしたときの切れ端と思いますが、十分な長さもあって味も申し分ないものです。
700グラムで800円ほどですからね、これは絶対お得というものです。
スタンドでも人気商品らしく入荷と共に数日でなくなるよう、取り置きの願いや入荷の問い合わせもあるのだとか。
*
その季節になれば、近(ちか/親)しいシミズさんから筍をよくいただくのですが、収穫の末期には1メートル弱もあるような、伸びきったものも(笑い)。
「伸びすぎてしまったけど、やわらかいとこもあっぺ、食ってけろ」、と。

ここで思案です(笑い)。
筍は煮つけに汁の実にそれからたけのこご飯にとずいぶんと工夫して食べたことだし、さてどうしよう。
節取りをすればまだ何とか食べられるところもあろうけど、では変わったところでメンマとして利用するのはどうかとネット情報をさぐれば、やはりいるのですね、先駆者が。実践者が、同じことを考えている輩(やから)が。わざと伸びきった筍をつかって、本場に負けず劣らぬメンマをつくることに情熱をかたむけている楽しい輩たちが(笑い)。
調べればそもそもメンマというものは、亜熱帯性気候に生育するマチク(麻筍)と呼ばれる筍を原料にしているのだとか。しかも1メートル近く成長したものを収穫して、先端部分と節間の部分をカットした後、それらを蒸して発酵させてから天日乾燥したものを保存食として利用してきたとのこと。※丸松物産のHPから
ならば、事はそうむずかしいことではありません。
堅い部分の節取りをし、米のとぎ汁で茹でてあくを抜き、袋に入れて密封して3、4日(これで発酵する。ビワ茶をつくる要領と同様とした)、あとはカラカラになるまで天日干しにすればよいのです。
そうして乾燥さえしっかりすれば、3年でも5年でもメンマとして利用できるというものです。
これはグッドアイデア。
冬場になって薪ストーブを焚きはじめた10月に、さらに室内で乾かして完璧な状態にしました。
発酵の匂いもしてとてもいいあんばいです。
それをさてと、この2月。
水から沸騰させて、冷まして、手揉みをし、水を換えて一昼夜…、
沸騰させて、冷まして、手揉みをし、水を換え一昼夜…、
そうすると、乾燥したものから水を切った状態での筍の重量は約5倍に増えていました。
それを市販の塩漬けメンマの調理と同じ要領(山形県は上山にあるメンマ加工会社の丸松物産のレシピを参照して何度もつくっている)で、調味料をからめて煮つめれば出来上がりです。
本来のマチクメンマともちがった食感でこちらもよろし、これもおいしくできました。
単品としておかずの一品に、ラーメンに添えるもよしで。
シミズさんにいただいた筍の竹は、調べればモウソウチク(孟宗竹/別名がモウソウダケ)と分かりました。
この辺にある植栽の竹は自分では勝手にマダケ(真竹)とばかり思っていたのですが、節に2本の輪があるのがマダケ、モウソウは1本なのでした。確かめれば節の輪は1本だったのです。
そういうことで名称は、“孟宗メンマ”としました。
“清水メンマ”でもよかったかも(笑い)。あるいは“巌メンマ”(笑い)。それとも“巌孟宗メンマ”がぴったりだったろうか?(笑い)
でもなあ、これを“イワオ妄想メンマ”なんてイメージされたら、それは大ごとだ(笑い)。
ちなみにですが、モウソウチクの名は、老いた母親に筍を食べさせたくて寒い雪の日に掘りにいった孟宗という孝行息子にちなんでいるとか。
泣けてくる話です(笑い)。
来年は、“ルーザの森クラフト謹製”の名で道の駅に並ぶ手はずです。すでに、知らない間柄ではない坂川駅長にお願いしておきましたし。
これは冗談(笑い)。
それでさっそく昨日(2月17日)、できあがったメンマをイワオさんに届けたのですが、とても喜んでくれました。
で、返礼としてか今度は、1メートルの雪の中から掘り出したという大根をいただいたのでした。恐縮しました。
雪の日に掘った筍ならぬ雪の中から掘り出した大根ねえ、感謝です(笑い)。
*
夕べは吹雪きでした。夜、町場であった会合から戻る時の国道13号のきびしさ。

筆者が18歳で進学のために家を出た1975年まで、冬場のごちそうのひとつは棒だら(鱈)煮でした。
山形県の内陸部、とりわけその南部の米沢を含む置賜(おきたま)地方は、太平洋からも日本海からもどちらの海からも遠いという地理的な特徴があります。それは何を意味するかといえば、流通がとどこおる冬場は新鮮な海産物を食べることができなかったということです。
冬は雪のために物流は鉄道が頼りだったでしょう、雪でクルマが動かないときに鉄道の駅より先は不透明、したがって冬場の魚屋にあるのはギンギンに塩をからめたシャケ(鮭)やマス(鱒)の塩引きや塩クジラの塩ものが主だったような。その他は身欠きにしん(鰊)や棒だらなどの乾物ぐらいだったような気がします。
ああ、ハタハタ(鰰)はあったなあ。
大量に入ってきていたものか、たまにオヤジが買ってきて焼いたハタハタはうまかった。ゴムのような弾力のある卵の食感が今も舌に残っています。
それから氷の中に納まったタラ(鱈)も入ってきていたかもしれない。
でも、生のタラを口にすることができたのは大晦日の鍋ぐらいだったと思います。我が家は貧しくもあったし。
時移って今は、スーパーマーケットに行けば冬でも魚介類の種類は豊富、刺身でも切り身でも、新鮮なものがいつでも手に入る時代となりました。まさに隔世の感です。
けれども筆者は冬場になると、新鮮な魚介類もいいけど干物の棒だらを思い出すのです。あの、舌が雄弁に記憶する、滋味豊かな、甘じょっぱい何とも言えない棒だらの煮つけ…。
それで探したのだけれど、棒だらってどこにでも置いてあるというものでもないのですね。スーパーでもわずかに残る地元資本の店にはあったけど、全国チェーンの店にはありませんでした。たぶん、チェーンのバイヤーは山形県民が棒だら煮をどれほど愛しているかを知らないのです。
そして筆者は買ってきましたよ、地元の店のコマレオで。
内容量178グラムで756円でした。今もそう高いものではないですね。
棒だらを袋から出しまして、
一昼夜、水にひたして戻し、

やわらかくなったところを出刃包丁で食べやすい大きさに切りました。
干物の棒だらのもとはスケソウダラ(助宗鱈)です。
スケソウダラの、干物にされる前の姿。

切り身を鍋底に並べ、戻し汁を利用しひたひたになるくらいに注ぎ、薪ストーブの上でコトコト。
酒、みりん、しょうゆ、砂糖を入れて、ゆっくりコトコト。
強火は魚身をくずしてしまうのだそうで、ゆっくりとコトコト。
水分が少しずつ減っていき、
魚身に煮汁が徐々にしみ込んで、
一旦火から下ろして、静かに冷やして、
また、コトコト。
さらに煮汁を魚身にしみ込ませて、
冷やして、またコトコト。
そうして最終的に冷やせば、棒だら煮のできあがりです。
これがたまらないのです。ウンメエです!(笑い)
*
それから、からかい。
冬の食 my rank で、からかい煮と棒だら煮は他を圧倒して王者であり女王です。世界の誰とてこれを覆すことは不可です(笑い)。
“からかい”というのは、エイ(鱏、鱝、鰩など)の干したもの。
一般に知られるエイ干しの商品名は(最近知ったことですが)“かすべ”なのですね。けれども山形県では昔から“からかい”の名で通り、県でも庄内地方は“からげ”という名で呼んでいるところもあるそうな。
正月には必ずと言っていいほどにからかい煮は出る、忘れられないハレの日の料理です。
からかいはエイのヒレ(鰭)を干したものとは知っていたけど、エイはエイでもガンギエイ(雁木鱏)という種類だったとは知りませんでした。
雁木(がんぎ)とは空を飛ぶ雁(ガン)の列のような形を指すとのこと、ひとつ勉強をしました。
からかいはこの量で178グラムとあり、これだけで1,620円もしました。
からかいはもはや高級品になっているのですね。

棒だらとからかいの煮つけの仕方や味つけは似たり寄ったり。
ちがうところがあるとすれば、からかいは戻すときに米のとぎ汁を使い、3日くらいの長時間を水にひたすこと、それからぬめりを取って沸騰するまで煮て、その水は捨て去ることでしょうか。棒だらは戻し汁を生かすことが肝要のようです。
あとは棒だら同様コトコトと煮つめ、冷ましては煮て、煮ては冷ますことをくりかえして味をしみこませていきます。
そうしてできあがった、からかい煮。
からかい煮を外の冷気で冷やせば、煮汁がやわらかい寒天のようにプルプルする煮こごりと化しています。
この煮こごりこそ、からかい煮の真骨頂です。

ウンメエのなんの!(笑い)
不覚にも、ほっぺたが落ちました(笑い)。
うまさに涙がにじみました(笑い)。

棒だら煮にせよからかい煮にせよ、はたまた塩引き(鮭、鱒)にせよ特別に冬に食すのは、雪国ではその昔冬に行動が制限され、容易に外に出かけることができなかったからです。
そうしてひとびとは冬の暮らしの辛苦に耐えながらも、なんとかおいしいものにありつきたいと願ってきたのです。その知恵の最たる結晶が棒だら煮とからかい煮なのです。
棒だら煮とからかい煮こそは文化遺産、食の世界遺産と言ってもいいと思います。
筆者の相棒は米沢と奥羽山脈を隔てた福島県伊達郡梁川町(現在の伊達市梁川町)の出身、距離にして60キロのところです。
ところが、縁あってこちらに来るまで棒だら煮とからかい煮はまったく知らなかったということです。それだけこれは、海から遠い内陸部の雪国に発達した特別な料理ということが言えると思います。

なお、自分の幼い頃にはありつけなかったもので米沢で親しまれてきたものに塩引き寿司があります。
米沢に移ってきてからはじめて食べたのですが、これもまたすばらしいです。
*
今、リビングにはお雛様を飾っています。
福島は三春張り子のお雛様、控えるは会津の起き上がり小法師です。
玄関口に鎮座する、米沢を代表する民芸品の土人形の相良(さがら)人形。
戦後7代目の故・相良隆さんの逸品です。
昨年の夏に、市内のアンティークショップの禅林堂で購入したものです。
なお、こちらの男雛と女雛は上の並びと違いますが、こう位置するのは京風、関西風なのだそうです。
華やかかりし雛人形は、春を呼ぶ使者でもあります。
春よ来い、早く来い、です。
次のsignalは、「カレンダーめくれば春が迸(ほとばし)り」(いつぞやの朝日川柳)のごとく、春のきざしや匂いが届けられるでしょうか。
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をさらにクリックすると写真が順次移りかわります。