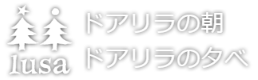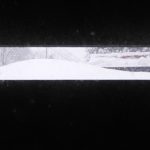本日は(2025年)2月12日、久しぶりに太陽というものを拝んでいます。
ありがたきはお日さま、です。
冬場の筆者の日常のはじまりはほぼ決まっていて…、
目覚まし時計は5時20分にセットしてあって、目覚ましが鳴ればどんなに眠かろうが飛び起きます。そして薪ストーブに火入れをしたら防寒着に身を包み、10分後には外に出て除雪にかかります。
そうして雪の状態によって小1時間から1時間半の作業を終えてから朝食、外に職場を持つ相棒を送り出して、皿洗いなどの家事を済ませてからその日の仕事(ものつくりその他の課題解決)にかかる…、このくりかえしです。
この冬はことのほか厳しく、降っても降っても雪降りやまず。
寒波は断続的で居座りが長く続くのが今冬の特徴でしょうか。
とにかくすごい雪の降りよう、雪には慣れているはずの我が身も怖さを覚えるほどです。
今回のsignalは今冬の大雪の続報、題して「降っても降っても」。
*
2月2日には、町内会長として集会所(公民館)の雪も放っておけず、6人の隣組長に声をかけてみんなで汗を流したものでした。
それにしても、大屋根から滑り落ちてたまった雪のこの高さ!
ホイルローダーも除雪機もすごい雪の前にはあまり役に立たず、最終的には人海戦術で屋根の下の巨大な雪山を崩したのでした。
強烈な寒波がやって来たのは、その2日後のことでした。
雪はしんしんと降りしきり、雪はとめどなくもさもさと降ってきて。
この“もさもさ”というオノマトペはたぶん、米沢を含む置賜(おきたま)地方の方言だと思います(笑い)。
※この“もさもさ”について調べれば、たとえば新潟県の山古志とか、八戸とか仙台とか、東日本・北日本の局所局所で用いられているよう。山形県では置賜だけでなしに全域なのかもしれない。
もさもさ…、長い年月にわたってひとびとは、とめどなく雪が降る様子をこうつぶやきつづけてきたのです。
リビングから見える景色。
ベランダのビールケースの上は冷蔵庫代わり。
このサッポロビールのビールケースは飲んでたまったものではなく(笑い)、踏み台や作業台として使うために酒の販売店から購入したもの。ひとつ300円はしなかったと思いますが、今は流通しているかなあ。
なぜサッポロかと言えば、それはケースの色が赤だからで(笑い)、意図してそろえたのです。黒い板壁との対照の妙というわけでして。
屋根から落ちてきた、もう限界の雪の山。
これ以上放っておけば、雪囲いの板の高さを超えて雪がガラス窓を直撃してしまいます。
除雪の優先順位第1位!
ベランダに積んでいる薪。
使い込んで嵩(かさ)を減らせば、天気の落ち着いた日に薪小屋から補充します。
薪は筆者たちの冬の暮らしを支える貴重な燃料です。
工房仕事の合間に雪かき、と言いたいところだけれど、このところは逆転、雪かきの合間に工房仕事という感じです。工房に入ることができない日も多くなってきました。
工房の窓の雪囲いの板のすき間から見える風景。
ルーザの森クラフトの主製品のドアリラ、その特別な注文が入り、図面から起こして思案中。
まっさらな状態から新たにものをつくり出すってとてもたいへんなことです。
注文はひとつだけど、ひとつつくるも複数つくるも同じこと、それで今後の販売も見越して6体をつくろうとしています。
時に、ラジオでクラシック(「クラシックの庭」など)を聴きながら。
暖かい地方にはあたたかい地方なりの、雪国には雪国なりの機能というものが備わっているのだと思います。雨が多く風の強い地方にはそれなりの防備があるはず。環境が機能の形をつくっていくのです。
例えとして家屋の柱の太さは暖かい地方と雪国とでは違うでしょう。南の地方が3寸角(約90ミリ角)なら北は3.5寸が標準では。さらに強度を望むのなら4寸を使うのかもしれない。雪の重さを考慮すれば構造材はおのずと太いものとなるものです。
例えてこのへんで水道管といえば地下45センチ以上に埋設されているのが標準です。これが暖かい地方なら30センチでよいはず(関西地方の規程)で、それは凍結に耐えるための深さの差です。寒さ厳しい北海道では100センチ以上とのこと。
一事が万事です。
地方地方、そこに暮らす者はそこに暮らすための機能とスキルを有しているものです。
たった数センチの雪で「大雪」と騒ぐのは、雪が降らない地方に降ってしまったから。1メートルの雪でも平然としているのはそれなりの備えがあるからです。環境が機能の形をつくるのですから、それは自然なことです。
たぶん、雪国に自生する木々も周到な防備機能を有しているはず。とくに針葉樹にはそれを感じます。葉を落とすことなく酷寒に耐えていられるのはどう考えても驚異的です。葉を通して体温が奪われないような構造になっているということでしょうか。
動物だってそう。サルがどこまでも白い雪原の中で生き延びるためにクワ(桑)の木の樹皮を剥いで食べて飢えをしのいでいるのも、イノシシが雪の中では川に集結するのは川端に青いものが見えるから、クマが冬眠するのもそうですよね。
そういう意味では寒さと雪が必然の地方の方が、あたたかい地方より生き延びるための野生を残しているのかも。
そう、野生という、都市と社会を形成し、便利と快適の抗いがたい魅力にいざなわれて暮らす住人が徐々に減退させているこの感覚。
雪の降らないところに運搬用のソリは要らないし、当然にもありませんよね。でも我が家では必需品です。
このソリは約30年前に6,000円ほどで購入した覚えがあるけど、今は15,000円もするようです。
このソリは有能、これぐらいの薪で60キロくらいの重量はあるだろうか、でも雪を滑らせれば楽々運べます。
玄関わきには鉄製のスノーダンプと、石炭スコップと平シャベル。
雪の状況で使い分ける必要があるのです。そのほかにも、先のとがった剣スコップ(ケンスコ)やツルハシも備えてあります。
除雪機の格納庫前にもスノーダンプとスコップ。
同様のスコップは工房と車庫にも備えてあります。
備えあれば患(うれ)いなし、なのです。
*
この10日、市役所に用があって、気が進まないながらも久しぶりに町場に出ることに。
外は吹雪いて、道路はスノーボードのハーフパイプ(笑い)。
笊籬溪(ざるだに)の今。
クルマのすれ違い不可能な約1キロの森の道が続きます。
もし中ほどで対向車にあったらたいへん、どちらかがバックして相当の距離を戻らねばならず。
待避所をつくるよう(米沢)市の土木課に申し入れをしているのだけれど、雪が多くなってくればそれも消滅してしまいます。
そんな道を幸運にも対向車なくようやく抜け切ってホッとした矢先、何と施設の解体工事を請け負う建設会社のホイルローダーが目の前で道路を塞いで立往生したではありませんか。ガビーン、です(-_-;)。
ローダーと言えど万能ではなく、あまりの雪に“亀の子”となってしまったよう。どんなに優れた重機でも腹に(底に)雪がつまってしまえば車輪は空回りするだけなのです。
作業員が必死に雪の壁を崩して筆者のクルマを通そうとしています。やれやれ、です。 
と、用を済ませて町場から戻れば、道の幅出し(道路の拡幅)のためにロータリ除雪車と除雪ドーザが組になって来ていました。
何度か話したことがあるドーザのオペレーターが筆者に声をかけてきました。
「とにかくたいへんだ。(夜の)12時に起きて1時半から(この地区の)作業をはじめて、あんたのところに行くのが5時半、押し雪場(雪の押しつけ場所)に(雪の壁が高くなってしまって)もう雪が上がらない。もう限界だ」とぼやくばかり。
その苦労は分かりますけどね。お疲れ様です。
突然ですが、ここでクイズです。
下に、ぽこぽこしたモーグルのこぶみたいな写真があるけど、さてこれは何でしょう。
正解は墓場(笑い)、我が家の墓もある地区の共同墓地です。
先祖のお骨が雪の布団をかぶって気持ちよさそうに?眠っている図です。
こんなことだから、春の彼岸の墓参りというものはここらでは不可です。墓はまだまだ雪の下ですから。
*
除雪機で飛ばす雪の影響のないところに設置している積雪計。
黄色と黒は20センチずつの刻みです。赤い紐は200センチライン。
1月30日、160センチ。
1月31日、180センチ。
200センチラインの赤い紐。
2月6日、190センチ。
2月9日、225センチ。
2月10日、240センチ。
この日はさらに降ったので、午後には245センチまで積みあがっていました。
ここまで来るとねえ(笑い)。
笑うしかない(笑い)。
雪の降らない地域に住むひとがここルーザの森に来たら、白目をむいて(笑い)、口から泡吹いて(笑い)、卒倒するかも(笑い)。
除雪しても除雪しても、雪は容赦なく降ってきて、また除雪、また除雪。
頃合いを見て外に出るための、時間刻みの天気予報と雨雲(雪雲)レーダーのチェックは欠かせません。
そして、「今日のひと針、明日の十針(とはり)」、なのです。
今にできることをやっておかないと後につけが回ってたいへんなことになる、やがてしっぺ返しが来る、そしてお手上げ状態になる…、これはもはや絶望です。
見て見ぬふりをしてはならない、怠慢は事故と災害を呼び込みます。
これは、絶望を避けるための、ひとに残された野生の知恵です。
そうして雪国のニンゲンは歳のことも考えずにアドレナリンを全開にして頑張るのだけれど、それゆえに事故の痛ましいニュースがあちこちから聴こえるようになってきました。あまりに想定外の雪ゆえのことです。
屋根からの落雪で埋まって亡くなった、屋根から滑り落ちて腰の骨を骨折した…、気温の状態だとか(特に屋根の)雪の状況の見誤りが原因には違いないのだけれど、つい無理をしてしまうのは絶望から逃れたいからであって。
そんなことにお構いなく、もさもさ、もさもさと、降っても降っても雪はやまず。
この除雪機なくして、冬を乗り越えることはできません。
これまでにすでに120リットルのガソリンを消費しています。
身体はみりみりして(笑い)筋肉痛。 時に、身体全体がだるくもなり。
でも、筆者のように在宅して時間がどのようにでもなる者はまだいいのです。
(かつての自分のように)外に職場があって、こんな時期さえ毎朝出勤しては夕方に帰る勤め人の大変さと言ったら…、気の毒のひと言です。
かつての筆者もそうでした。朝暗いうちから2時間ほども除雪して出勤し、夕方から夜にかけてもまた2時間ほども除雪して事なきを得る、そうしてまた早朝から除雪して…、そうしなければ家屋と暮らしを守れなかったし。

こんな過酷な雪は1993年にここに移住して以来はじめてのことと思うのだけれど、過去の記録に当たればそうでもないのでした。
ひとって、つらいことがあると今が一番なんて錯覚するのですね。
たぶん2010年以降で記録している限り、最大積雪深で2013年は260センチ(ピーク2月25日)に達していました。18年195センチ(1月26日)、21年230センチ(2月23日)です。
記録には残していないけど、2005年と2006年の冬の厳しさはすごかった印象もあります。2006年の2月、市中の5階建てビルの天井が雪の重みで崩落、ということもありましたし。信じられない事態でした。
それでも、それでも筆者は、雪を忌まわしいものに思わないのだけれど、それはなぜだろう。
長く、きびしい冬があるというのはいいことだ。もし冬がなければ、春の訪れや、太陽の沈まぬ夏、そして美しい極北の秋にこれほど感謝することはできないだろう。もし一年中花が咲いているなら、人々はこれほど強い花に対する想いをもてないだろう。雪どけと共にいっせいに花が咲き始めるのは、長い冬の間、植物たちは雪の下ですっかり準備をととのえていたからではないか。そして人の心もまた、暗黒の冬に、花々への想いをたっぷりと募らせているような気がする。
めぐりくる季節で、ただ無窮の彼方へ流れゆく時に、私たちはたった一回の生命を生きていることを教えられるのだ。
星野道夫『長い旅の途中』文藝春秋1999
極北のアラスカの季節を静謐な文でつづる星野のごとく、
筆者は、厳しい試練があるほどに春は輝くのを知っていると思う。あの、芽吹きの頃のひかりの美しさ!
試練があれば幸いは深くなることを身体に刻んでいる、とも思うのです。
早朝の除雪ドーザ。
雪は、排土板(前面の、雪を圧す板)の高さをゆうに超えています。
能力の限界を超えながらもオペレーターは作業に従事してくれています。
お疲れ様です。
屋根からの落雪を除くためのアプローチの壁はもう5メートルを越しているよう。
我が家では小屋を含め6棟の建物があるけど(主屋以外はすべてワタクシの自作)、屋根の雪下ろしは原則しないこととし、落雪に任せています。そのために建物のすべては滑りよく耐久性のあるトタンに張り替え、主屋のそれは10年ごとに塗装(シリコンコーティング)を施しています(当然にも業者に頼んで)。
でも、一番東に位置するコンテナ小屋だけは雪が積もるばかりです。コンテナ小屋は東から南にかけては樹木でおおわれていて日が差す時間が極端に少ないがためです。
それで、もう限界に達して今季2回目の雪下ろしをしました。
雪下ろしの条件は外気を見誤らないこと、屋根に上るのなら午前中の氷点下前後の時に限ります。それから、屋根の上10センチほどは雪を残す、決してトタンまで掬(すく)わないということです。
ものすごい積もりよう。
*
1月31日。
2月6日。
2月7日。
2月9日朝6時。
2月9日午後4時。
2月10日。
2月11日。
そして本日、2月12日。
超巨大なガルショーク(壺焼きシチュー)の出来上がり(笑い)。
これは、「ぐりとぐら」のカステラどころの騒ぎじゃないです(笑い)。
*
雪と冬の厳しさのピークはほぼ2月20日です。雪国に暮らすひとびとはこの日をどんなにか待ち望んでいることか。
2月20日が過ぎたら、警戒心は少し解いてよいことになります。
この日が過ぎたら、たとえ吹雪がきても、雪が降り続いたとしても知れたもの、長く続くことはありません。あとは、春のにおいをさがすばかり。
そのうち雪は甘くなり、ぼたん雪が見られるかもしれない。ぼたん雪は確かな春のいざないです。
まだ筆者が10歳の頃だったと思うけど、冬の峠を越えた3月、薄くて大きな、赤ちゃんの手のひらくらいに大きな雪が垂直にゆっくりとあとからあとから落ちてきて飽かずながめていたことを思い出します。
中国ではぼたん雪でも特に大きな雪片の雪を“鵡毛大雪”(ムモウタイセツ?鵡は白いオウムを指しているよう)と呼ぶのだそうで、筆者が目にしたのはそんな雪、大きくて羽根のように軽い雪でした。
日は少しずつ長くなってきました。東から西への太陽の軌道の扇の角度も少しずつ開いてきました。
もう少ししたら雪が引き締まってきます。そしたら、堅雪渡りができます。それからスノーシューを履いて縦横無尽に森の中を歩き回りましょう。それは大きな楽しみ。
大量の雪はやがておいしい伏流水となってワタクシタチの前に現われでるでしょう。
雪はやがて田畑をうるおし、川となって森の養分を海に運ぶでしょう。そういった自然のめぐりは希望そのものです。
リビングには一刻も早い春をと願って、米沢の伝統の技、笹野一刀彫の木花(笹野花)を飾っています。
ずっとずっとその昔、かつてはアイヌコタンだったという笹野地域に伝わる、アイヌの祭具イナウに似たいにしえの技のうつくしさです。
春よ来い、早く来い、です。
*
それじゃあ、また。
バイバイ!
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。また、写真の下にあるスライドショー表示をさらにクリックすると写真が順次移りかわります。