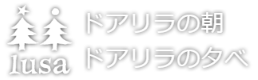長く親しんできた茨木のり子の詩の中でも、私が特に好きなのは「花の名」という一篇です。
この詩について、私の勝手な思いめぐらしを記していこうと思います。
「花の名」はおおよそ、次のような内容になっています。
父親を野辺送りしたのちの帰りの列車で、たまたま乗り合わせた(向かい合った)男性と他愛のない会話をすることとなった。自分は静かにしていたいのに相手はおめでたいくらいに陽気で、そんな中(明滅するかのように)亡き父の言葉やなつかしい思い出が浮かんできた。そして男性はいろいろと花の名前を覚えたいと思っていたと言い、大きな白い花がいちめんに咲くのは何だろうとたずねる。自分は、今頃の季節ならそれは泰山木(タイサンボク)ではと伝えるが、東京駅に着いて別れたあとに、咲く時期が違う、それは辛夷(コブシ)だと気づく、というもの。
花の名にこと寄せて父の喪失のテーマにせまるその大枠の構図と自然な流れに沿ったストーリー、練られた技巧の跡を垣間見せつつ、そうして昇華された虚構空間が読む者をしてこころ震わすのです。
この詩の魅力はここに集約されるように思います。
第三詩集と「花の名」
この「花の名」はのり子の第三詩集『鎮魂歌』(思潮社)に収められています。
発刊は1965年、のり子39歳のときです。
この詩集には、「花の名」を筆頭に、以下、順に13篇が収録されています。女の子のマーチ/汲む/海を近くに/私のカメラ/鯛/秋が見せる遠い村/最上川岸/大男のための子守唄/あるとしの六月に/本の街にて/七夕/うしろめたい拍手…、そして最後に長詩「りゅうりぇんれんの物語」で締めくくられます。

その初版あとがきにはこう記しています。
「第2の詩集を出してから5年たち、不惑の年にだんだん近づいてきたが、惑いはかえって深くなり、自分の魂をもよく鎮め得ない。/鎮魂歌という題は、ひとを悼む詩が多かったためである」。
それから、詩集には様々な種の詩が入り混じったこと、読み返して残ったものは消しようのない足跡とし、後半は「りゅうりぇんれんの物語」の周辺について記しています。
上の詩集『鎮魂歌』初版は増刷には至らずにそのまま絶版、時経ってのり子75歳、2001年秋に童話屋から再刊されています。
そのあとがきには、分量(A5判見開き)の約3分の2を使って、やはり「りゅうりぇんれんの物語」の周辺について記し、こう続きます。
「りゅうりぇんれん氏は、2000年9月、87歳で逝かれた。損害賠償を求めた訴訟がやっと今年勝訴となり、「国は原告に2千万支払え」という判決が下ったのに、またもや控訴となって、裁判は子息に引きつがれている。/なにしろ強制連行のシンボルであり、生き証人であり、彼のうしろには無念の白骨累々なのである。/1945年8月15日の日本国の負けっぷりの悪さが、今も尾を引いていると思い知らされることが実に多い」。
これは、のり子が終生気にかけこだわりを持って対象化した、個人をないがしろにする国家の在りようへの問いかけを(この場を借りて)あえて付したものと言えるかもしれません。
確かに、初版あとがきに記すよう、この詩集にはひとを悼む詩が多く含まれています。

ひとつは「本の街にて」。
ここに登場する伊達得夫氏は編集者、書肆(しょし)ユリイカの代表で、1961年に41歳の若さで世を去っています。
56年6月(21日)にのり子は代表作のひとつに数えられる「六月」を朝日新聞紙上に発表しますが、その年に伊達は詩や批評を中心とした文学誌『ユリイカ』を創刊しており、このあたりからふたりは関係を築いていったのかもしれません。
再版のあとがきにのり子は、「りゅうりぇんれんの物語」の初出は初期『ユリイカ』で、伊達氏から「特別ですよ」と告げられた秘蔵の中国の剪紙(きりがみ)をカットに使わせてもらったという思い出話を差しはさんでいます。

ひとつは「うしろめたい拍手」。
清末から中華民国、中華人民共和国にかけての京劇俳優の梅蘭芳(メイ・ランファン)がやはり1961年に亡くなっています。本来は女形の梅蘭芳は一貫して抗日の立場を貫き、日本軍の占領下では女形を演じない意思表示としてヒゲを生やしていたといいます。
のり子はこの役者の矜持(きょうじ)に大いに共感していたようです。
のり子にとってはふたりとも、こころ寄せて大きな影響を受けた人物だったのでしょう。


その他の詩にも戦争の影を引きずった亡霊もいくつか見え隠れしますし、60年安保闘争で亡くなった樺美智子の亡骸(なきがら)も抱えながら、詩集の題名を「鎮魂歌」としたのは初版あとがきの通りだと思います。
けれどもたぶん、冒頭の「花の名」における父の死は愛しい肉親であるがゆえに他をしのいで重いものだったことでしょう。
ゆえにこの「花の名」の別の題は「鎮魂歌」そのもののようにさえ思え、詩集名とした「鎮魂歌」とはこの詩のために用意されたとも言えなくはないと思います。
私がなぜまずあとがきに注目したのか、それはのり子自身が、詩集冒頭の、事実をベースとして紡がれた詩「花の名」にまつわるエピソードとかそれに関連づけられる何がしかに触れていはしまいかと思ってのことです。
あとがきには結局は何ひとつ見当たりませんでしたし、エッセーはむろん、対談とかインタビューでもこの詩への言及はないように思います。
その、触れていないことを確かめたかったのです。
およそ世に出した作品というのはそこから勝手に歩き出すわけですから、独り歩きしだした者に庇護や保護が不要なように、作品についての説明や注釈も同様です。もしそれらを必要とするものであるならそれは作品とはいい難いものでしょう。
作品はただ読者の自由な読みと受け取りにゆだねるだけがよく、作者は黙して語らずがいいのです。
ということで作者は、ここはノンフィクション、この部分は創作であり脚色などと手品の種明かしのような開陳(かいちん)をする必要はありません。
けれども一方、読者はただ素直に受け取るだけの存在ではありません。中には私のように疑い深くひねくれた輩もいるものです(笑い)。
そう、「花の名」は事実の積み重みでストーリーを紡いでいるように見えて、その実、創作と脚色も含まれている…、それへの魅力的な疑い(笑い)をかけつつ私なりの「花の名」の解題を試みたいと思うのです。
*
「浜松はとても進歩的ですよ」
「と申しますと?」
「全裸になっちまうんです 浜松のストリップ
そりゃあ進歩的です」
なるほどそういう使い方もあるわけか 進歩的!
登山帽の男はひどく陽気だった
千住に住む甥ッ子が女と同棲しちまって
しかたないから結婚式をあげてやりにゆくという
「あなたは先生ですか?」
「いいえ」
「じゃ絵描きさん?」
「いいえ
以前 女探偵かって言われたこともあります
やはり汽車のなかで」
「はっはっはっは」
わたしは告別式の帰り
父の骨を柳の箸でつまんできて
はかなさが十一月の風のようです
黙って行きたいのです
*
父の死
茨木のり子の実家は愛知県幡豆(はず)郡(現西尾市)吉良町吉田、実家の宮崎医院は(今も変わらずに)名鉄西尾線・蒲郡線の吉良吉田駅のすぐのところにあります。
のり子は1926年に医師である父・宮崎洪(ひろし)と(山形県庄内は三川町出身の)母・勝(かつ)との間に大阪で生まれ、洪の勤務の関係で大阪から京都へ、そして愛知県西尾市に移ったのはのり子が6歳のとき、それから洪が(町議会の強い要請で)医院を開業、吉良町に転居したときは16歳でした。
この間のり子は、11歳で母を亡くしています。

父・洪の死去は、1963年4月2日、曜日は火曜です。
葬事(特に葬儀・告別式と火葬)では忌み日として六曜の友引を避けるよう、その友引が5日、そうすると気ぜわしいながら通夜は翌3日、葬儀(告別式)は4日に執り行われたものと思われます。そして1日おいて、6日土曜に遺骸を荼毘(だび)に付したものでしょう。
詩の記述からして洪の死は突然であったようですが、のり子は夫である三浦安信とともに通夜には間に合うように駆けつけたはず。
安信は4日の葬儀(告別式)を終えてひとり先に東京に戻ったものと推察されます。よって詩に綴られる場面、のり子の東京への帰途はひとりです。
帰路
まず、父の葬事から東京への帰途、のり子が列車に乗り込んで登山帽の男性と向かい合うまでを想像してみたいと思います。
(吉良吉田を含む愛知県西部地区の天気は)1963年春4月、死去の2日は時おり北西の風が吹きやや肌寒いながらも雲ひとつない快晴でした。
通夜の翌3日は気温が17度まであがってこれもほぼ快晴、葬儀(告別式)の4日は気温が20度を越してあたたかな日和で薄曇りから晴れへと推移し、5日はさらに気温が上昇して晴れ、火葬場にあった6日は南からの微風が吹いてあたたかく穏やかに晴れていました。
のり子が帰途についたと思われる7日は日中は12度ほどにしか上がらずに寒く全般に曇りでした。
父の一連の葬事を終え、のり子は医院を継いだ弟・英一がいるにせよ(表面上は別にしても)交流薄く親しみ少なかったであろう継母のいる実家では腰が落ち着かないことは確かだったでしょう。
そして当然、実家が開業医では患者が診療を待っている身、代替わりした弟自身もそうのんびりとはしていられなかったでしょう。
よってのり子は火葬を終えた翌日の7日日曜の朝には東京への帰途についたのではないかと想像されます。

7日の朝、のり子は(普通に考えて)歩いてすぐの吉良吉田駅から名鉄(名古屋鉄道)に乗って蒲郡に出、国鉄東海道本線上りに乗り換えたものでしょう。
1963年というのは戦後日本のエポック、かの東京オリンピックの前の年のこと、同時にそれは東海道新幹線の開業の1年前でもありました。
私にとってはまったく縁のない東海地方、しかももう60年も前の鉄道事情がどんなものだったかは想像すらできません。そこでここは当時の時刻表を探してにらめっこする以外にはないと思われ、ようやく探し出して調べはじめました。

そして分かったことは、のり子が名鉄から東海道本線に乗り換えた蒲郡と、それから詩の流れで重要な、向かい側に座る男性が乗り込んできたと思われる浜松の両駅で停車し、そこから東京まで乗り換えなしで行ける列車は急行列車か(停車する駅が急行より若干多い)準急列車に限られるということでした。
詩に描かれる様子からしてのり子の乗車はおおまかには午前中でしょうから、そうすると以下いずれも蒲郡発の、急行列車は11時41分発の「六甲」の1本、準急列車は7時37分発の「東海1号」、9時14分発の「東海2号」、11時16分発の「東海3号」の3本です。
鈍行列車にも7時49分発と10時49分発の東京行きがありますが、いかに急がぬ身とはいえおよそ7時間をかけてコトコト、ふたりして時間を共にするイメージは現実的ではありません。
急行なら4時間20分弱、準急なら4時間40分ほどの所用時間です。
ちなみにですが現代の東海道新幹線では(蒲郡から14分ほどの)豊橋から東京までは1時間40分弱です。隔世の感とはこのことです。
準急東海2号
こうして見てゆくと、のちの桜と海の描写の様子などからして、のり子が実際に乗り込んだのは準急列車の7時37分発の東海1号か9時14分発の東海2号にしぼり込めるように思います。
当時の名鉄蒲郡線の吉良吉田発蒲郡行きは30分程度の間隔で出ており、所用時間は35分ほどです。したがって東海1号に乗るなら朝早く、遅くて6時半ぐらいに、東海2号なら8時過ぎくらいには実家を出る必要がありますが、葬事をようやく済ませた実家を気ぜわしくさせてはならないという配慮がのり子に働いたのなら、現実的には東海2号に乗車したとするのが妥当なところではないでしょうか。

東海2号なら、豊橋が9時28分、浜松が9時59分、静岡は11時ちょうど、熱海が12時8分、そして美しい海が見え出す早川や思い出深い根府川(のり子の記念碑的な作品のひとつに「根府川の海」がある)を通過すのが12時半くらい、終点の東京には13時55分に着きます。
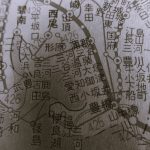
準急東海2号が蒲郡を出、豊橋と鷲津に停まって約40分もすれば車内はだいぶ込んできたよう、作中の登山帽の男性が浜松(または磐田かもしれない)から乗り込んできたものでしょう。「ここ、よろしいですか?」、「どうぞ」とかなんとか軽く言葉を交わして。
詩は「浜松はとても進歩的ですよ」とストリップと浜松をからめて冒頭に置きますが、のちに「僕は材木屋です」と紹介しているとおり、浜松というのは男性の住まいを指していると思われます。
そして対面に腰を下ろした男性がさっそくにものり子に「あなた様はどちらから?」とか聴いて、「ぼくはここ浜松」とでも言ったのでしょう。そのあとに「浜松はとても進歩的ですよ」がつながってゆくという流れであり、ここから詩がはじまっていきます。
挽歌とユーモア
それにしても「花の名」はまごうことなき挽歌、重い喪失の歌であり鎮魂歌のはずなのに、のり子は特有のカラッとしたユーモアでのっけから笑わせてくれます。
自分のこころは「父の骨を柳の箸でつまんできて/はかなさが十一月の風のよう」としているのに、相手が浜松にかけて話し出したストリップのことを「進歩」にからめてわざわざ置き、次には登山帽の男性があなたは何をなさっているのかという問いに対しては、はぐらかしながら、「以前 女探偵かって言われたこともあります」と余計なことまで語っています。このへんはもう、プッと噴き出してしまうほどです。
それから、「千住に住む甥ッ子が女と同棲しちまって」などと、なんて砕けたことを差しはさむものか。
これで、どこが挽歌だというのでしょう(笑い)。
*
「今日は戦時中のように混みますね
お花見どきだから あなた何年生れ?
へええ じゃ僕とおない年だ こりゃ愉快!
ラバウルの生き残りですよ 僕 まったくひどいもんだった
さらばラバウルよって唄 知ってる?
いい歌だったなあ」
かつてのますらお・ますらめも
だいぶくたびれたものだと
お互いふっと目を据える
吉凶あいむかい賑やかに東海道をのぼるより
仕方がなさそうな
「娯楽のためにも殺気だつんだからな
でもごらんなさい 桜の花がまっさかりだ
海の色といいなあ
僕 いろいろ花の名前を覚えたいと思ってンですよ
あなた知りませんか? ううんとね
大きな白い花がいちめんに咲いてて……」
「いい匂いがして 今ごろ咲く花?」
「そう とても豪華な感じのする」
「印度の花のようでしょう」
「そう そう」
「泰山木じゃないかしら?」
「ははァ 泰山木 ……僕長い間
知りたがってたんだ どんな字を書くんです?
なるほど メモしとこう」
女の人が花の名前を沢山知っているのなんか
とてもいいものだよ
父の古い言葉がゆっくりよぎる
*
桜と海と
「今日は戦時中のように混みますね/お花見どきだから」とあります。
のり子が7日に帰途についたとして、実際の天気は午前9時以降午後3時頃までは薄曇りです。
吉良吉田から横浜にいたるまでの東海道本線沿線はずーっと天気はあまり変わらず、気温も10度前後で推移していたようです。肌寒いながらも、桜が美しく咲き誇っていたことでしょう。

桜の咲き具合の裏を取ってみます。
気象庁の記録によれば、(定点を当時の準急で浜松から1時間ほどの静岡として、)1963年の静岡の桜の開花日は3月30日でした(ちなみに横浜の開花は4月1日)。静岡の現在までの開花の平均値は3月24日ですから、当時はけっこう遅めの開花だったことが分かります。
満開は開花日より約10日先のこと、つまり4月7日というのはだいたい7分咲きほどの、これから本当に美しい見ごろを迎えつつあったということです。
そして列車は7日が日曜とあらば、それこそ混んでいたことでしょう。


「でもごらんなさい 桜の花がまっさかりだ/海の色といいなあ」。
満開前の桜のいちまい一枚の花びらの先に集積した美しい韓紅(からくれない)の赤と、車窓から見える相模の海(夏には赤いカンナが印象的だという根府川駅からの海も目にしただろう)の、瑠璃や露草色の青。やや薄曇りではあったけれども、その混雑のにぎやかさに重なった色彩のあざやかさ…、そして、登山帽の陽気さ。
これはもはや弔いのあとのしんみりとした風情ではなく、憂いつつ寂しげな「十一月の風」の色どころではなくなっています。寂寥に対して歓喜の色の対照、その対比が際立ちます。
そして、「僕 いろいろ花の名前を覚えたいと思ってンですよ/あなた知りませんか? ううんとね/大きな白い花がいちめんに咲いてて……」/「いい匂いがして 今ごろ咲く花?」/「そう とても豪華な感じのする」/「印度の花のようでしょう」/「そう そう」/「泰山木じゃないかしら?」という会話が差しはさまれます。
登山帽のこと
少し先走りますが、ここで冒頭から登場した登山帽の男性がいう材木屋に触れます。
私が材木屋と聞いて思い浮かぶのは原木市場(の経営者)か製材所もしくは木材販売店ですが、実際は製材所のような気がします。というのは、原木市場なら山から伐り出した様々な種の原木について触れるでしょうし、販売店なら材木屋のあとに「銘木を扱っています」とか二言めがありそうだからです。
とはいえこのことは詩に影響を与えるものではありませんが、ただしいずれにせよ、この男性は自分のところに持ち込まれる木(多くは針葉樹でしょうが)がどこで育ったものなのか、どこから運ばれてくるのかその辺の事情については明るいのだろうと思います。
そして男性がかぶっている登山帽です。
この登山帽という帽子はいったいどんなものを指すのでしょう。
私はのり子とちょうど30歳ちがいの1956年の生まれで、かろうじて登山帽のイメージを持つことができますが、現在この言葉は完全な死語となっていると思います。
たぶんですが、のり子が形象した登山帽はチロリアンハット(チロルハット)でしょう。つまり、つばがせまくうしろを折り上げた形で、クラウン(=山。帽子のパーツ用語)の立ち際に飾りのひもが巻かれるのが一般的な特徴です。登山家に愛されていた帽子です。
私は少しは山に登りますが、現在の山登りにあってこのチロリアンハットをかぶるひとはまず見かけませんし、現在では野球帽のようなキャップ、または日差し除けのつばの広いハットが普通です。
したがってこの登山帽はある時期だけに共通してイメージできる時代の指標物とも言えるものでしょう。「ガリ版」や「ワタナベの粉ジュース」(笑い)、近くは「ポケベル」と同じです。
当時でも一般のひとびとが登山帽を市中でカジュアルにかぶるというのはイメージしにくく、よって登山帽をかぶっていたというのは、男性は少なくとも普段から低山くらいには登っていた、山歩きを趣味としていた、したがってそれは土地や標高のちがいによる植生も肌で感じとっていた可能性もあるということでもあります。
そこでです、山歩きをし木の事情に明るい者が春先の野山に自生するマグノリア(モクレン科モクレン属)のコブシの名を知らないことってあるでしょうか。



コブシは野山に自生するだけでなく街路樹にもされる木ですし、公園などでも見かけるはずです。仮にもしコブシの名を知らなくても、いくら何でも家庭の庭にも植栽されているハクモクレン(白木蓮)を知らない訳はないでしょう。
ならばここは、「大きな白い花がいちめんに咲いてて……」についで、「木蓮の花を少し小さくしたような…」が挿入されてしかるべきです。
のり子と山歩き
それから片やのり子としたら山歩きを趣味としていたでしょうか。
いやいや、略歴を眺めても書いたものやインタビュー記事をふりかえっても山の魅力や野山の花々の美しさについて書いたり語ったりしたものを私は知りません。
のり子は詩に辛夷を登場させますが、これとて山野の自生種ではなく、市中の植栽されたものからの覚えでしょう。東京にも、昭島とか日本橋小伝馬町にもみごとなコブシ並木があるようですし。
のり子には山や、野山の植物に関する詩が3つほど確認できます。
ひとつは「六月の山」というもので、これは山とカメラの雑誌『山と高原』の1960年6月号に掲載されたものです。
貝殻の化石から思う山のこと海のこと、かつては許されなかった女性の山登り…、そんな主旨のエレメントが見え隠れしています。
もうひとつに「山小屋のスタンプ」というものがあります。
これは(「花の名」の発表のあと)66年8月号の『装苑』という婦人誌に掲載されたものですが、これはまず写真が先に作者に提示され、それに合わせて詩がつくられたもののようで、行間からは実体験がともなってはいない印象を受ける内容となっています。

もうひとつは「まんさくの花」です。
これは1975年に『復刊四季』(潮流社)という雑誌に掲載されたものです。
作中にこんな箇所があります。
「まんさくの花は どんな花/おもいおもいしてきたら/三年前/ようようのことめぐりあう」とし、ついで、山形県は出羽三山詣での要衝・岩根沢に疎開した詩人の丸山薫を思い出しています。丸山の知られた詩にまんさくをうたったもの(「白い自由画」)があるのです。
この「まんさくの花」は当時の四季派詩人の代表格の丸山への追悼の意味も込められていたようです。
マンサク(万作)の花をようやくにして見たとは、のり子の普段の暮らしが山や野山の自然から遠いものであったかを物語るものでもありましょう。
以上この3つの詩篇はのり子自身がかかわった選集や詩集に入れなかったのは無理からぬことだったろうと思います。やはり、リアリティに乏しく、言葉の美しさと強さがまるでないことは本人の自覚にあったことでしょう。
のり子は基本、山歩きの楽しみやそれについてくる植生への関心は薄く、多くを知らなかったのではないでしょうか。
登山帽の「ううんとね/大きな白い花がいちめんに咲いてて……」を受けてのり子は、「いい匂いがして 今ごろ咲く花?」「印度の花のようでしょう」と答えをしぼっていきます。
「印度の花よう」とは言い得て妙とは思いますが、私にはまったくそのイメージを持つことができません。そして、この修飾にどれほどのひとが(登山帽の男性のような相槌で)、「そうそう」と口をついて応じることができるでしょう。
この、登山帽が聴き、のり子がこたえる部分こそがこの詩の最大の脚色部分、フィクション性をあらわしていると私は思いますがどうでしょう。
註
※1 死去のあとの葬事の流れと執り行い方については大きな地域差がある。当時の宮崎洪の葬事については、当地方西尾市の葬儀社とのやりとりをもとに順序立ててみた。
※2 当時の気象データは、気象庁の1963年の名古屋地方気象台の、吉良吉田を含む西部区域の記録に依っている。
※3 東海道本線の運行ダイヤについては、当時の時刻表(1963年6月号…他の号はなかった)を参照した。地元の図書館には保管がなく、山形県立図書館の協力を得た。
※4 当時の気象データは、気象庁の1963年の名古屋地方気象台の、吉良吉田を含む西部区域の記録に依っている。
※5 詩「六月の山」、「山のスタンプ」、「まんさくの花」は宮崎治編『茨木のり子全詩集』(花神社2010)の「拾遺詩篇」で確認した。この全詩集からは初出一覧等大いに参考とさせていただいた。
茨木のり子「花の名」をめぐって 2 につづく。
*
それでは、本日はこのへんで。
じゃあまた、バイバイ!
※写真のクレジットの“web”があるものは、web上からの借用です。それ以外は筆者の撮影もしくは友人知人からの提供を受けたものです。
※本文に割り込んでいる写真はサムネイル判で表示されています。これは本来のタテヨコの比から左右または上下が切られている状態です。写真はクリックすると拡大し、本来の比の画像が得られます。